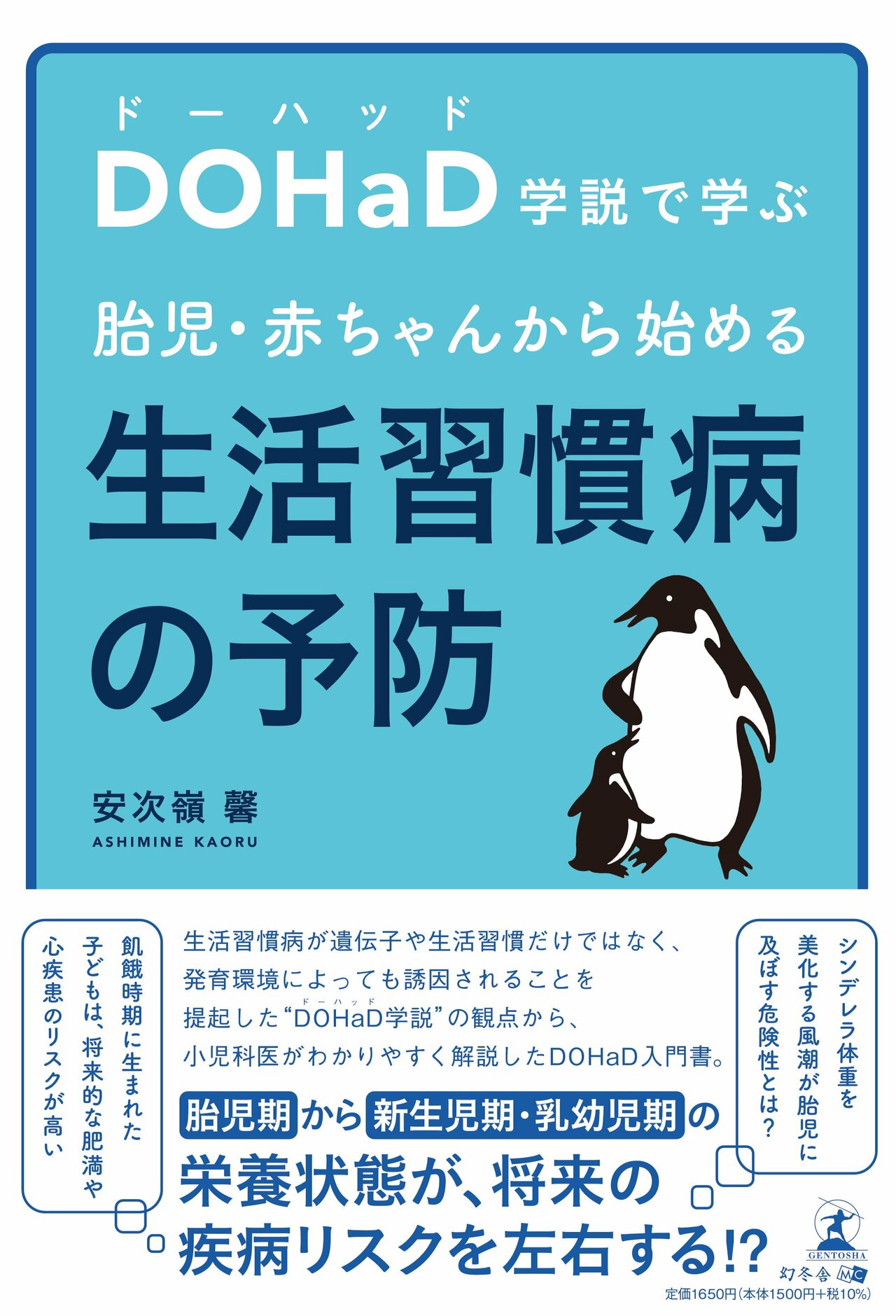2001年、バーカーはフィンランドのヘルシンキ大学との共同研究で、低体重児が2歳以降、急激な体重増加をきたした群に、心疾患とインスリン抵抗性がみられたことを報告しました4,5。
この共同研究は、バーカーのオリジナル論文に欠落していたデータを補強する極めて重要なものでした。バーカーは著書(『The Best Start in Life』)の中で、この共同研究について、次のように述べています。
「ハートフォードシャー台帳が、ツタンカーメンの墓所の入り口を開く扉だったとしたら、ヘルシンキ公衆衛生研究所の100年に及ぶデータは、墓の内部に足を踏み入れることだった」
この共同研究はFOADからDOHaDへとバーカー仮説が発展する転機となる重要な機会だったといえます。
バーカーの発見は、新しい研究分野を拓き、世界の科学界に多大な影響を与えました。バーカーは2003年に引退しましたが、その後も、精力的に執筆活動、講演活動を続けました。晩年の目標は、彼の学問研究を一般市民に知ってもらうこと、とくに思春期の女性、妊婦、乳幼児の健康を改善し、健康社会をめざす新たなる公衆衛生戦略を作ることでした。
バーカーの最大の功績は、「悪い遺伝子と悪い生活習慣が慢性病を招く」というそれまでの常識を根本的に変え、人々の健康な生活を約束する公衆衛生上の新たなる思想を生み出したことと、私は考えます。
2│予測適応反応(Predictive adaptive responses, PARs)
グラックマンとハンソン(Mark Hanson)は、2004年以降、それまでのバーカー仮説に関する夥しい研究論文、また批判論文などをレビューし、Developmental Origins of Health and Disease(DOHaD)という装いを新たにした学説への道筋をつけました。
慢性非感染性疾患、すなわち生活習慣病の発症は、遺伝子や生活習慣のみに影響されるのではなく、人の発育早期の環境によっても大きく影響されるということを明確に述べました。そのキーワードの一つが「予測適応反応」という概念です6,7,8。
このことを、少しわかりやすくいうと、胎児が発達する感受性期に、栄養不足や酸素不足で子宮内環境が悪化したとします。この状態で胎児のとる反応は、まず、生き延びるために迅速な適応反応(immediate adaptive responses)として、成長を抑制し、低体重児となることです。
さらに出生後の環境も悪いと想定して、将来を予測する適応反応(predictive adaptive responses)をとります。すなわち、摂取エネルギーを脂肪として蓄積しやすい体質を作ります。