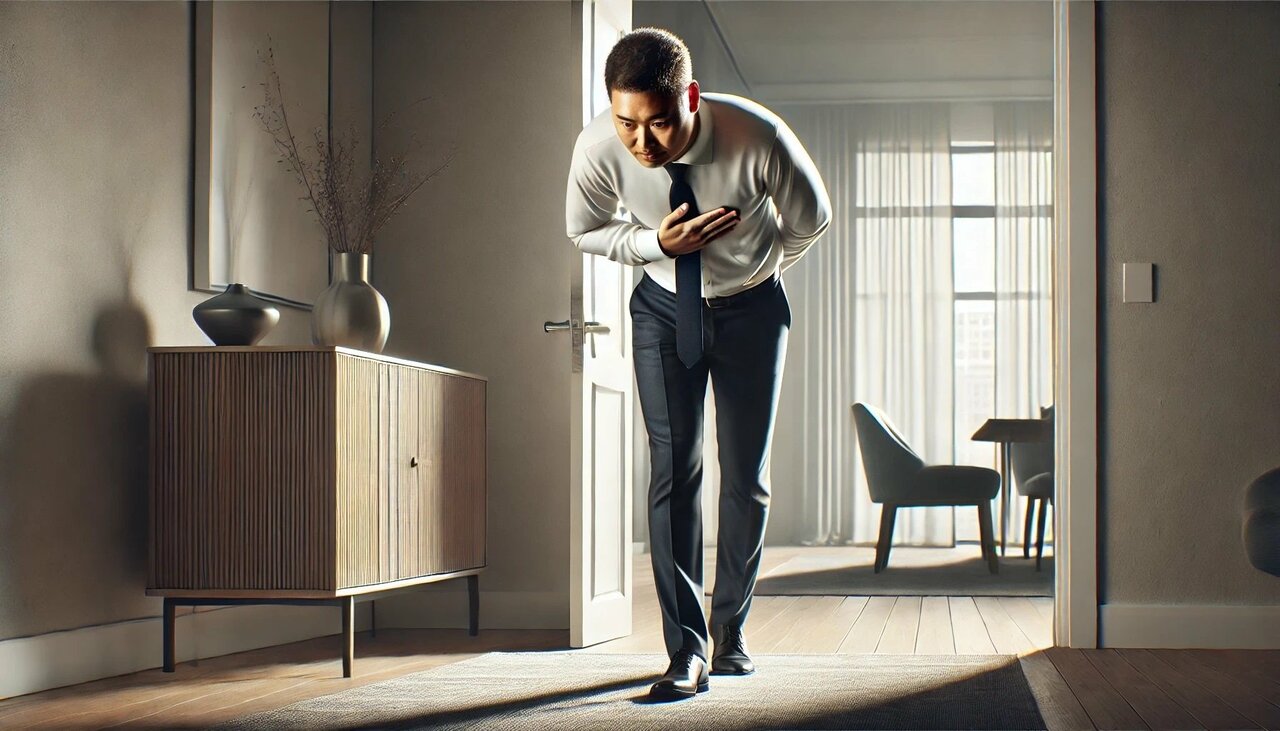早速、翌日の放課後に実践することを心に決める。両親とも残業で遅くなる日にお決まりの夕飯用のカレーを用意している様子を見て、モモはその日の決行を誓った。
とはいえ、簡単なことではない。学校に誰もいなくなるまで待つ必要がある。誰にも見つからずに身を隠しておける場所を授業の合間に探して回る。
そして目に留まったのは、最上階の角のトイレだ。そこは人通りも少ない上に、六年生のクラスの階にも行きやすい絶好の場所だった。
隠れ場所が決まってしまえば、あとは誰もいなくなるまで身を潜めるのみである。帰りの会が終わり、クラスメイトがいなくなるまで、モモは道具箱の整理をしたり掲示物を眺めてみたり、のらりくらりと教室に残る。そして最後の一人がいなくなるのをしっかりと見届け、例のトイレへと向かった。
ランドセルの中にたくさん詰めてきたお菓子を食べながら、時が来るまでひたすら待つ。時間がわからなくならないように持ってきた腕時計を装着し、暗くても大丈夫なように持ってきた懐中電灯をポケットに入れる。
モモは探検隊にでもなった気分で胸が高鳴った。トイレの窓から見る空は、柔らかな青色から淡いピンク色へと姿を変え、だんだんと夜に向かって時を進めていた。
そろそろよい頃合いだろうかと思い、トイレから出てみる。すると、静まり返った暗い廊下がモモを迎えた。いつもよりもひんやりとした空気が体を包み、まるで世界にたった一人だけになってしまったかのような錯覚に陥る。
誰もいない学校の静けさに小さな恐怖心が芽生え始めた。しかし、モモの心は探検隊であり続ける。懐中電灯を取り出し、六年生のクラスの階まで下りていく。
暗闇の中、足音がパターンパターンと響き渡り、誰かの気配を感じては立ち止まる。より一層暗さを増した階段や廊下を、懐中電灯の光だけが頼りなげに照らし続けた。
不安と期待のバランスが逆転した頃、六年生のクラスの前の長廊下の端に到着した。懐中電灯は点けたままポケットに入れて深呼吸をする。そして、壁に腕をつき顔を伏せ、大きな声で言った。
「だーるーまーさんが、こーろーんだ!」
モモの声だけが静かな廊下にこだました。まるで時間が止まったかのように空気が張り詰める。後ろを振り返りたいのに、体が固まったみたいに動かない。いつの間にかモモは恐怖と不安でいっぱいになっていた。
【前回の記事を読む】ある朝物音が聞こえて目覚めると「おはよう」とキッチンに立ち、にこやかに挨拶をする夫が立っていて……
次回更新は9月2日(月)、18時の予定です。