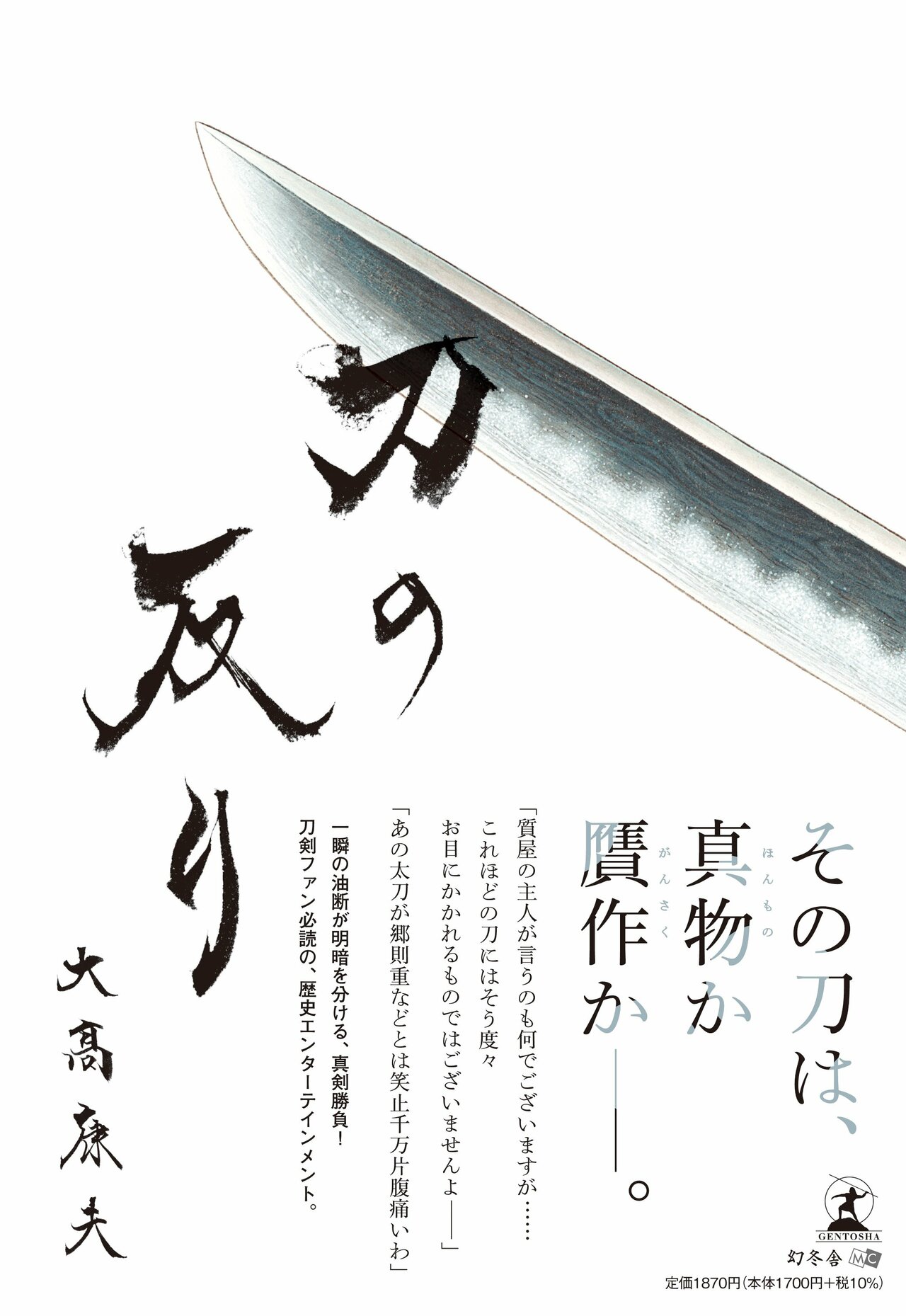山門の前にまで来るとくるりと背を向け、無言でその場から立ち去ろうとする猛之進に弥十郎は声を掛けた。
「猛之進……おぬし、このままでは気持ちも鎮まらぬであろう。少し付き合わぬか」
「付き合う? ……どこへだ。これか?」
猛之進は盃を呷(あお)る真似をした。城勤めになる以前には二人で居酒屋によく通っていたのだが、この二人が一緒に飲むと必ずと言って良いほど喧嘩口論になるのだ。斬り合いにまでなりそうになったのは一度や二度ではない。
その度に周りが諫(いさ)めるのだが、それを幾度か目にしている居酒屋弥勒の主人は、店の入口で二人の刀を預かるようにしていた。預けなければ酒は飲ませないということである。
「おぬしとは暫く一緒に飲んではおらぬではないか。たまには良かろう。それがしが相手だ。少しばかり遅くなろうと瑞江も気にはすまい」
「うむ、そうだな。よかろう弥十郎……おぬしと盃を交わすのも久方振りだからな」
ここまでは良かった。二人がこのままこの場で別れていれば何事も無かったのだが、猛之進は酒と言われて断ることはできなかった。弥十郎も酒には目がないのだが、それにかこつけて何かを論じることが二人は好きなのだ。とは言うものの、最初は互いに相手の話は聞いているのだが、二人の性格から次第に押し問答になるのは必然的だと言えよう。
そこに刃物でもあれば刃傷沙汰になるのは自明の理である。今まで二人が斬り結ぶことにまで至らなかったのは己が家のことを考え互いに自制し、彼らなりにその先を見据えていたのは間違いないことであった。
幕府が私闘を禁じる触れを出していたことから藩としても私的な果たし合いを禁じており、事が露見すれば喧嘩両成敗として互いの家に何等かの処分が下されることは明らかで、軽くても減俸、悪くすればお家取り潰しという厳罰を科せられるかも知れないのである。