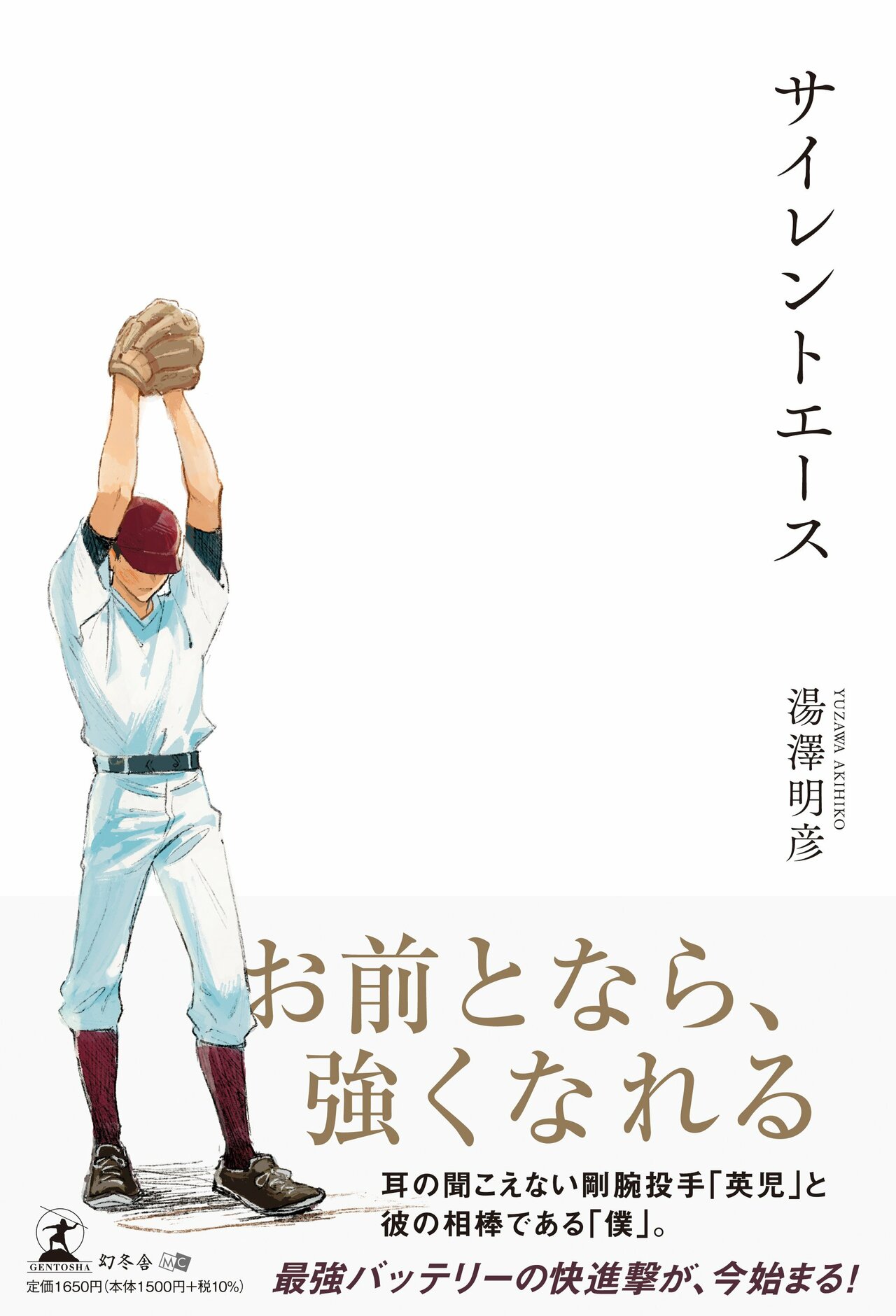「はじめまして。真紀の父親です。今日は呼びつけてしまってすまなかったね」
優しそうな笑顔を浮かべた福田記者は、僕にお茶と和菓子を勧めてくれた。面差しはどこか真紀さんに似たところがあり、奥さん、つまり真紀さんのお母さんもとても笑顔が素敵な方だった。
「はじめまして。湯浅太郎と申します」
「君のことを真紀から聞いて、とても興味を持っていたんだ。仕事がら、野球選手を取材することはいくらでもある。特に近頃は子供の野球離れが深刻でね。その意味でも少年野球の記事に力を入れているんだよ。
そんな中で、地元で有名な沢村君のボールを捕ることが出来るキャッチャーがいるというじゃないか。これは話を聞かないわけにはいかない、そう思ってね」
「いや、本当に僕はたいしたことがないんです。確かにチームであいつの球を捕れるのは僕しかいません。
でも、ただ捕っているだけなんです。しかも、きちんとリード出来ているとはとても言えません。今のままではだめだ、ちょうどそう思っていたところです」
僕の話を聞いて、福田記者はご自分の体験を話し始めた。
「僕は中学生からずっとラグビーをやっていた。高校生でも花園に出場して、憧れのM大学ラグビー部に進んだときは、天にも昇る気持ちだったよ。
ポジションはウイングで、チームの得点源になっているという自負もあった。大学日本代表合宿に呼ばれるまで、その自信はずっと続いていた」
そこで、福田記者は少し間をおいて静かに言った。
「四年生の日本代表合宿で、僕は足に大けがを負った。最初はすぐに治ると思っていた。
でも、足の腱が断裂して、全治1年以上と言われた。目の前が真っ暗になった。『なんで俺なんだ、なんでこの時期なんだ』って何度思ったか分からない。
結局大学生時代に完治することはなく、ラグビーのトップリーグ、今は名前が変わったが、そこのどのチームからも声がかかることはなかった。悔しかった。
でも、スポーツにかかわることは諦められなかった。その僕を変えたのが、この『江夏の21球』なんだ」