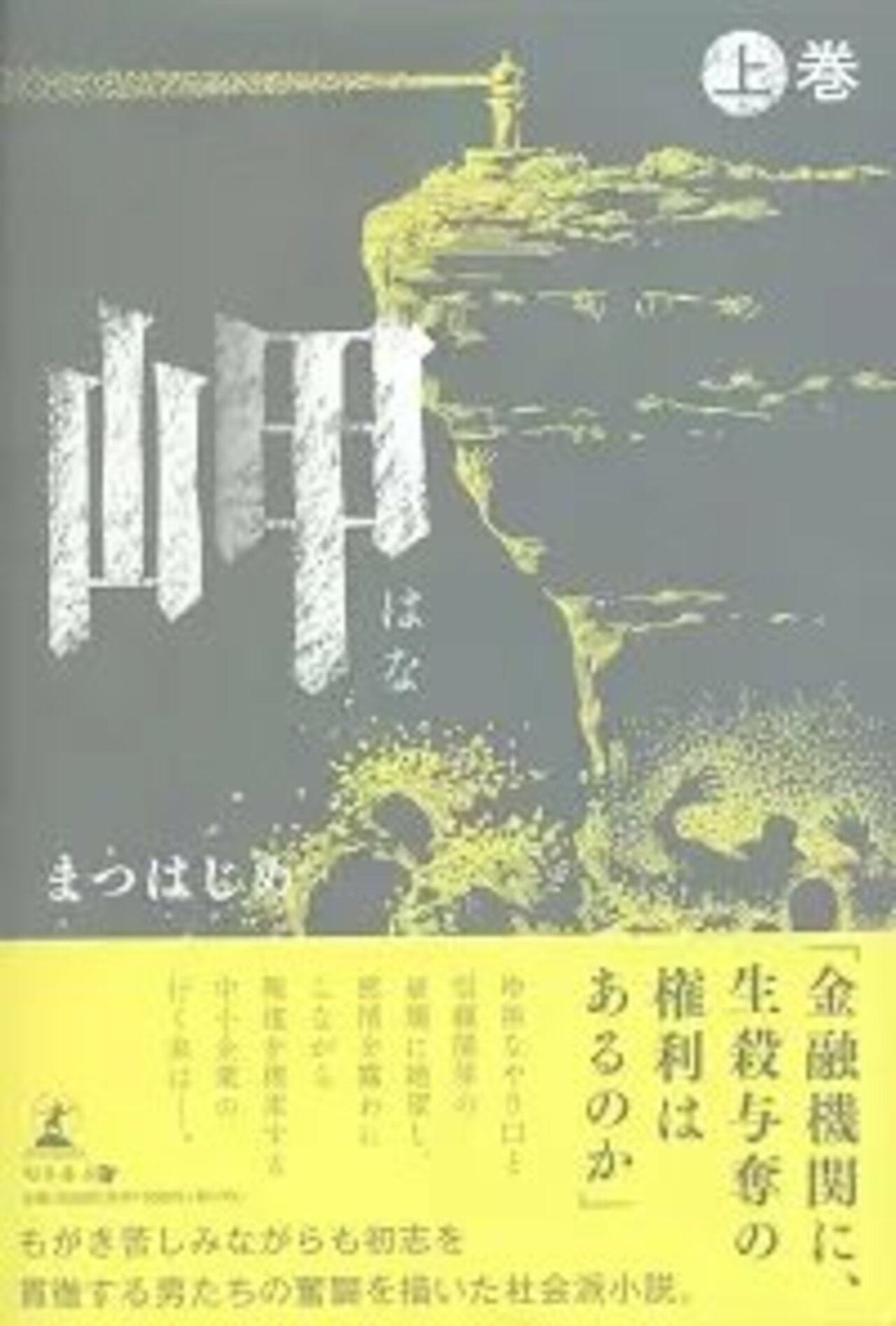全く、田舎者扱いだ。田舎の会社にそんなものが造れるか、と最初から決めてかかって、製品の話を聞こうともしない。話の糸口さえ掴めない。4、5歳下の者からこんな扱い受けて、馬鹿にするのもいい加減にセイ!と席を蹴って帰りたかったが、グッと我慢した。
松葉は悔しくて、悔しくて、涙をこらえるのが精一杯だった。
帰り際に受付嬢にお辞儀はしたものの、とても声に出しては言えなかった。
松葉は、ホテルに帰って考えた。
こんなぶっつけ本番みたいなことをやっていては、同じことの繰り返しになるだけだ。東京というところは、アポイントなしではことが進まないところみたいだ。
今まで、アポイントを取って訪問すると、相手の時間を束縛するみたいで申し訳ない、という気持ちが松葉にはあった。
近くに来たので寄ってみた、と言ってよく訪問していたが、よくよく考えてみると、相手は不意に来られて、えらい迷惑だったに違いない、ついでに来るくらいなら、来てもらわなくて結構と考えていたに違いない、考え違いもいいところだった。
アポイントを取らずに会えたとしても、あんな青二才しか現れない。これでは、嫌な思いをするだけだ。どこから来たのか分からない馬の骨とは、誰もまともに会ってはくれないだろう。
よし! アポイントを取ることにしよう。
アポイントを取るにはどうしたらよいか、松葉は思案した。
高校の友達や先輩の伝手を頼ってみてはどうか、とも考えてみた。
しかし、松葉の出た聖ザビエルス高校は、松葉が11期生という新しい高校だったため、同窓生はまだまだ自分のことで手一杯、働き盛りで時間もない。