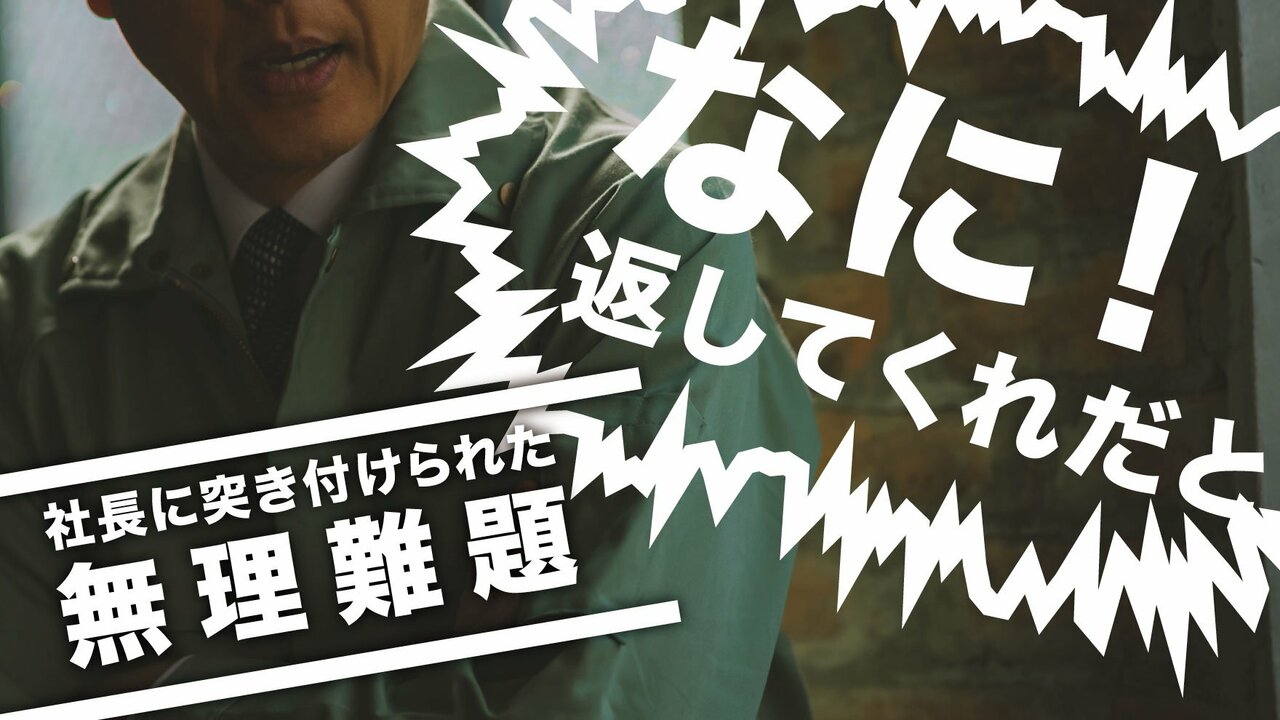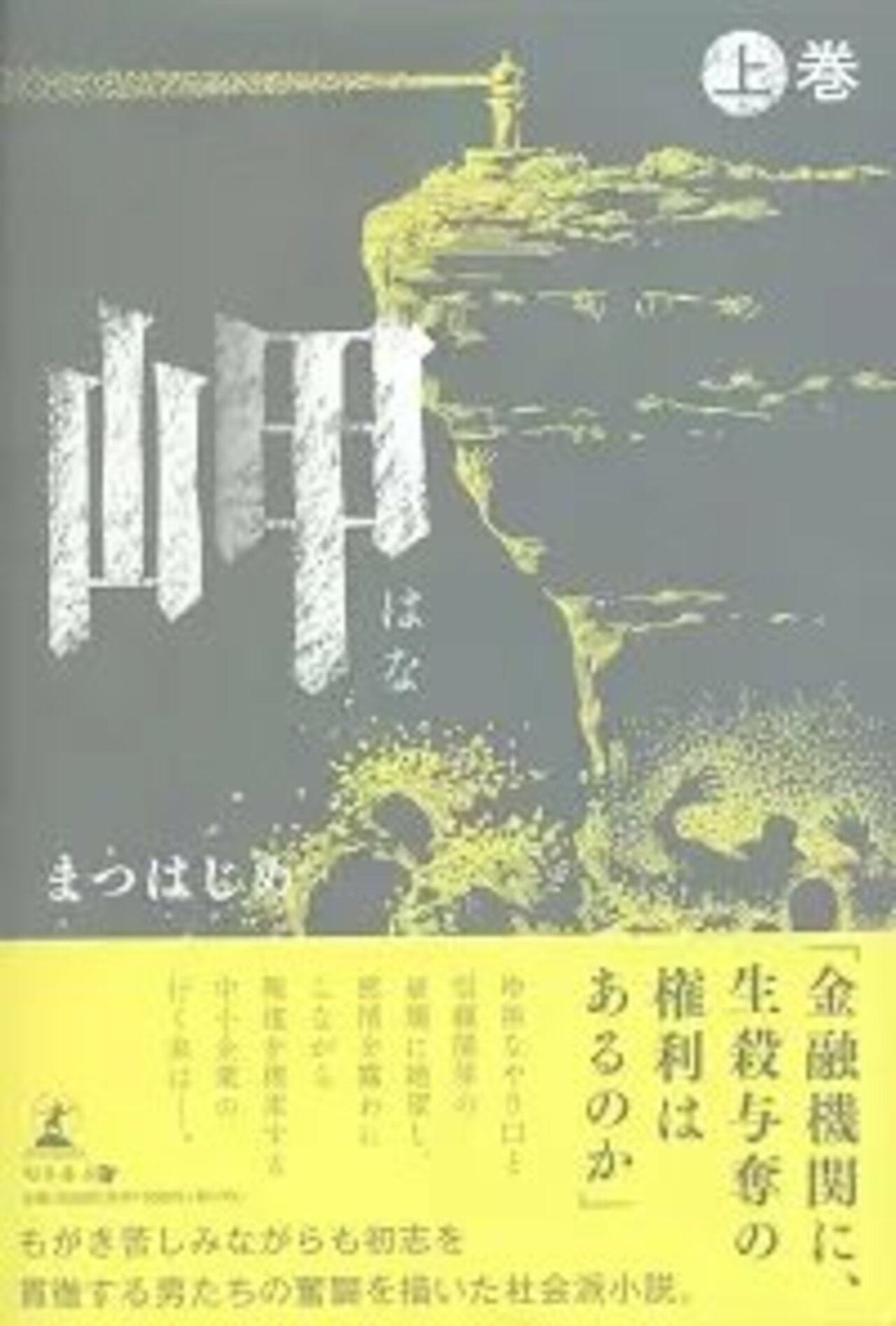第1章 貸し剝がし
返済強要
「なに! 返してくれだと」
鹿児島第一銀行から帰ってきた経理部長の佐久智広の報告に、社長の松葉哲造はびっくりし、怒って佐久に言った。
「はい、切り替えはできない、とのことです」
小さな声で申し訳なさそうに、佐久は応えた。松葉が社長に就任する16年以上前から手形貸しと呼ばれる方法で借りてきた5千万円を返せという。
3か月に1回、手形の期日が来ると、また3か月先の期日の新たな手形を切り替えるやり方で、借りてきた5千万円だ。そんな馬鹿なことがあるか。今まで、鹿児島第一銀行との取引は、どちらかというと、鹿児島第一銀行の希望に沿う形で行われ、友好的な関係が築かれていた。
銀行側の営業に協力しながら取引が行われていたといっても過言ではなかった。鹿児島第一銀行が松葉工業のメイン銀行であることを営業の武器にして、この地方の地盤を築いてきたことを、ここでは知らない者はいない。
「今までに、そんな話があったことがあるのか」
佐久を問い詰めるような口調で松葉は聞いた。
「いいえ、初めてです」
「誰が言ったのか」
松葉は、信じられないという顔をしながら、念を押すように佐久に聞いた。
「融資担当の古賀さんです。取り敢えず、一旦返してくれとのことです」
そんな筈はない、もう16年以上借りっ放しだった5千万円だ、こちらが貸してくれと言って、借りた金でもない。金利だけ払ってくれていればよい、と歴代の支店長が言っていた、しかもたいした金額でもない、何で今になって急に返せと言い出したのか、松葉には解せなかった。分からない。何があったのか。
松葉は、3年前、鹿児島第一銀行から出向してきた常務取締役の外村紀実雄に聞いてみようかと思ったが、思い留まった。外村の仕事振りに、松葉は彼に寄せてきた期待感が色褪せていくのを、最近特に感じていた。聞いてみても納得の得られる説明はできないだろう。支店長に直に聞いてみた方がよい、と思ったときには既に松葉は電話の受話器を取っていた。