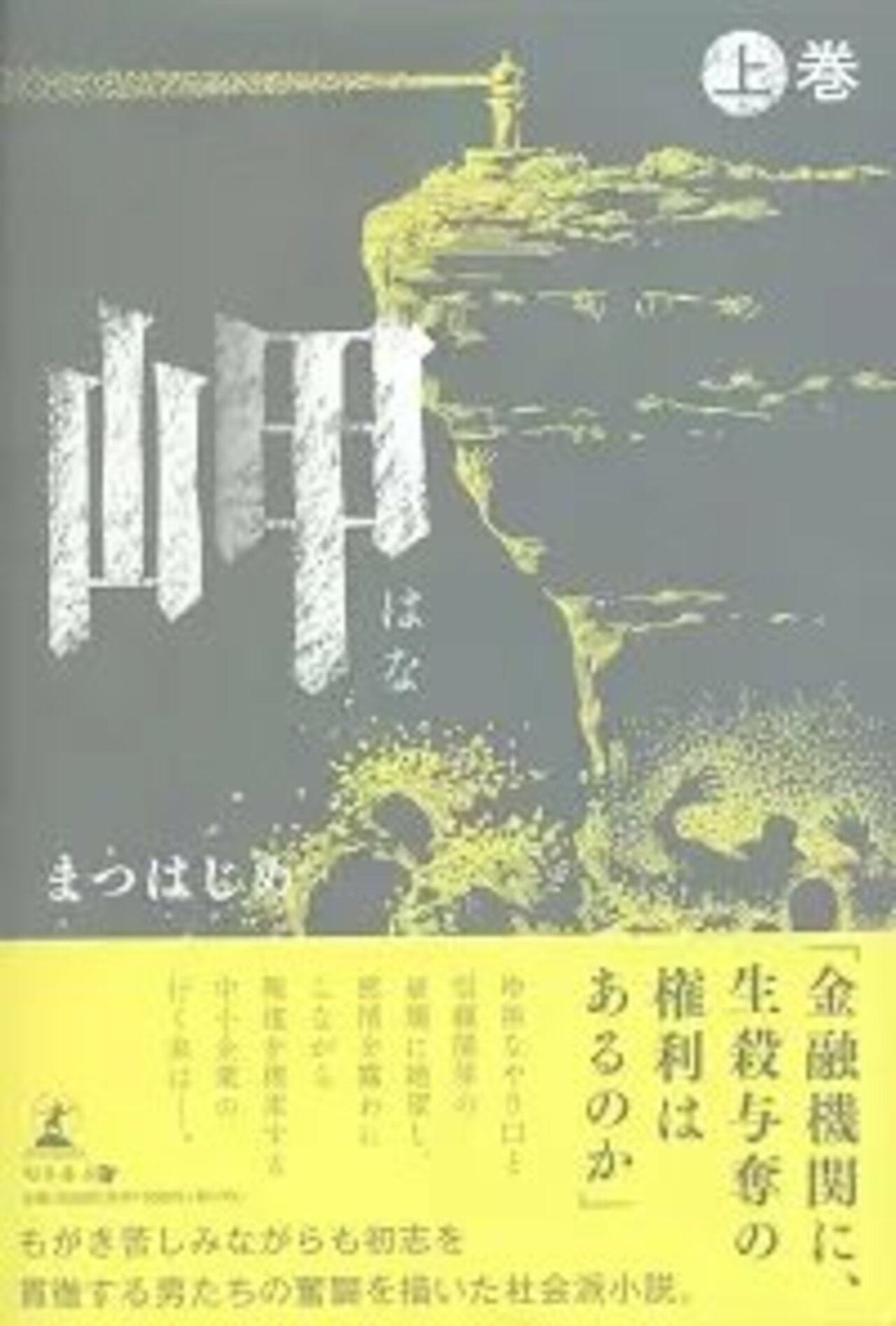第1章 貸し剝がし
返済強要
まだ、10月というのにこの日は肌寒く、辺りはどんよりとして、今にも雨が降り出しそうな気配だ。松葉は、事務所を出ると、自分の車に駆け乗った。
午後5時前ということもあって、道は空いていた。南九州の人口13万余の小さな田舎町ではあるが、最近では、信号2、3回待ちのラッシュに出くわすことも珍しくなくなった。
特に軽乗用車の多くなったことに松葉は驚いていた。一軒で3台の車を保有しているところも多い。交通手段が他にないこの田舎町では、車は必需品になっている。
殆ど、ドアツードアで行き来している。そのせいか、最近の田舎の人は歩かなくなって、都会の人に比べて足腰が弱ってきているという。松葉は、最近の世相に思いを馳せながら、鹿児島第一銀行の都城支店へと急いだ。
銀行の駐車場はガランとしていて、2台の車しかなかった。通用口に一番近いところに駐車して、通用口のインターホンを押した。ピーンポーンという音と同時に、「どちら様でしょうか」という女性の声がした。
「松葉工業の松葉ですが」
「すぐ、伺います。今しばらくお待ち下さい」
誰に用があるかとは聞かなかった。既に支店長から伝えてあったのだろう。
程なく、ドアが開錠される音がした。
「いらっしゃいませ。お待ち申し上げておりました。どうぞ」と支店長応接室に通された。
部屋に入るなり支店長も現れて、大きな声で
「いや、松葉社長さん、いつもお世話になりましてありがとうございます。ここのところお会いしていませんでしたね」