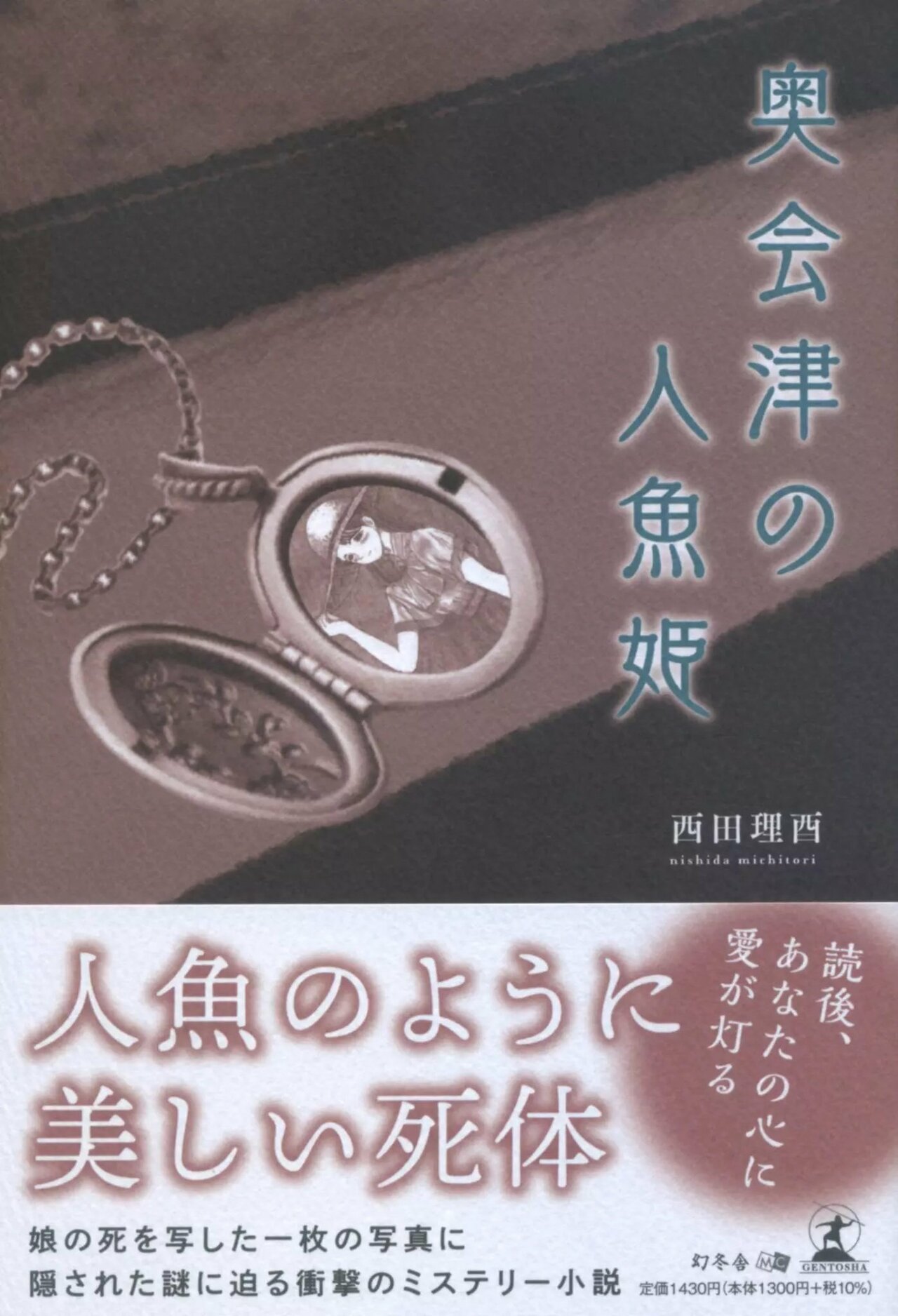「時に、汐里の記憶が飛ぶって話を聞いたことがあるか?」
すると千景は、何を言っているんだという顔で鍛冶内を見た。
「残念ながら俺の思い出す汐里のイメージは、たまに顔を合わせるたびに、俺を小馬鹿にしたような目で一瞥をくれるだけの、ぞっとするほど冷たい横顔をした女なんだ。
汐里は俺との一切の関わりを拒絶していた。だから汐里に何かの疾患があって、記憶が飛ぶような症状が表れていても、たぶん俺にはわからなかっただろう」
「本当に世話になったね、乙音ちゃん。千景の世話は大変だろうが、お腹の子のためにも、あまり無理しないようにね」
「ええ、嬉しいわ。ありがとう、おじさま」
「あ、そうだ。これを渡すのを忘れるところだった………」
そう言うと、鍛冶内はおととい柳瀬町で調達してきた赤色と黒色の二つの漆のワインカップを鞄から取り出し、さらにはそれを覆っていた布をほどいた。
「今回うっかりとおみやげも買ってこないで失礼したからね。一つは乙音ちゃんに、そしてもう一つは千景に、と言いたいところだけど、乙音ちゃんとお揃いで俺の晩酌用にさせてもらおうかと思ってる。
これで飲みながら、乙音ちゃんを思い出すよ。ふふ、俺にだってそのくらいの役得があってもいいだろう? 千景には次に来た時にでも何か買ってくるから今回は許しておくれ。という訳で、どちらか選んでくれるかい? どれ、じっくり見て選んでもらいたいから、一つずついくよ」
鍛冶内から手渡されたのは、高さ20cmほどの足のある会津塗りのカップだった。それを順番で一つずつ手に取ると、両手で持って、あちこちの角度から眺めていた乙音だったが、やがてにっこりすると黒色のほうを手元に引き寄せた。
「大事にするわ。また来てね、おじさま」
ふり返ると、送ってきた車の運転席で、乙音は軽く目頭を抑えているように見える。自分のために泣いてくれてるのか。そう思うと、鍛冶内は言い知れぬ思いに、胸が一杯になった。
「しかしどう考えても……」
と、鍛冶内は考えた。あの子が他人を陥れるようなことをするのだろうか、と。幾度考えても鍛冶内の中で、解けない謎がループを繰り返していた。
【前回の記事を読む】死んだ娘に掛かっていた6000万円の保険金…。双子の片割れにはアリバイがあった。