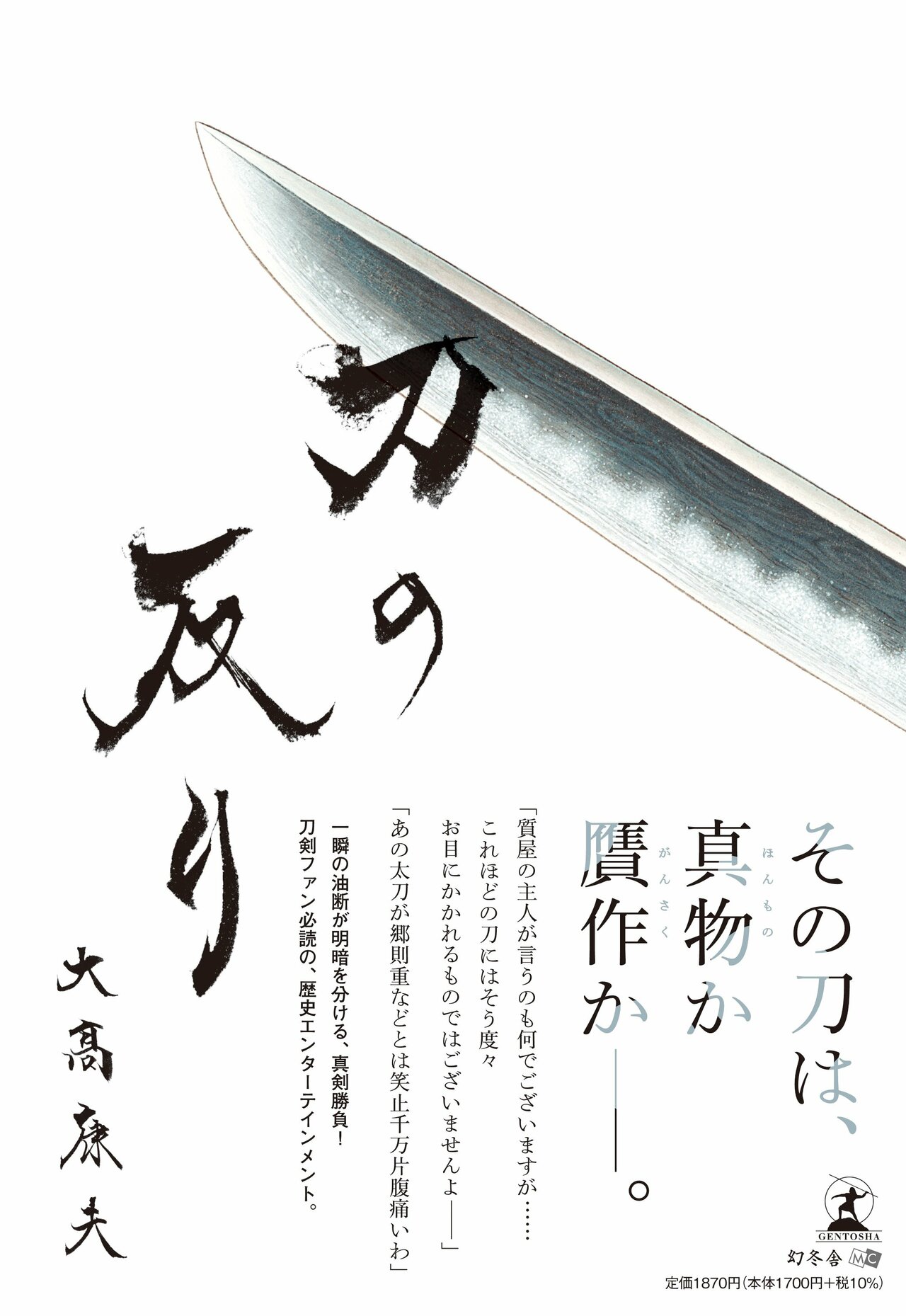「何だと、猛之進。言うに事欠いて僻目とはなんだ。おぬしの方こそ見てもらうのが怖いのであろう。これが則重ではないと言われたときのおぬしの顔が目に浮かぶわ」
向かい合う二人の目尻が吊り上がっていた。今にも刀の柄に手が掛かりそうであった。
「まあ、待ちなされ二人とも。わしが思うにこの太刀が真物でも贋物でもそのようなことはどうでも良いではないか。この刀は家宝として須田の家に伝わってきたものじゃ。それこそ真物というべきものであろう」
恵泉は諭すように優しげな目で交互に二人を見ると、少し考えるように間を置いた。
「のう、猛之進殿と弥十郎殿……おぬしたち二人は幼少の頃からこの和尚がずっとこの目で見守ってきた。そこもとらは藩中でも秀でた剣の遣い手であることは誰しもが認めるところだ。
しかし、じゃ……長ずるものが剣だけでは武士として傑物とは言えまい。勿論、太平の世とは言え文弱の徒と言われては藩……いや己を守ることさえ覚束ぬよの。
しかるに、おぬしら二人に欠けておるのは他人を思いやる気持ちじゃ。それがなければ常に人と争うことになる。況(ま)してや、おぬしらは既に隠居した父御(ててご)の跡を継いで城勤めの身ではないか。
いつまでも元服前のような気持ちでいては父御や母御(ははご)が安穏とした余生を送れぬぞ。どうじゃ、弥十郎殿。これはそこもとが言い出したことじゃ。それに義兄としての立場もあろう。ここはおぬしが鉾を収めねばなるまいて」
【前回の記事を読む】雌雄を決することができなかった竜虎と呼ばれた二人は決着をつけようと立ち合いをして…