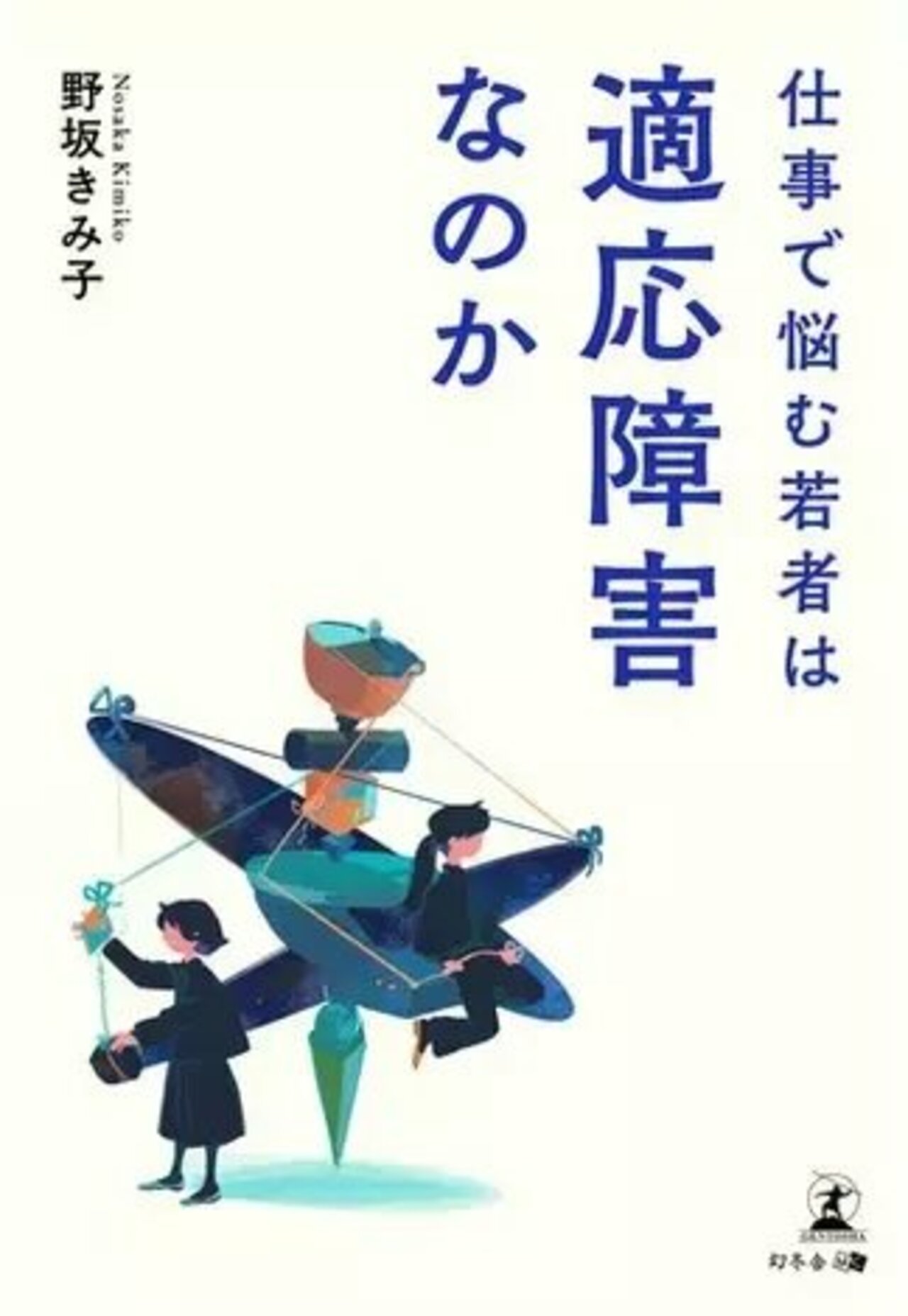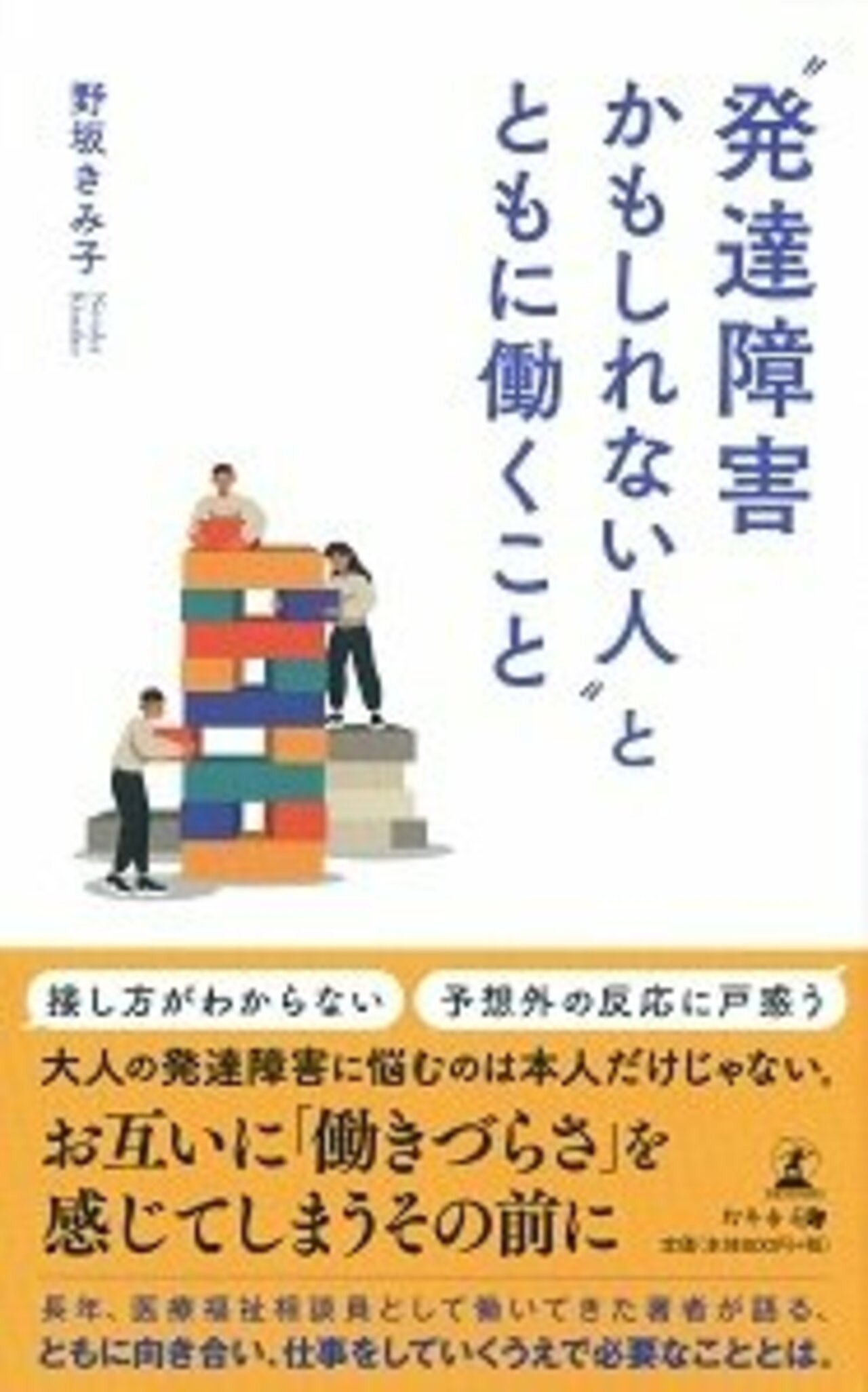第6章 働くことは複雑になっている
働くことの変化
このような状況に会うと、まず若者の精神的な状態や変化に目が行ってしまいます。若者が弱くなったのではないか、甘えているのではないか、新世代なのではないか。
今はZ世代などと言われています(1990年代後半から2012年頃までに生まれた世代で、デジタルネイチャー、スマホやSNSが生まれた時から当然のようにあった世代を指しています)が、戦後ずっと新人類、ゆとり世代等々、これまでと違う感覚を若者に感じると名前をつけていたように思います。
しかし若者が勝手に変わるわけではありません。大きな社会の流れがありますが、働くことに関しても大きく変わってきています。特に最近は今までにない変化を見せています。
戦後の働くことの変化を大雑把にとらえてみますと、敗戦後生きること食べることに精いっぱいで、国を再興し、皆が食べられるよう生活していけるようにするのがまずもっての目標でした。
産業を再興し外地から帰ってきた人たちにも職を与え、生活して行けるように賃金を支払う、まさに生活給です。そして保障としての終身雇用。家族は男性の働き手と妻と子どもと老親というセット。年金も充実していなかったので高齢者の扶養も含まれていました。
そして国としての復興は資本主義社会としての再建であり、経済の復興を目指すために男性は戦士のように働き、妻は銃後の守りで家庭を守ることが期待されました。まさに時代の要求です。
そしてその努力は実り高度経済成長に突入します。生活は豊かになりましたが、多くの人が都市に集中し、地方の過疎化や公害など多くの問題も生み出していきました。