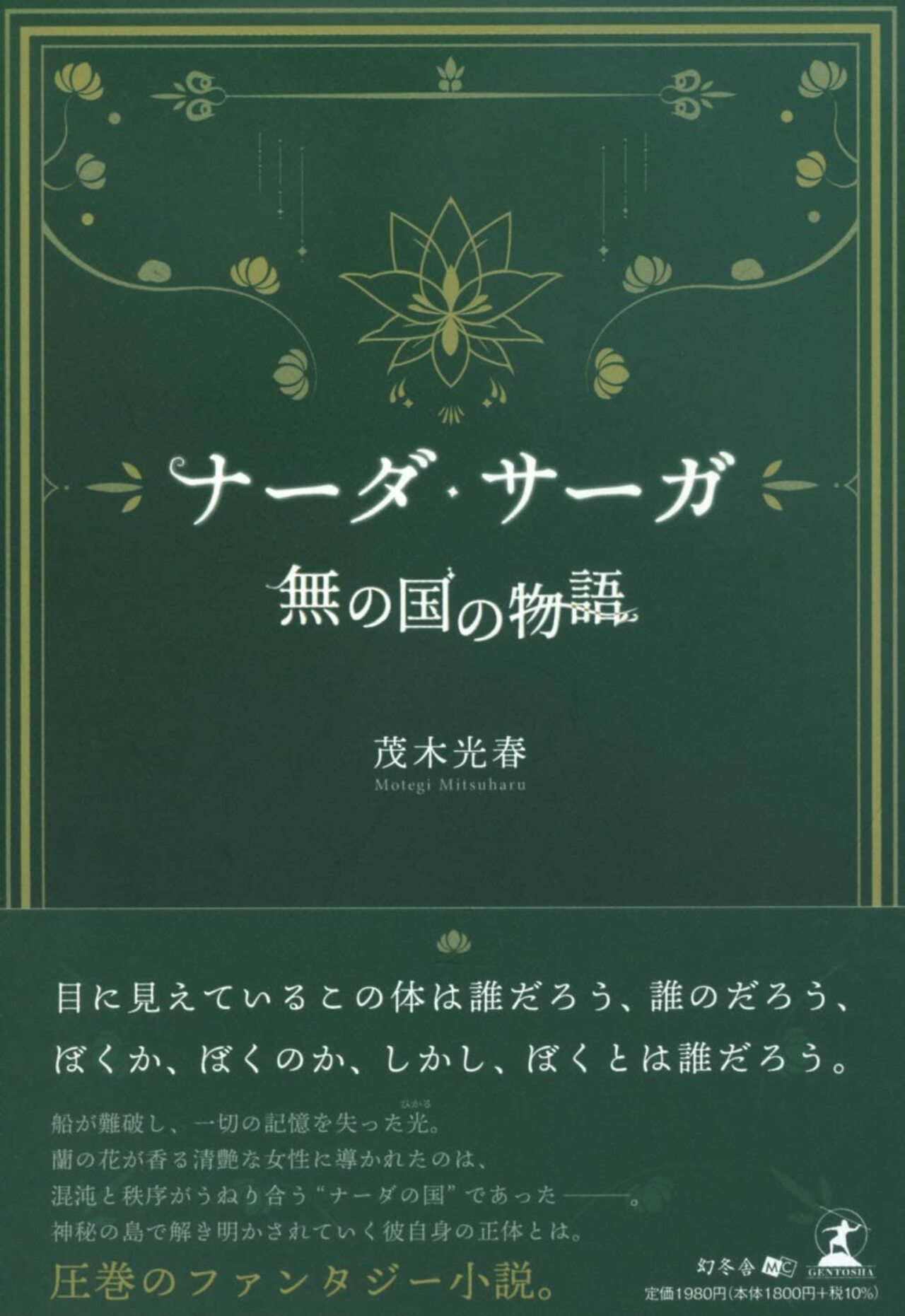さらには別の樽の脇腹には「babel fish」と書かれてあって、「バベルの魚」というものか、しかし、たとえそう書かれてあったとしても、それがどういうものかさっぱり見当がつかなかった。
主人の傍らには何十個もの鉢植えの苗木があって、その一本一本には名前がついていた。たとえば、「聖書の木」とか「三国志の木」とか「アラビアンナイトの木」とか「論語の木」とか「万葉集の木」とか「源氏物語の木」とか「ハムレットの木」とか「ドン・キホーテの木」とか「芭蕉の木」とか「チャタレイ夫人の恋人の木」とか「吾輩は猫であるの木」とか「易経の木」とか、そんな名前がついていて、やはり何のことやら分からなかった。
そこに集まった者の中にやはり分からない者がいて、店の主人に向かって質問すると、百歳の漱石先生がつまらなそうに言ったものである。
「分からないものは分からないでいいです。無理に分かろうとする必要はないです」
「それじゃあ商売にならないんじゃないですか」
質問した客が反論した。
「私は百年後の客を待っています」
漱石先生は憮然とした面持ちで言った。
「それではあなたもぼくも死んでしまうではありませんか」
「世には売り手が死んでから買い手がつくという品物があるのです」