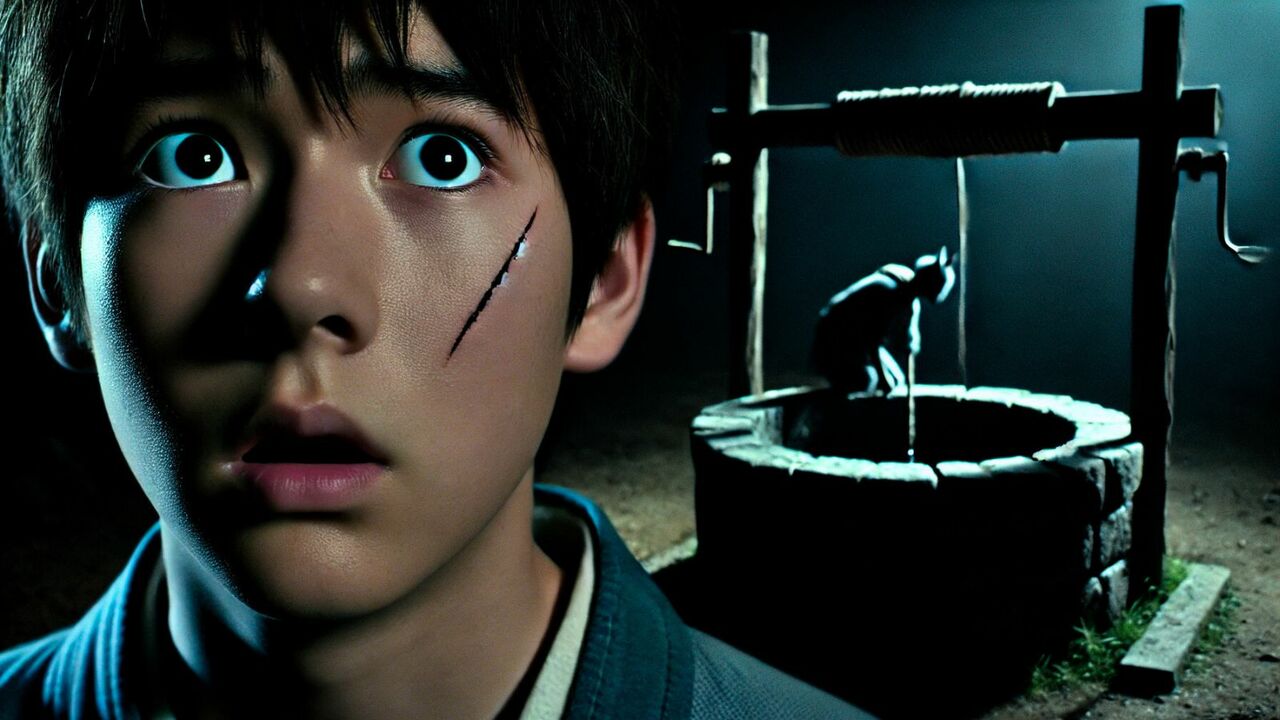まだ十四という歳でありながら五尺五寸と当時の人びとの中にあっては大きく、鍛え抜かれた体躯と隠し切れぬ品格がそこから溢れ出ている。
一見すると、どこぞの若い武者修行の武芸者に見えなくもない。
がっちりし大柄な源五郎と、小柄で明らかに百姓と見える熊吉との連れ合いは、武者修行中の若武者とその下人、といったところが妥当であろう。
が、本人は食い詰めた牢人を気取っているらしい。
そこで熊吉の本音がこぼれた。
「やっぱ源五郎様は牢人には見えませんでごいすな~」
「そうかな?」本人は上手い事牢人に化けているつもりであろうが、扶持(ふち)を得られず流浪する牢人の惨苦は滲み出るものであり、演じようとて演じられるものではない。
もしそれが演じられるとすれば、それはもう忍びの術の一つと言ってよいものであった。
そして牢人にしては若すぎた。
「やはり~武者修行中の若様……って感じでごいすなぁ」
「武者修行者には武者修行者の掟があるのではないか? 俺はそんなもの知らん」
「そりゃぁそうでしょうが……」
「まぁ思い悩んでもいたしかたあるまい。なるようになるだろうし、旅の折々で何か良い思案が浮かばぬとも限らぬ」
「まぁそうでごいすな。ただ……お名前は変えておいたほうがいいでごいす」
「そうだな……松本……左近、なんてどうだ?」
「松本左近様……強そうなお名前でごいすな~。してどのような訳の旅にするでごいすか?」
「そうだな……家が没落したため、美濃(みの)の親類を頼って行く途中、ついでに戦見分し兵法を学んでいる事としよう」
「おらはそのお付きの者という訳でごいすな。分かりましただ」
などと長閑(のどか)に話す二人の前には、いくつもの小さな水路と沼地が続き、その沼には大きな蓮の葉が茂っている。
元気なつき丸が振り返り振り返り源五郎の姿を確認しながら、そんな道端の草花の匂いを嗅ぎ廻っていた。
つき丸が首を伸ばし嗅ごうとした蓮の葉の朝露が、朝日を浴び輝く美しい姿を源五郎は晴れやかな気持ちで眺め、先日の鬱屈が嘘のような良い気分で、足取りも軽く順調に歩み続けた。
【前回の記事を読む】寄る辺ない身の上となった自分を頼り、必死について来るつき丸が哀れに思え……。