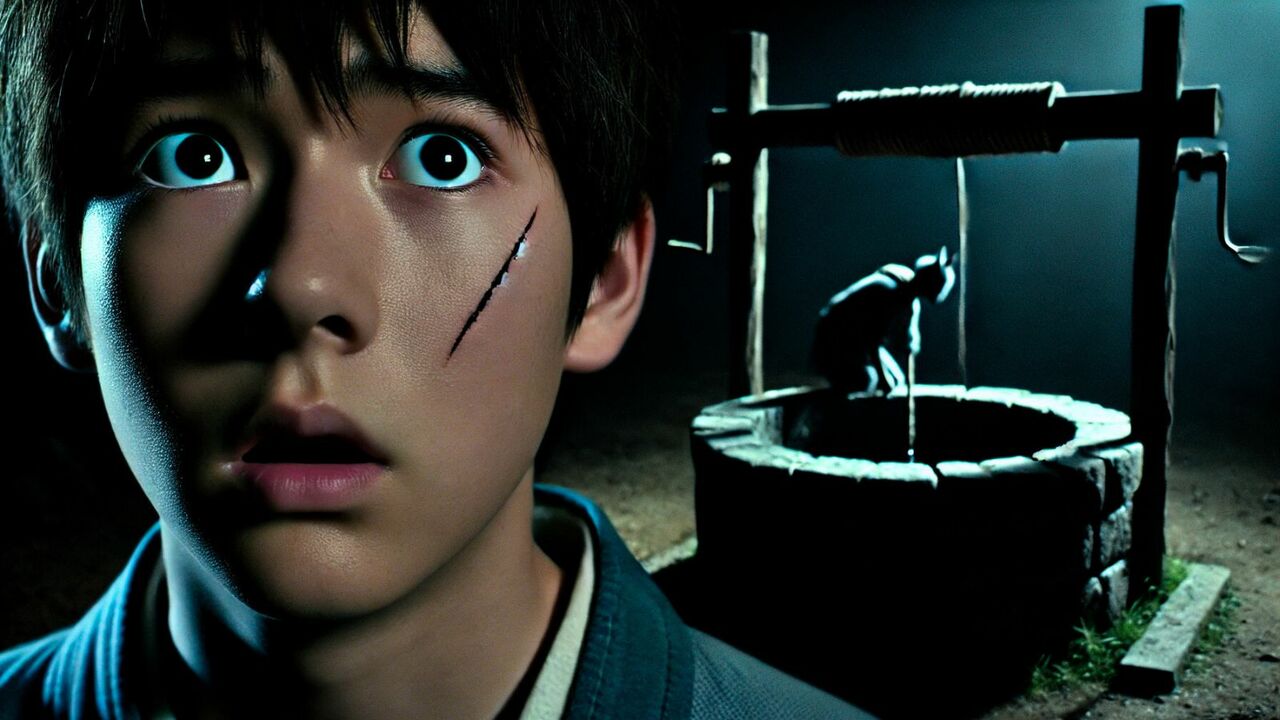夕陽が源五郎とつき丸に長い影を伸ばし、樹林の夜の静寂(しじま)へとつながっている……。
街道から外れ河原を歩き、陽が落ちてもまだ明るいうちに善右衛門の家に着いた。戸を叩き、出て来て驚いた善右衛門に告げた。
「別れを言いに来た……」
「どこぞに旅立たれるおつもりですか?」
「松山に参る」
「これからですか?」ここから松山まで十里はある……驚いた善右衛門は、
「今宵は我が家にお泊まりになって、明日発たれては如何でしょう?」と勧めた。
どこか呆然としている源五郎は、止まっていた思考を呼び覚ましながら深く考えず聞いた。
「よいのか?」
「もちろんですとも! このようなむさくるしい家でよければ幾晩でもお泊まり下さい」
熊吉もまだ足が完全に治っておらず療養中で囲炉裏横に座っていたが、源五郎の姿を見ると嬉しそうに、
「源五郎様、よくおいでくださりましただ。ささ、どうぞ中へ」
まるで自分の家のように中へと招き入れる。源五郎は二人に勧められるまま、あばら家の中に入った。囲炉裏横に座っても、うち沈み口を開こうとしない源五郎に、何事かあったものか……。
と察した善右衛門夫婦と熊吉だったが、あえて聞こうとはせず黙って源五郎の言葉を待った。まゆだけはつき丸を抱きしめ、嬉しそうに土間であやしている。
暫くして……。
「俺は松山へ行く事になった……」源五郎はボソッと繰り返し言った。
「へぇ……何用でごぜぇますだ?」
「難波田の……婿養子になる事と決まった」
「へぇ……」と言う熊吉の顔をどこか焦点の合わない目で見ていたが、不意に彼が先日言っていた言葉を思い出した。
【前回の記事を読む】名を残さねばならないという使命感は、孤独な小童の心の拠り所だった…