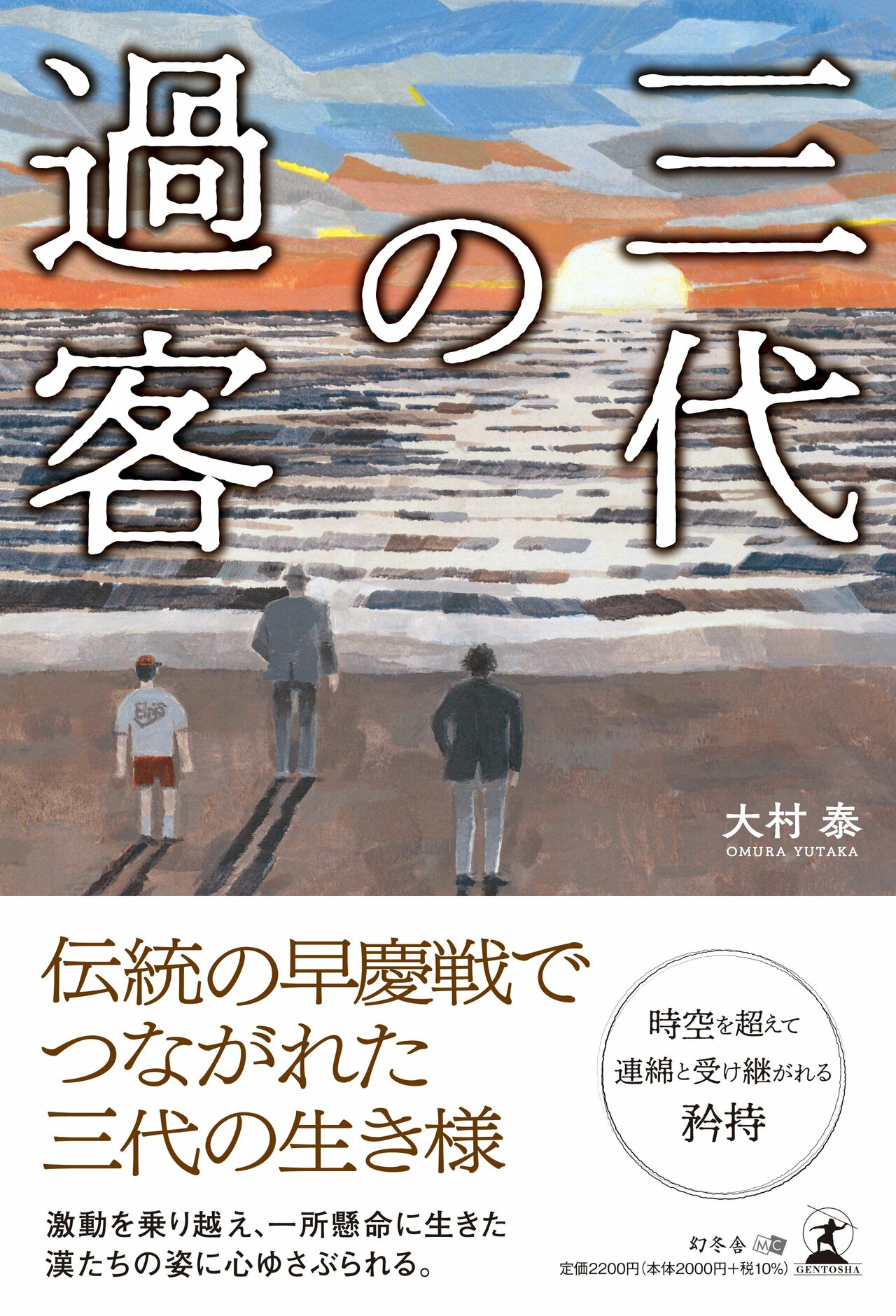南麻布にある国際総合医療センター最上階の特別室で瞑目(めいもく)している草壁俊英 (くさかべとしひで)(八一)は、サイレンにも、鼓膜を破らんとするかのような蝉の大合唱にも覚醒しない。意識は深い闇の奥底に沈殿したままだ。
すると、ウワー、球場に谺(こだま)する三万人の大歓声。固く閉じた俊英の瞼が心なしか開いたようにみえる。
(ん? ワセダ? ケイオウ? 早慶戦?)混沌とした意識が一瞬のうちに深い眠りのなかに再び沈んでいく。頭の中に真綿が詰まったようなこの感覚は遠い過去にもあった。
六十年前の満州、いまの中国東北部。激しい砲撃戦の末に、意識を失う。戦友の顔が次々と浮かんでは消えてゆく。
最後の早慶戦の応援席にいるのだろうか。満州の戦地は夢か現(うつつ)か。夢のなかで胡蝶になった荘子のように、夢が現実か、現実が夢か、夢が覚めてもその区別がつかない。
ふと「眠っているのか。おかしな夢を見たんだな。取るに足らない、つまらぬ話、夢のように、たわいもない」と誰かがささやく。その正体は、シェイクスピアの「夏の夜の夢」に登場する妖精パックだった。
「真我(しんが)は万古(ばんこ)に死せず1」。
三十年前に旧陸軍士官学校の同期生と旅行したおりに読みふけった、江戸時代の儒学者・佐藤一斎(さとういっさい)の「言志四録(げんししろく)」の一節が脳裏を飛び交う。
夢寐(むび)のまにまに、起臥(きが)の二界をさまよい、半醒半睡 (はんせいはんすい)の境地を旅する老境の二人。二〇〇五年八月十五日は、忘れられない長い一日となる。
二つのちの世代の若者たちが艱難辛苦(かんなんしんく)を乗り越え、すぐりし精鋭が集う甲子園球場。遮る雲もない。烈日の意気高らかに、理想の王座に挑む両軍の選手たち。六十年前のこの日と同じ顔をした日輪が大地を灼(や)いていた。
1 夢の中の我も我であり、醒めた後の我も我である。その夢の中の我であり、夢醒めて後の我であるということを知るのは、心の霊妙な作用である。この霊妙な作用こそ、「真の我」なのだ。この真我は常住の霊でありまた常住の知覚でもあって、万古にわたって不朽不滅のものである。