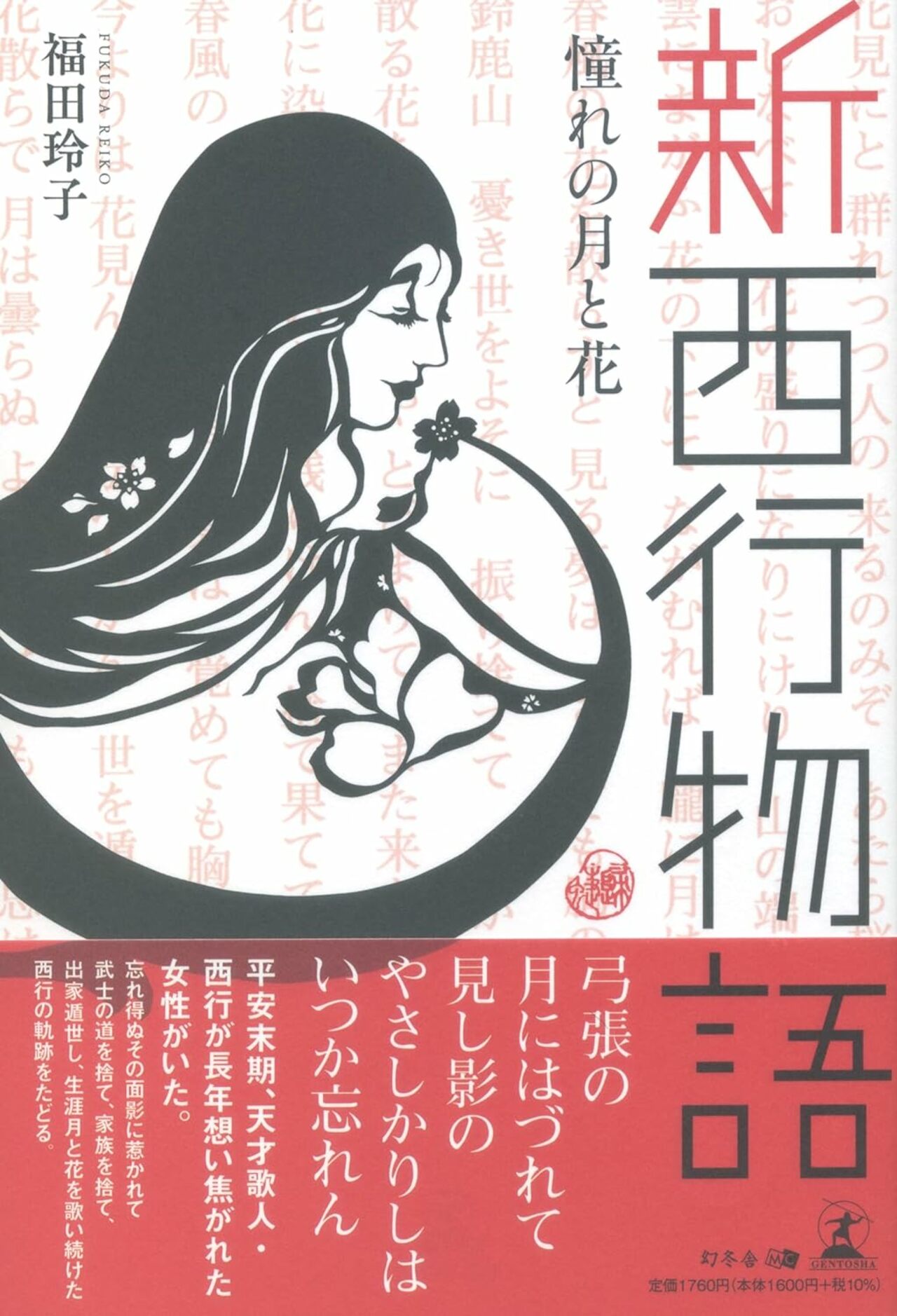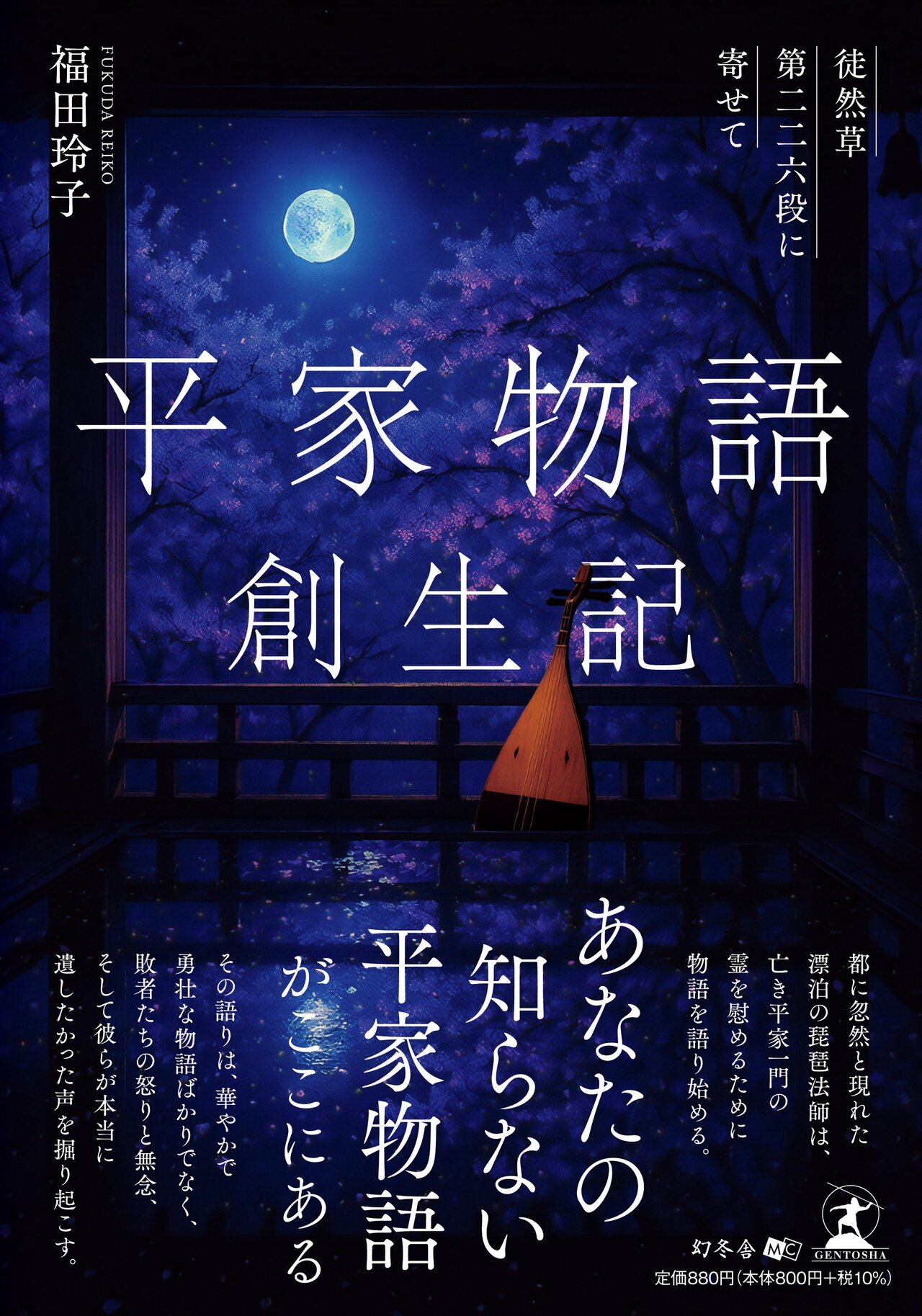しかし義経は堂々とした態度で見事な太刀を両手に持ち直し、差し出している。供の者達も一人としてたじろぐ者はなく、静かに控えている。義経はほんのひととき金色の光を放つ太刀に目を落とし、物問いたげ、とでもいうような無垢な表情をわずかに浮かべた後、再び威厳ある態度を取り戻し、神官に渡した。
太刀を神官に手渡してしまうと、義経はもう振り返りもせずに神殿に進み出て、深く拝礼し、音高く柏手を打った。
壇ノ浦の海原深く、一振りの太刀が沈んでいる。
天叢雲剣(あまのむらくものつるぎ)である。八咫鏡(やたのかがみ)・八尺瓊勾玉(やさかのまがたま)と並ぶ、三種の神器の一つだ。八咫鏡と八尺瓊勾玉は取り戻せた。だが天叢雲剣は、ついに戻らなかった。
それがどんなに掛け替えのないものだったか、源義経にもわかってはいた。
しかし戦には時宜が肝要だ。舟戦(ふないくさ)の巧みさにかけては西国の海を根拠地とする平家に、源氏は到底敵わない。坂東平野(ばんどうへいや)を駆け巡り騎馬戦に慣れた源氏が平家を滅ぼすためには、電光石火の急襲で敵の意表を突く、全く新しい戦法を採るほかなかったのだ。今でも義経はそう思っている。
だがその後義経は追われる立場となり、今では天下に身の置き所も無く逃げ回っている。
こんな自分を、神はどうご覧になるのか。自分はいったい、どうすれば良かったのか。他にどんな生き方があったというのか。
義経は、それを神に尋ねたかった。追手に身を曝す危険を冒してでも、義経はどうしても神のみ前に問いかけずにはいられなかった。それで、壇ノ浦合戦から一年になろうとするこの日、二度と戻ってこない天叢雲剣(あまのむらくものつるぎ)の代わりに、数々の戦に陣太刀(じんだち)として佩(は)いてきたこの黄金作りの太刀を、伊勢大神宮に奉納したのである。