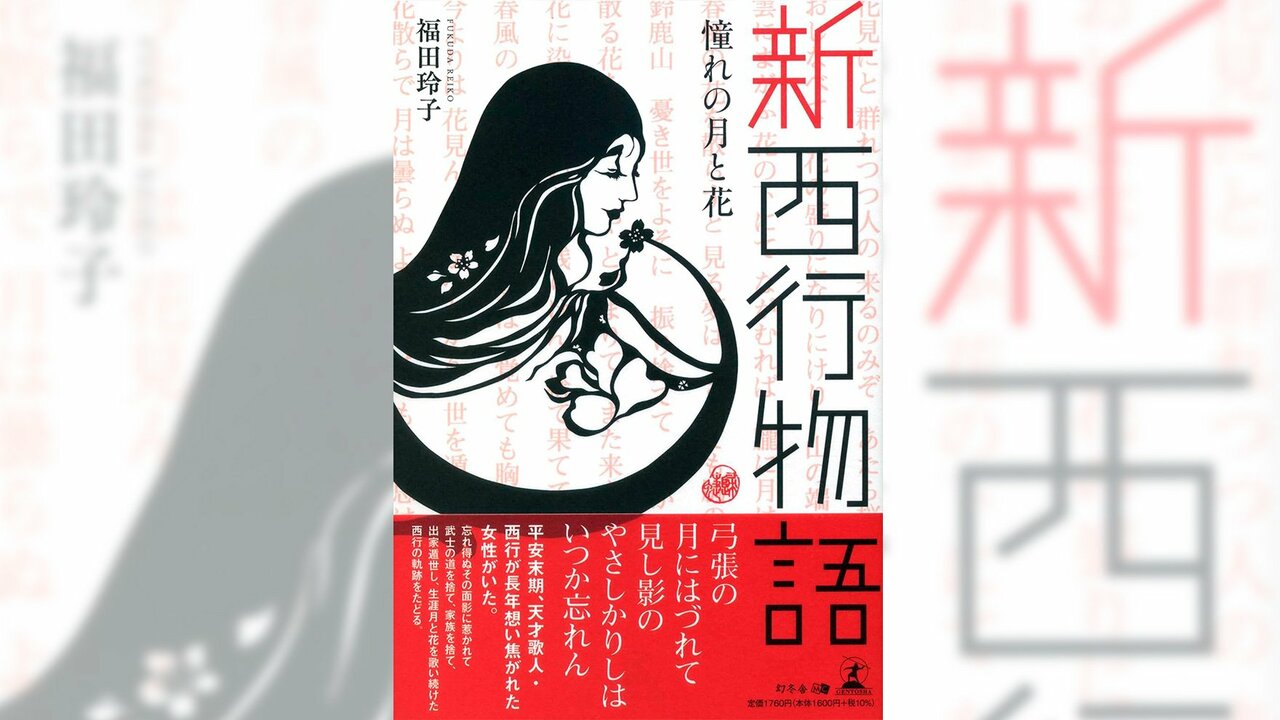序章 旅立ち
とはいえ、もとより神に答えを望んではいなかった。長居は危険である。神殿に深々と一礼するや直ぐに踵を返し、義経主従は再び山深く紛れ込もうとした。伊勢大神宮の鳥居を出た時、義経は参道の傍らに佇む老僧と目が合った。
老いてはいるが一見して武道の心得のあると知れる引き締まった体格である。肩の筋肉が盛り上がっているのは弓の修練の名残であろうか。濃い眉と骨太の顔立ちは、厳めしい。だがその眼と口元には、人が人と出会ったときに自然に浮かべる笑みが漂っていた。
ゆっくりと、老僧は義経に向かって頷いてみせた。
それを見た時義経は、なぜかこの老僧には、自分が誰であるか、伊勢大神宮で今何をしてきたのか、すべて理解されているような気がした。今までこらえにこらえてきた激しい怒りと悲しみが、堰を切ったように突然義経を襲った。義経は不覚にも涙がこみ上げるのを感じ、顔中をくしゃくしゃにしかめて必死にそれをこらえた。
見知らぬ若者の表情が唐突に崩(くず)れるのを見た瞬間、老僧西行の胸底に三十年前の鋭い痛みが蘇った。保元の乱の崇徳上皇を思い出したのである。
保元の乱も、やはり兄と弟の戦だった。待賢門院璋子(たいけんもんいんたまこ)の第一皇子崇徳上皇と、第四皇子後白河天皇である。崇徳上皇は和歌の中心的存在であり、西行とも親しかった。
兄弟の父鳥羽上皇の崩御をきっかけに陰謀が動き出し、事態は日毎に崇徳上皇に不利となった。西行は崇徳上皇を守るため和歌仲間の寂然(じゃくぜん)や西住(さいじゅう)と奔走した。