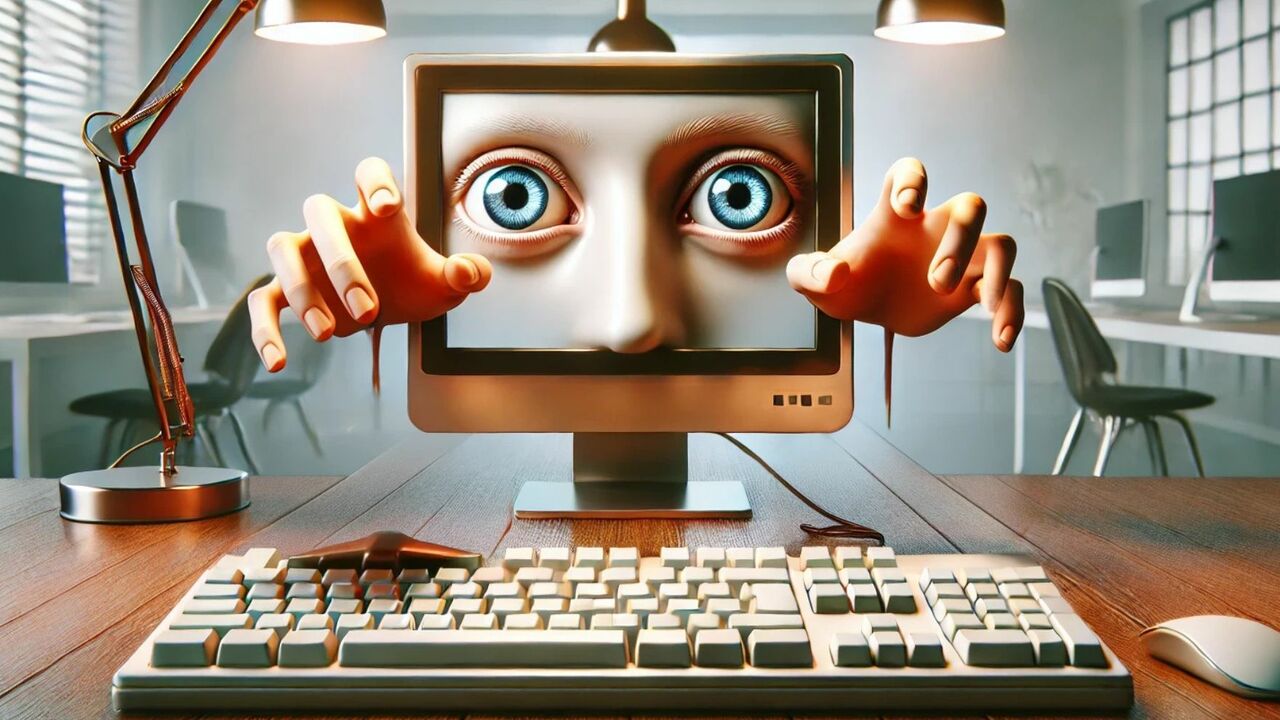序章
3 ヒトと道具の調和のために
ヒトのパートナー
コンピュータの創設期に、知能の拡大を目標とした。そこでは、ヒトとは異質なブツというとらえ方がされている。
一方、コンピュータをヒトに似せると、ヒト型ロボットとなる。10万馬力の力持ちで空を飛ぶ少年ロボットやなんでもかなえてくれるネコ型ロボットのような存在である。それらは、ヒトとよく似たパートナーである。パートナーという位置づけのほうが、ヒトはコンピュータと関係を結びやすい。
変化に必要なこと
ヒトがコンピュータを操作するときの、インターフェイスの歪みを克服しようとした考えは、以前からあった。
例えば、石井裕のタンジブル・ビッツである[石井裕, 1997]。彼は、コンピュータ・ネットワークの世界では、モニターとマウス越しでしかインターフェイスしないという、既存の概念に異を唱えた。
そして、環境自体をインターフェイスにすることを試みた。形のない“情報”というものを、“環境”という物理的な実体で表現しようとしたのである。
環境を進化させなければ、このインターフェイスの歪みは解決されないのか? 決してそうではない。知的な機械が、人体能力を尊重するように変化すればよいのである。
ヒトが元より持ち合わせている豊かな能力を尊重し、活用する。つまりは、ヒト自体をインターフェイスとしてしまえば済むのだ。
また、坂村健やマーク・ワイザーによるユビキュタス(どこにでもある)・コンピューティングという考えもあった。
Internet Of Things、モノがインターネットでつながる、ということにつながる考えである。コンピュータがいずれ、いろんな所に埋め込まれて、それらが協調動作する。
そうすることで、ヒトはコンピュータを意識しなくても、いろんなことができる社会が実現すると。コンピュータを意識しないことは、インターフェイスがないということであり、それが理想である。