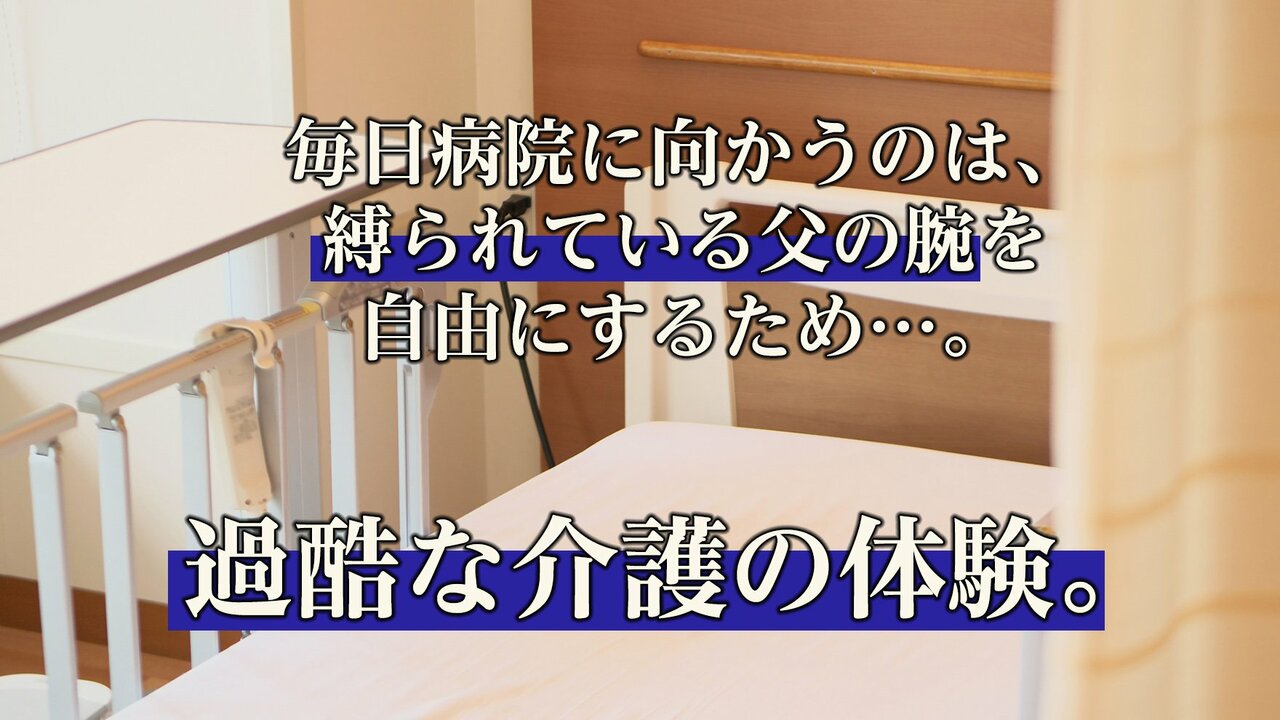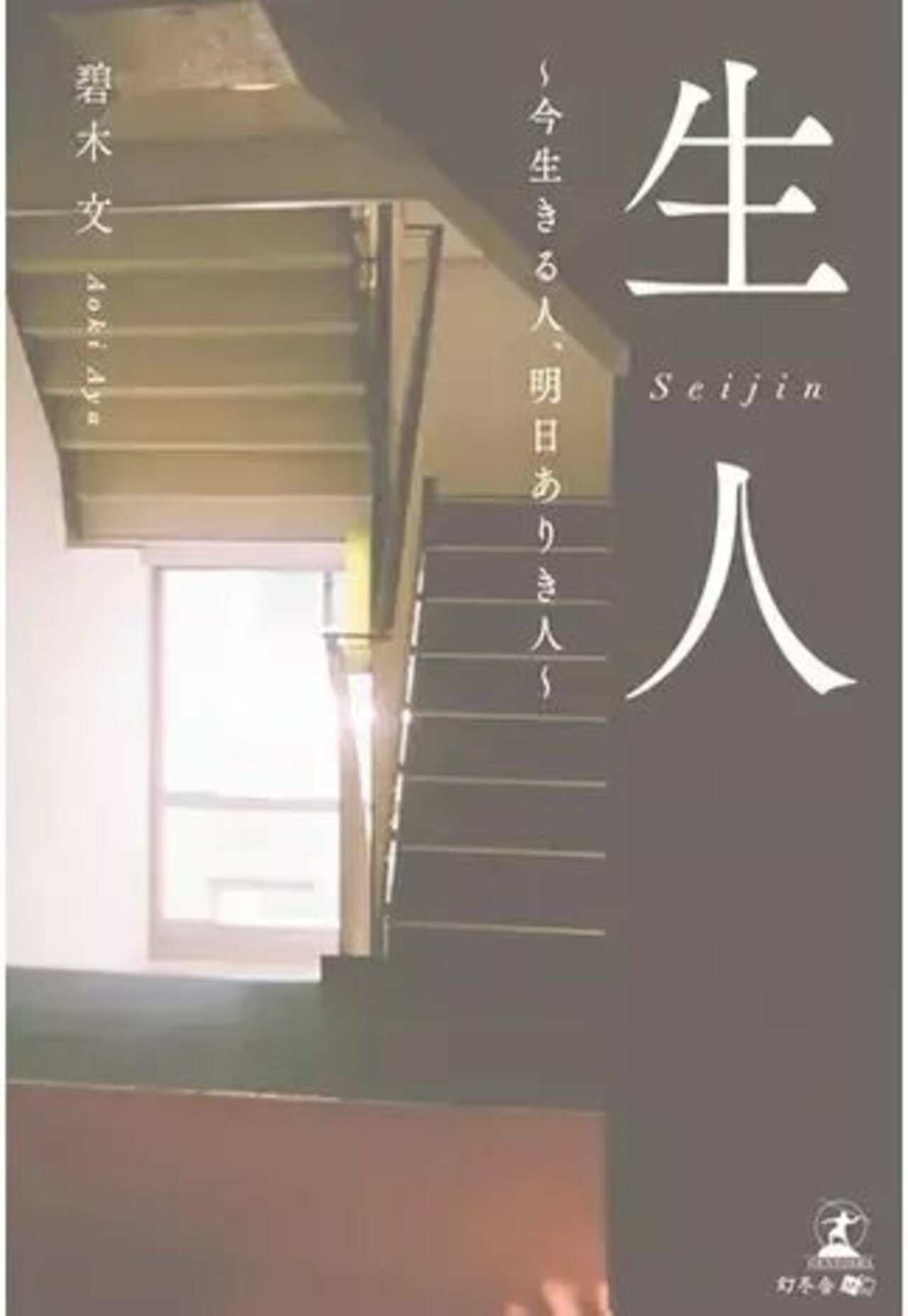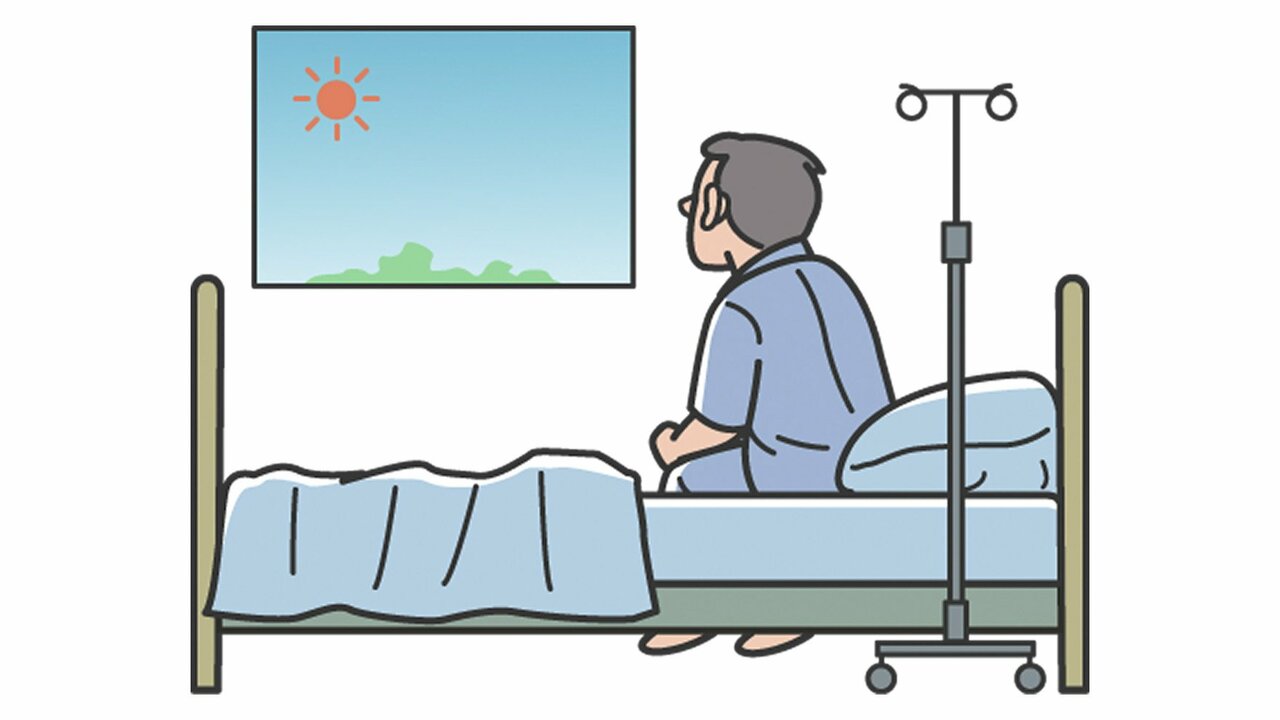介護
人生百年時代なんて、そんな軽々しく煌びやかな愚かしい言葉が流行っているようだ。
無責任なことを言うものだと感心してしまう。
それを信じている生人もいるのだろうか。実にめでたい。
誰にも迷惑かけずに、元気にシャキシャキと歩いていられるだろうか。自分で金の計算ができるだろうか。自分のケツを綺麗にふけているだろうか。はなはだ疑問である。
介護とはほど遠い生人の言うことだろう。
介護というあの底知れぬ泥沼のようなところを知らない。クソまみれを知らない。経験のない幸せ者だ。
介護は、される側もする側もどうしようもなく身を削るものだ。心身が痛めつけられてしまう恐ろしい穴蔵。
子育てとは全く違う、あの小さな可愛いおしりの簡単なオムツ替えとは全く違うのだ。
決して育つものでもなく、元気になるものでもない。
ただ切なく、虚しく、懸命に刻を過ごす。いつまで続くのか。
まるで乗りたくもないジェットコースターにいきなり乗せられてしまったような感覚であった。
少し良くなれば少し喜び、また奈落の底に突き落とされてゆく。
それが繰り返し繰り返しやってくる。期限が見えないところで、あえぎ苦しみ悩み悲しみ疲れきってしまう。
毎日病院に向かう。両腕をベッドの両側に縛られている父の腕を自由にするためだ。
元気であった老生人にとって、訳の分からない、意にそわない点滴や尿道から膀胱に入れられた留置カテーテルでさえ、嫌で引き抜いてしまうことが多々ある。体に余計なものがついているのがたまらなく嫌なのだ。そして血だらけになったり、悲鳴をあげる。叫ぶ。そこから拘束という悲劇が始まる。
拘束を解くために何時間もそこにいる。話しながら体を拭いたり、足を揉んだり、シモの世話をするためだ。
行かなければ、縛られたままにされる。これが病院。
父を家に引き取った時、まさに二十四時間介護だった。何時でもお構いなしに自分を呼び続ける父。
病状が安定し、父が施設に入所した日に高熱を出した。
入所した施設に併設された病院の女医が言った。
何でこんな人を引き受けたんだ、こんな人診れるわけがないだろ、と。
父は再び救急搬送で、元いた病院に戻された。
その後、その病院で院内感染をした。MRSA、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症だ。
転院をしろと言われた。要するに院内感染させておいて、出ていけと言われたのである。
その当時、その感染症は治せないものであった。現代では、治せるらしいが。
父は転院を余儀なくされ、ナースセンターから一番遠いMRSAの方ばかりがいる隔離病棟に入った。