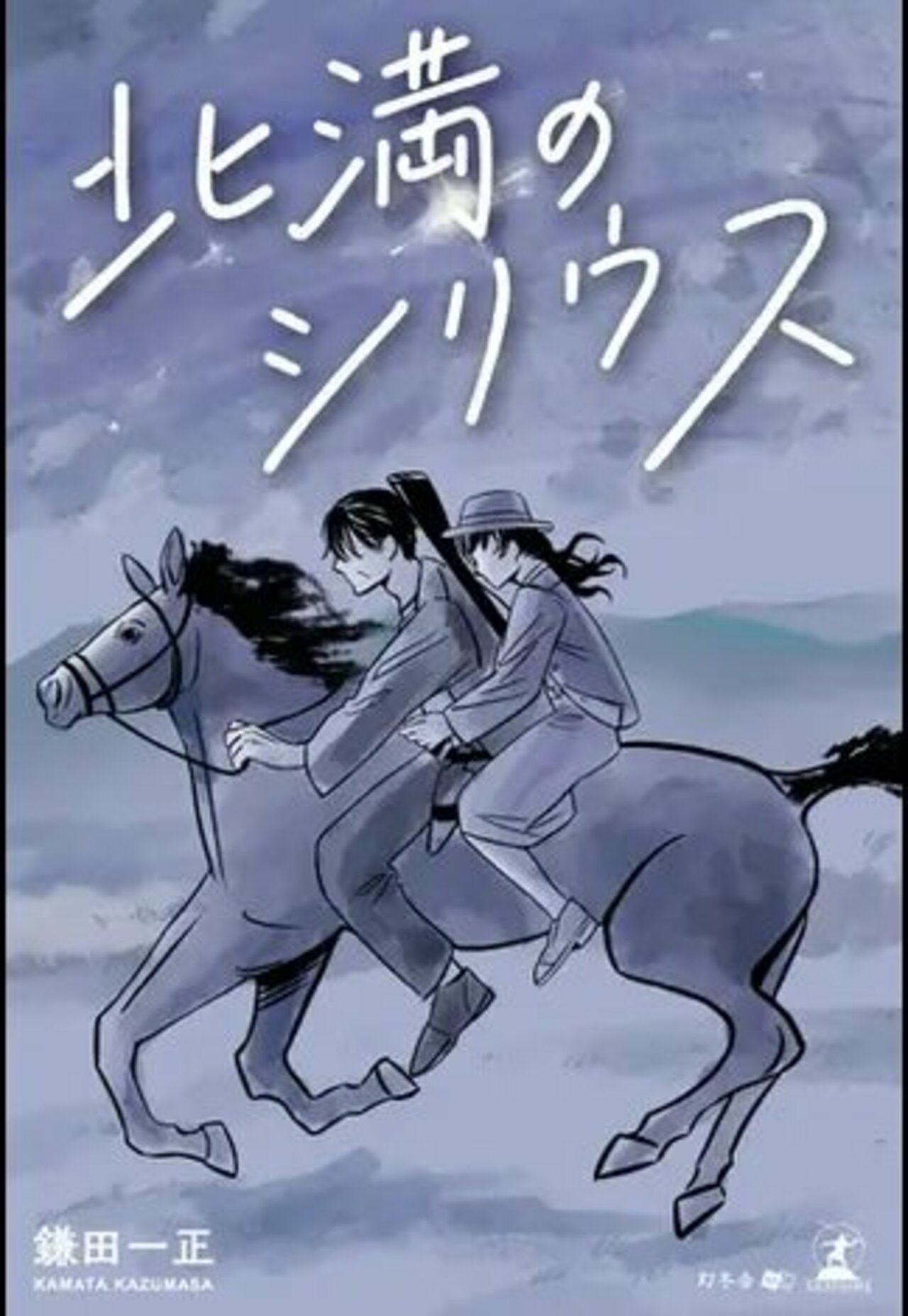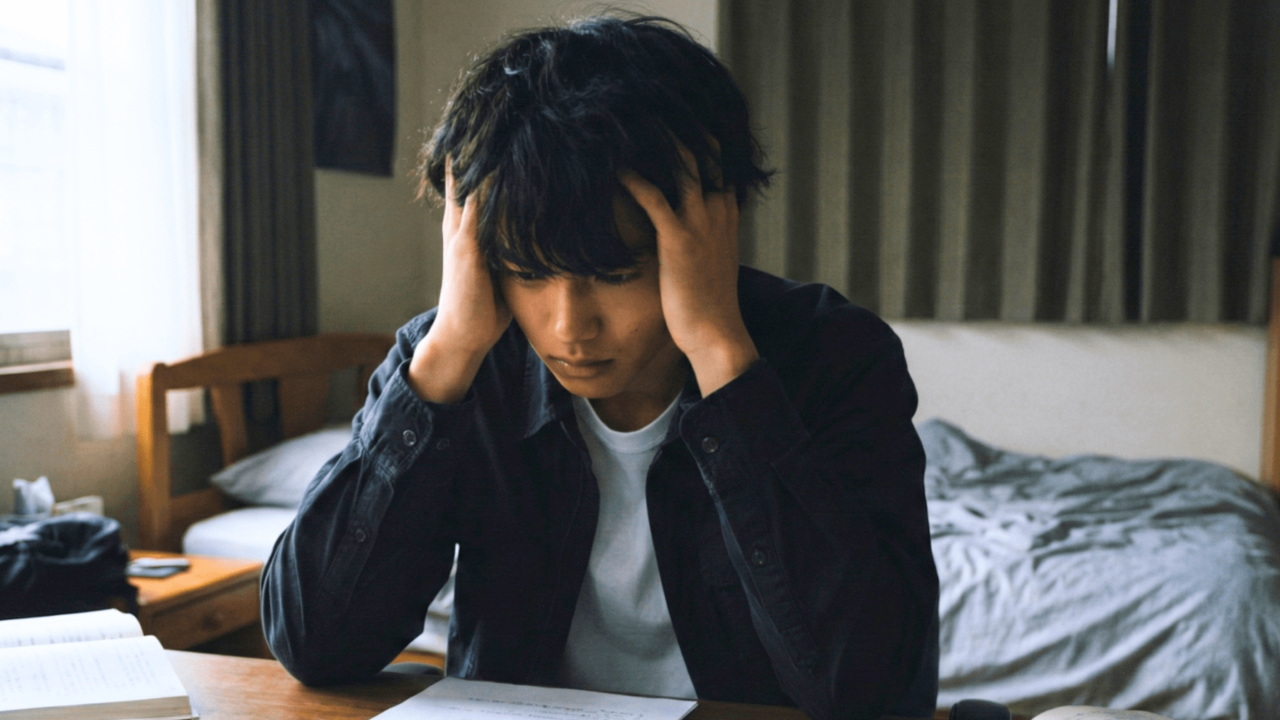八月七日 午後一時三十分頃 ハルビン ハルビン街 青島診療所
青島診療所では、暇を持て余した坂口茂夫老人が、診察室の患者用の椅子に座ったまま、医師用の椅子に、やはり座ったままのハルと雑談を続けていた。いつの間にか、ランニングの上から草色のポロシャツを着た茂夫に対して、ハルは、まだ白衣姿のままだ。
そこへ、看護婦の多恵が、青島家の末娘で四歳のフユの面倒を見ていた子守のイリヤと一緒に入って来た。フユも左腕にクマの縫いぐるみを抱えて、イリヤのそばに立っていた。フユは、右手をイリヤの左手とつないでいた。イリヤは、五十代くらいのロシア人女性だ。先に帰りの挨拶を切り出したのは、多恵だった。
「では、先生、切りがつきましたので、今日は、これで失礼させて頂きます」
「ああ、多恵さん、ご苦労様! 今日も本当に助かったわ」
続いて、イリヤ。
「私も二時から自宅で、アベードですので」
「アベード」というのは二時から四時までゆっくりと時間をかけて楽しむ、ロシア人の昼食のことだ。
ハルは、壁掛け時計を見上げた。
「ごめんなさい。そうだったわね! すっかり忘れてたわ。それじゃあ、急がないとね。でも、食卓の準備のほうは、大丈夫なのかしら」
「今日は、娘のフローシャがやってくれていますので」
「そうなの。フローシャさんがしっかりしているから、イリヤさんも心強いわね」
横から茂夫が口を挟んだ。彼は、ハルの顔を見ながらニヤリとしていた。
「ハルさん、耳が痛いのお」
もちろん、家事の全くダメなハルをからかったのだ。ハルは一瞬、茂夫を睨みつけたが、すぐに笑顔でイリヤに声をかけた。
「イリヤさんも本当に有難う。フユ、いい子にしてた?」
縫いぐるみを抱いたまま、フユは、コクリと頷いた。
「イリヤさんとね、お絵かきしていたの」
茂夫は、身を乗り出して、フユの顔を覗き込むようにした。
「ほお、何の絵を描いたんじゃ?」
イリヤは、にっこりしながら、フユを見下ろした。
「教えてあげたら?」
フユは、嬉しそうな笑顔を浮かべて、体をくねらせながら、イリヤの脚に抱きついた。
「ヒ・ミ・ツ……」
「何じゃ! 教えてくれんのか?」
その場にいた全員が笑った。窓から入る鐘の音が、診察室内の和やかな雰囲気を温かく包み込んでいた。