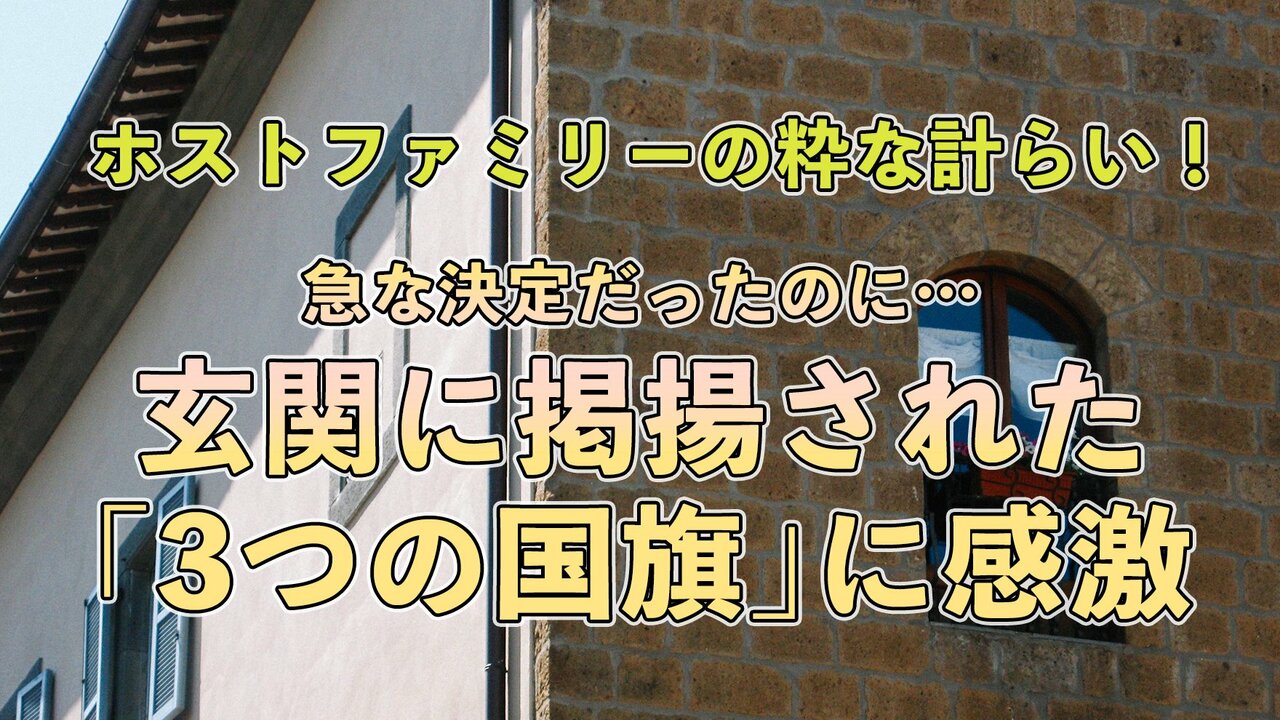ある日、母親のミセス・ワッツが、「所属する教会の日曜スクールに招待する。」と言ってくれて、「バイブルスタディ」と呼ばれる聖書の読書会に誘われた。
聖書の英語は難しく、理解するのに時間がかかった。二ヶ月のあの「ひとり旅」をしているときに、「イエス・キリストの生涯」という本を読んだことがあったが、キリスト教の信仰的なバックグラウンドがない人間にとって聖書を理解することは難しい。それでも、幾つか理解できたフレーズから想像して何を伝えようとしているのか考えた。
ミセス・ワッツは日曜ごとにこの読書会に誘ってくれ、会の人たちといろいろな話をすることができたことは、とてもよかった。一度こんな質問をしたことが合った。
「『この教会は、いつもみなさんに開かれています』と言われたり、その言葉が教会のドアに書かれてあったりしますが、なぜ夕方になると、ドアを閉め、鍵をかけてしまうのですか」
と。その場の雰囲気が悪くなったことは言うまでもない。
ミセス・ワッツは、教会の役員をしたり、地域のボランティア活動をしたりと、毎日が忙しい。彼女は、何に対しても一生懸命だった。しかし、彼女は家に帰ると、ぐったりしていることが多かった。そんなとき声をかけるのが憚られた。
平日の朝、些細な出来事で気を悪くさせてしまったことがあった。彼女の思っていることにうまく応えられず、二、三の言葉でサラリと受け流してしまったことがきっかけで、無言のままの関係が少し続いてしまった。
「もうダメだ。」
「耐えられない。」
と思い、ミズ・マックアルーンに事情を説明し、相談をした。彼女は、しばらく考え込み、
「あなたがそこまで言うのなら、ホストファミリーを換えますか?」
と言ってくれた。
次の日、早速荷物をまとめ、ワッツ家を出た。ミスター・ワッツに別れを告げ、ミセス・ワッツの車で次のホストファミリーの家に向かった。
「申し訳ないなぁ。」
という気持ちでいっぱいだった。あの時のミセス・ワッツの気持ちはどんなものだったかを想像すると、苦虫をかみつぶしたような、後味の悪い気持ちになる。
次に紹介された家は、「ウェアリング夫妻」の家だった。ミズ・マックアルーンは、
「急に決まったホストファミリーなのに快く引き受けてくれた。」と言っていた。
「ウェアリング家」に行くと、アメリカの国旗と、ウルグアイの国旗と、日本の国旗が玄関に掲揚されてあった。

「なんとも粋な計らいだな。」と思った。
それを見ただけで、「歓迎されているんだなぁ。」と思い、嬉しかった。