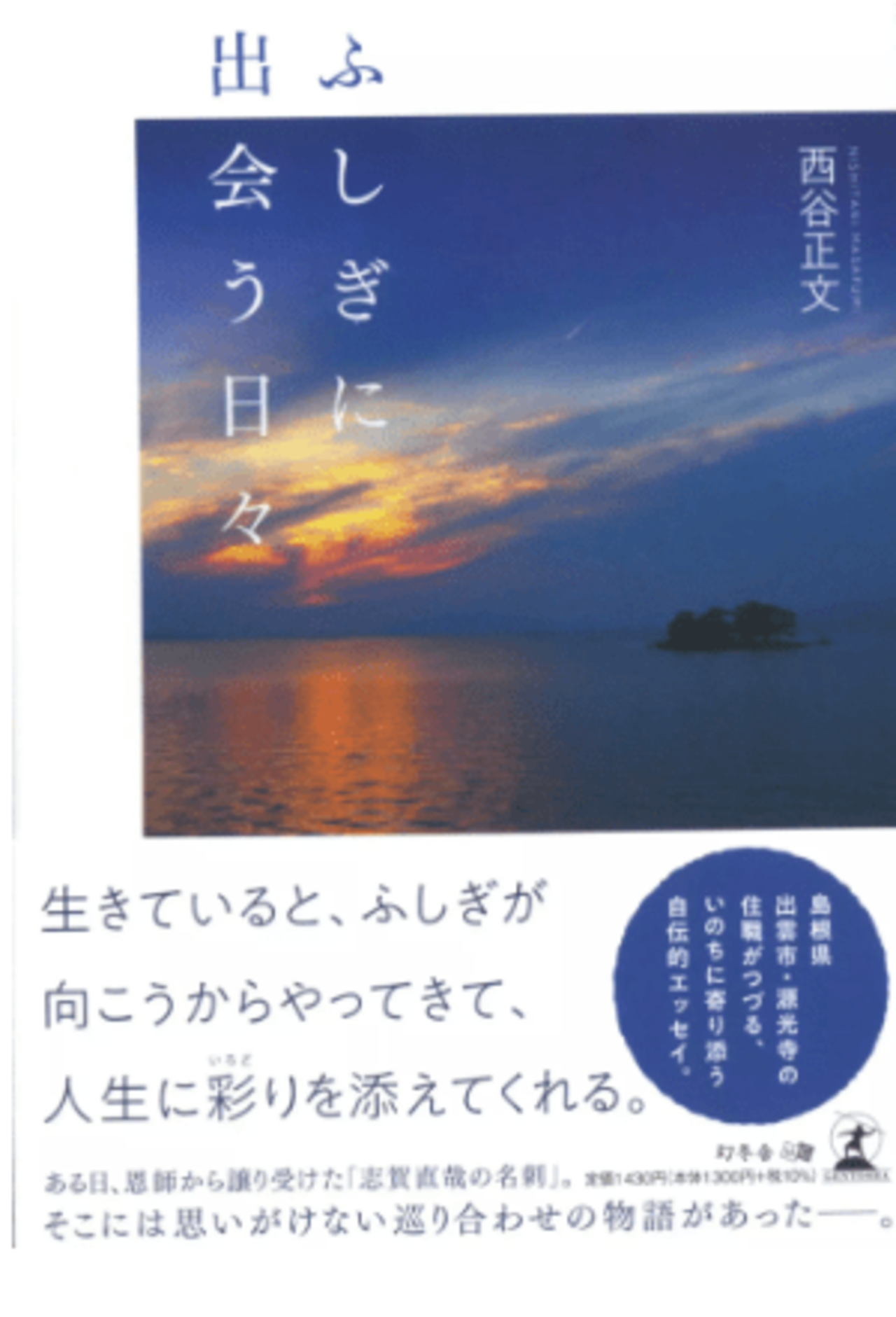第二章 回り道のふしぎ
ドイツ文学
大学の文学部で専攻に分かれるのは二年次からだったが、私が思うような心理学ではなかったため、中村さんに助言を求めた。すると中村さんからは、
「人間の心理を勉強したかったら、文学を専攻してはどうですか?」
との返事をいただいた。文学なら中学以来、乱読ではあったが、いろいろな文学作品を読んでいたので、私の得意とするところだった。とてもうれしく受けとめた。さて、次はどの文学を専攻するのかを決めなければならなかった。さんざん迷ったあげくに、ドイツ文学を選んだ。
理由の一つは、第二外国語としてドイツ語を学んでいたこと。中学・高校に通っていたときにも、土曜・日曜には犬の散歩がてら近くの川へ出かけていて、そんなときには、いつもポケットに文庫本が入っていた。ヘルマン・ヘッセの詩集が最初だった。その後『デミアン』や『車輪の下』などの小説も、川の流れの音を聞きながら読んでいた。
また、高校の図書室に新しく「トーマス・マン全集」が入ったときには、貸し出しカードの一番に名前を書きたくて何冊か借りたこともあり、ドイツ文学には親しみをもっていた。
さらに、私が親しんだドイツ文化に音楽があった。私は中学時代、吹奏楽部に所属して、アルトサックスを吹いていた。吹奏楽部はちょうど移行期で、応援団としてマーチを多く演奏していた活動から、コンサートで披露する、クラシック音楽を編曲した曲を少しずつ練習するようになっていた。
ベートーヴェンやチャイコフスキーの小品もあったが、なかでもワーグナーの『タンホイザー』や『ローエングリン』のなかで演奏される曲の響きに魅了された。音楽雑誌をとおして、ワーグナーが自分の作品だけを上演するためにバイロイト祝祭劇場を作り、毎年夏にそこで音楽祭が開かれていることを知った。そしてその録音が、その年の末にFMラジオで放送されることも知った。
当時は年末の昼間に放送されていたので、私は本堂の大掃除のBGMとして、ワーグナーの音楽を流した。ステレオがあったわけではなく、小さなポータブルラジオの音量を上げて、本堂いっぱいに響くようにしていた。作曲家の柴田南雄が曲の解説をしていて、音楽を聞きながら、舞台を想像した。毎年暮れには本堂にワーグナーの音楽が流れていた。
本堂の掃除をしながらだったから、時間はたっぷりあった。上演に四時間も五時間もかかる曲であっても、なんの苦にもならないし、むしろ長いほうが、掃除のやりがいがあった。こうして自分では自覚しないうちに、ワグネリアン(ワーグナーの音楽の心酔者)になってしまっていた。