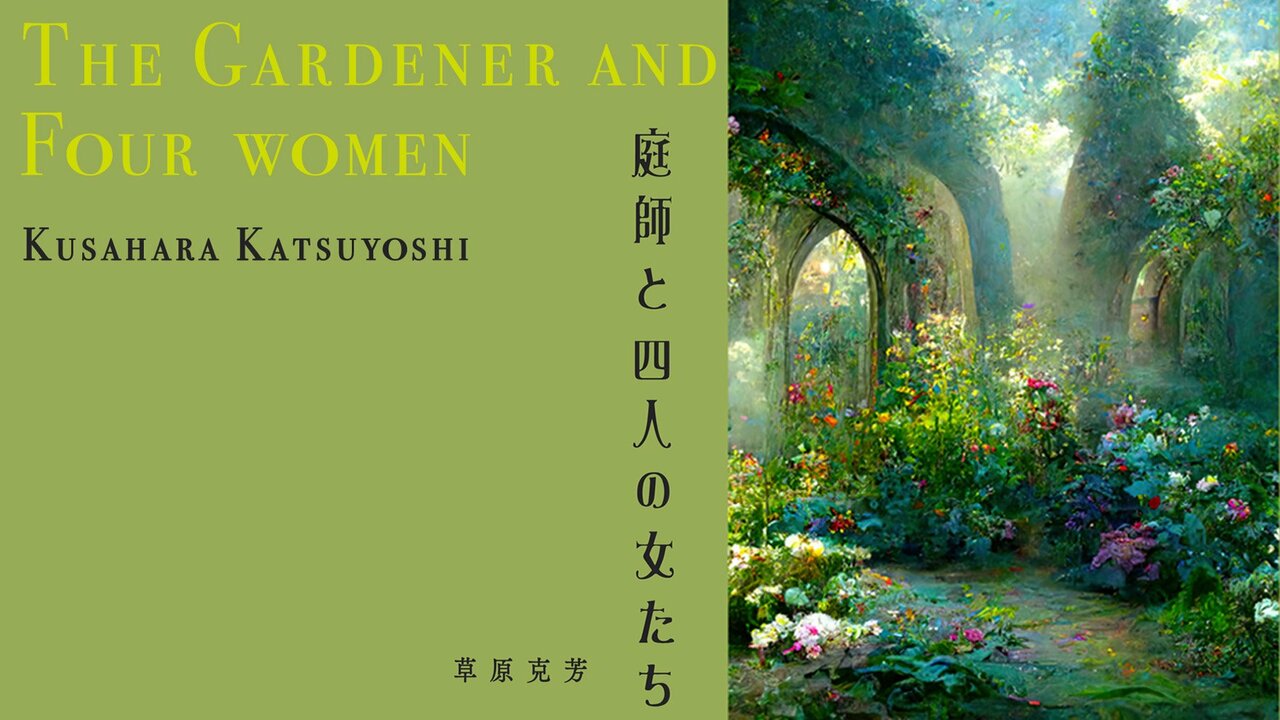庭師と四人の女たち
2
古民家を改造した建物には、贅沢ではないものの、趣味の良いインテリアがしつらえてあり、窓にはさりげなく、野草を差し込んだ鉛色の花器が並べてあった。
書棚には、相変わらず、雑多な美術本と、瀧口修造、吉岡実、鷲巣繁男らの詩集、マルセル・デュシャンや、パウル・クレー、シュールレアリスム系の画家や、前衛的な映画作家たちの本。クセナキスや武満徹などのCDと、現代音楽や民族音楽の評論書。それに、ブラヴァツキーやシュタイナーの神智学、人智学、スウェーデンボルグ等の妖し気な本が並んでいた。
これらは昔から彼の愛読書なのであった。陰影ある室内に斜めに差し込んでいる透明な光線が、美しかった。裏庭には小規模の窯があった。
「いつか、陶芸のできる家を持ちたいんだよね。単なる夢だけどサ」
彼は昔よくぼんやりとつぶやいていた。
そんなことを語っている横顔は、嫌いではなかったはずなのに。何であたしじゃ、駄目なんだろう、と睦子は低くつぶやいた。なんでここに、あたしがいないの……。
それはある意味で、睦子自身が望んでいた理想の生活であった。最初、冷静さを装っていた睦子は、少女の面影を残す女と、何かのやりとりをした。だんだん語気が荒くなってきた。じっと見つめている少女の目が、真ん中に寄ってきた。その黒目が、憎たらしいほど可愛らしいと思った。
不意に激情に駆られ、その場で泣き叫び、アトリエの棚に並べてあった鈍い藍色に輝くいびつな焼き物を、幾つか壊した。心の奥から、墨汁のようなものが、もくもくと湧いてきた。睦子は、驚いてその場を逃げようとする少女の髪を、毟るように引っ張った。男は、半狂乱になった睦子の手から、少女のような女をかばった。間違いなく、相手の方を、かばったのだ。
彼はふと猛烈な睦子の目つきに気がついて、バツが悪いような顔をして、しょぼしょぼした目をまたたいた。冷静な顔をして屈み込み、うつむいて陶器のかけらを拾い始めた。