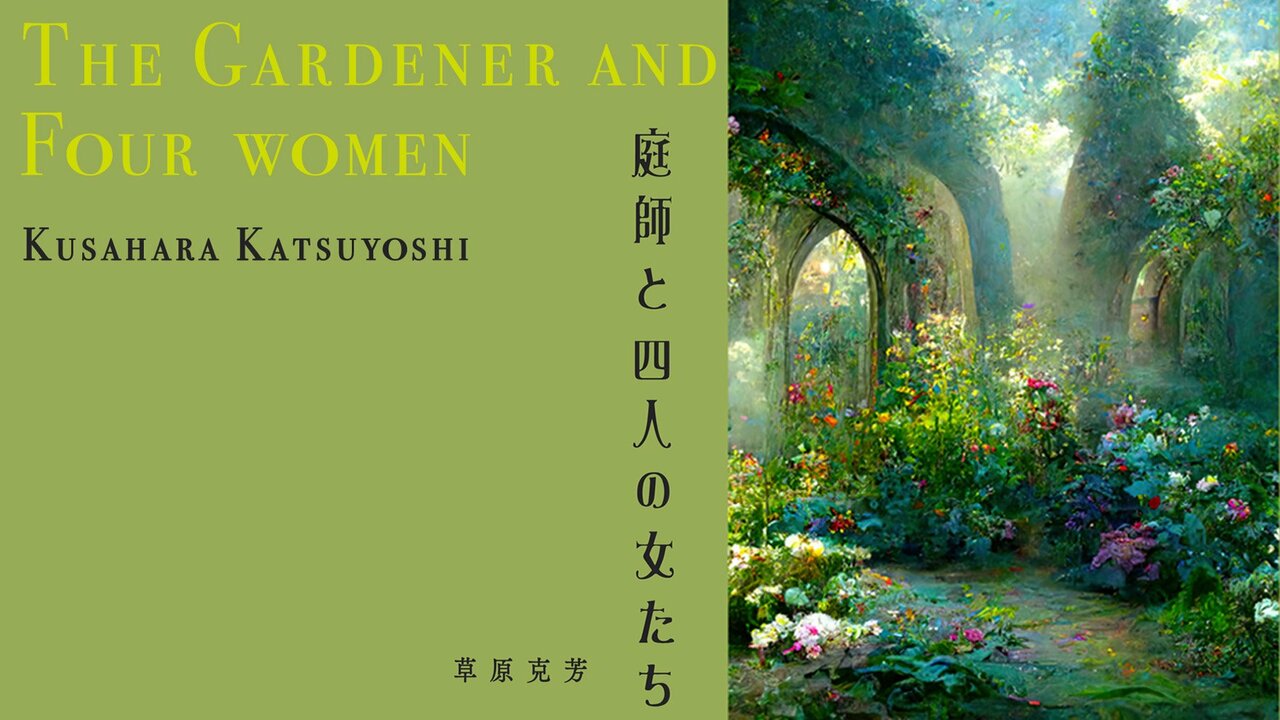庭師と四人の女たち
4
この男には、どことなく、反発を誘うものがある。それに耀子は、モデル系の美男はもうあたし、さんざん見飽きているんだから、という業界人ふうの体裁をとりたがっていた。睦子がいつも耀子から聞かされる口癖は「まあ、だいたい皆、見かけ倒しの頭の空っぽなナルシストなのよねえ」というフレーズであった。
夏の日射しでここのところいっそう濃くなった群葉が、金色の太陽光線を背景として、輪郭線を荒くしていた。庭師が動くたびに、バサバサと大きく、不安定に揺れた。
彼はさらに四肢を使って、太い斜めに伸びている一抱えほどの枝を登っていくと、枝の弾力と強度を確かめるように上下に揺らした。そのたびに地面では、青紫色の影が大きく動いた。
彼はまるで、椰子の実でも獲りに行く南の島の少年のように中腰になり、注意深く前方を睨み、細くなった先まで進んでいった。庭師を乗せた太い枝は、重みに耐えかね、ゆっくりと撓って、ぎりぎりと忍耐強く下がっていった。
腰には銀の金具のついたロープは下げていたものの、庭師はまるで、こんな見え透いたパフォーマンス自体を、いかにも楽しんでいるかのようであった。
「やめて!」口元を押えた彩香が、小さく叫んだ。
「大丈夫よ、プロなんだから」と睦子は、屈み込んだ少女の丸い肩に手を置いて、顔を押し付けるようにして、一緒に見上げた。
「あんなアザトイこと、そもそも、まともな植木屋さんが、やる必要が、あるのかしら」
耀子は、皆に聞こえよがしにつぶやいた。
庭師は待ち構えていたように片手を伸ばすと、向かいのアパートの手摺りに飛び乗り、腰をくるりと軽く捻って、二階の通路にストンと着地してみせた。
一連の動作は、彼にとってはすべて計算のうちといったふうで、不安定な動きにも、手慣れたような余裕があった。動きにはある種の美学めいたものが感じられ、まるでサーカスの芸人か、映画のスタントマンのようであった。
「なんだい、ありゃ。どういうつもりなのかねえ」
「やってることが、意味不明」
マス江と耀子がほぼ同時に言った。「腰に下げてるロープも使わずに」
「とにかく、変わった植木屋さんね」
睦子ママの声は、何故か、心持ち上ずっていた。