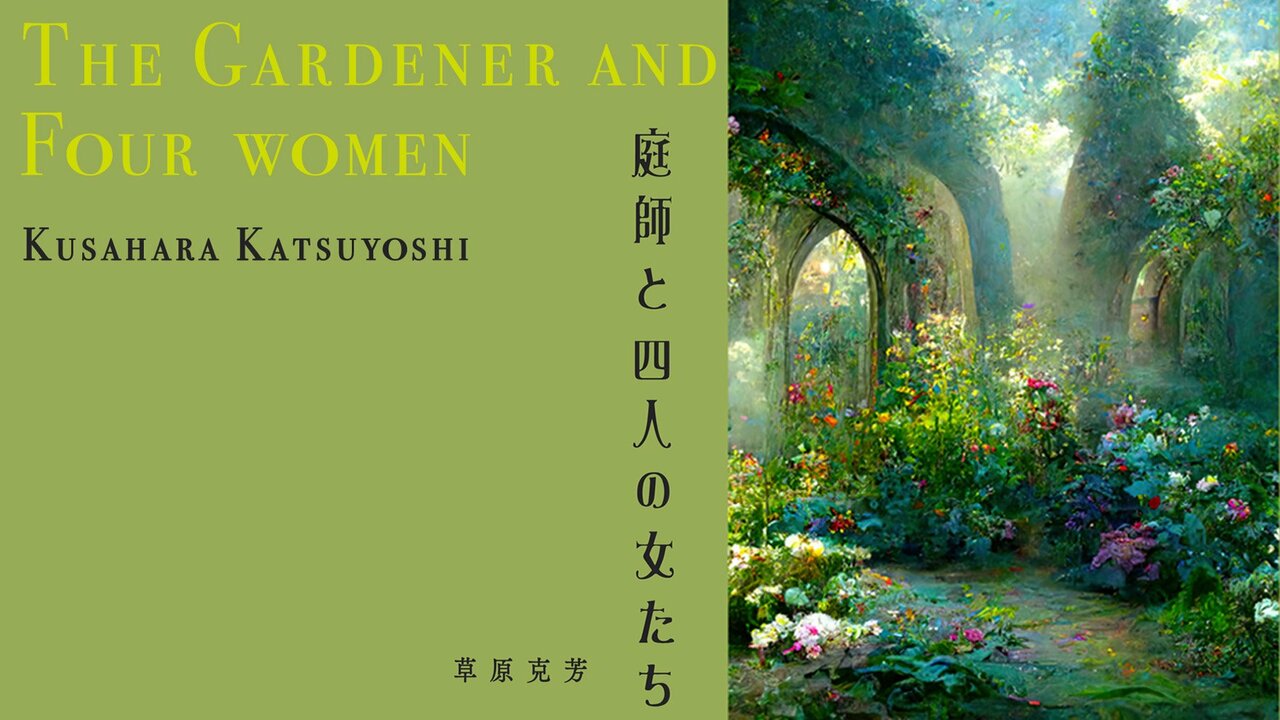庭師と四人の女たち
4
「じゃあ、さっそくお庭の方を見てみましょう」
日置という庭師は、店主とともに、中庭に出ていった。
そして片手を翳し、眩しそうに太陽をじっと見つめると、手の甲を合わせたまま両腕を伸ばし、大きく背筋を伸ばした。
好奇心も手伝って、女たちもそれとなく、店主と庭師の後に続いて、再び中庭に出た。
女たちよりも頭ひとつ程背の高い庭師は、腕を組んだまま中庭を見渡し、自分にだけその意味がわかるような微笑を浮かべ、ひそかに手順を考えるような顔をした。薄いTシャツの下で汗ばんだ庭師の筋肉質の肉体が透けて、上下に動いてゆくのが感じられた。
男はくるりと振り向くと、褐色の不精髭の生えた下顎を掻きながら、ちょっと眠そうなくすぐったそうな笑顔をして、
「さてと。どういうふうに、しますかねえ」と言った。
三人の常連客は、お互いの顔をうかがっていた。
「――客観的に見てね、あたしは喫茶店『パンタレイ』の中庭というのが、まず前提条件としてあると思うの」黒崎耀子が言った。「つまり、一種の宣伝効果、販売促進ツールとしての庭ね。何をプロモートするのか。一体、何を。……その答えは、ここの時間と空間そのもの、ということね」まるでプレゼンで企画書でも朗読するかのように、耀子はそう宣言した。
「店主として言わせてもらえば」
睦子があわてて、口を挟んだ。
「お客さんがリラックスできる自然な感じがいいわ。ぼうっと緑を眺めていられるような。癒しってやつ?」
「あたしはそんな大げさなことじゃなくてさ。雑草や蔦なんかで、モズの巣みたいになってるだろ、あれはさっぱりさせてほしいね。貧乏くさいのは、もう、やだよ」とマス江。
「あたしは、お花がいっぱい咲いているのが素敵だと思うんです。色のトーンは、パステルカラー。これから夏になって、秋にかけてだったら、コスモスとかいっぱい揺れているような。春はパンジーがいっぱい咲いていて……」多少は立ち直ったのか、うっとりと語る彩香。
「フフッ。みなさんまるで、ご自分の心のうちを、ご披露されているみたいだな」
庭師は、濃い眉をぴくりと動かすと、いたずら好きな少年のようにニヤリと笑った。
「もっとも、エデンの園の話以来、庭と魂とは、深い関係にあるものですからね」
黒崎耀子はきょとんとして、「なに言ってんだろ。変なこと言い出すわね、この植木屋さん」と首を傾げた。