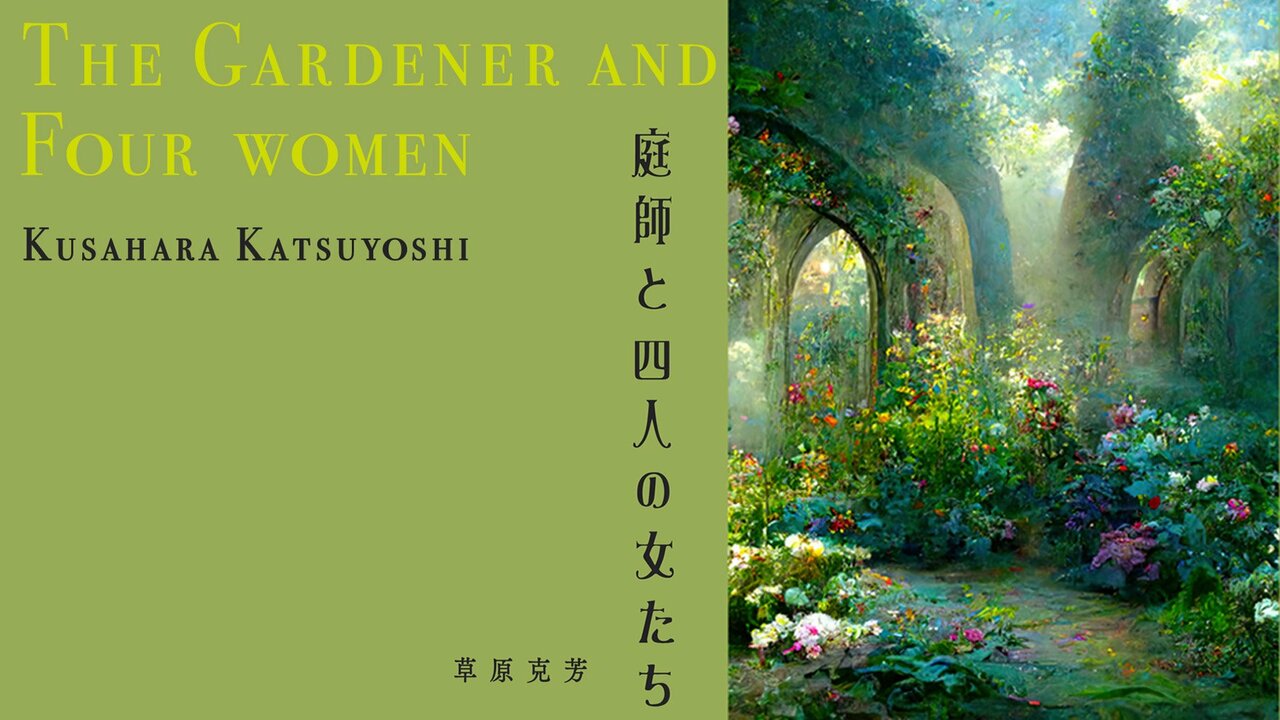庭師と四人の女たち
5
近くのアパートの一室にも、事務所と称する六畳の部屋を借りていて、そこでタウン誌やらPR誌などの編集をしているらしい。いつも忙しがっているが、公園で何時間もタバコを喫っていたりするので、本当はそれほどでもないようだ。
「あら、二村さんごめんなさい。いらしてたの? ちっとも気がつかなかったわ」
紺色の作務衣姿の睦子は、両拳を腰のところで小さく握り、かけっこのようにしておどけながら、小走りで寄って行った。
「あのさ。……いらしてたの、じゃないよ。さっきから、ずっとここで待っていたんだけどね、ずうっと。注文とらなくていいの。いいんだったら、このまま何時間でも、わざといてやるけど」
憮然として横を向き、男は言った。ふざけているのか怒っているのか、よくわからない。
「何になさいます、お客様」
両手を胃袋の前あたりで重ね、ホテルの従業員のような丁寧な口調で、店主は言った。
「なんだよ、わざとらしい。あのさ。ここ、水はタダなの?」
「ええ。南アルプスにいる知り合いから取り寄せているおいしい湧水ですけど。ミネラルたっぷりだし、ある人が見たら、特別な自然の気のエネルギーが入っているっていうので、わざわざ送ってもらっているの」
「ふむ。じゃ、俺はその水でいいよ」
店主は、仕方ないわねえという顔をして、とりあえず水を持ってきた。
「ねッ。わかるだろ」
袋田マス江は、後ろのテーブルの彩香に言った。
「あれ、ジョークのつもりなんだ。いつも同じこと言うんだ。水はただなの、だってさ。あの男の冗談はさ、ひとっつも、面白くないんだ。ひとっつも!」
耳が遠いせいか声の加減がわからず、小声の悪口がすべて周囲に聞こえている。彼女が憎まれる理由の一つが、これであった。
睦子は弁解がましく、さっき冷蔵庫で冷やしていた庭師からの貰い物の赤い果物を、二つに切ってガラス皿に載せて持ってきた。一応は、上客扱いなのだ。
二村は「何だね、こりゃ。スモモの変種か。赤すぎて、まるで小動物の病気の心臓みたいだな。気色悪い」
大して関心もなさそうに、精神安定剤を取り出して、二、三錠を口に含むと、目をギロリと剥いて、まずそうに薬を飲み下した。
せっかく食べやすく切ってきた赤い果物について、ひとくさり庭師がらみのエピソードを披露しようと思っていた店主は、軽い失望を感じた。この二村という客は、わざと面白くない雰囲気を、作りたがるのだ。彼はそれどころじゃないという顔をして、むっつりと瞑目し、人生そのものの苦痛に耐えているような、難しそうな顔をした。