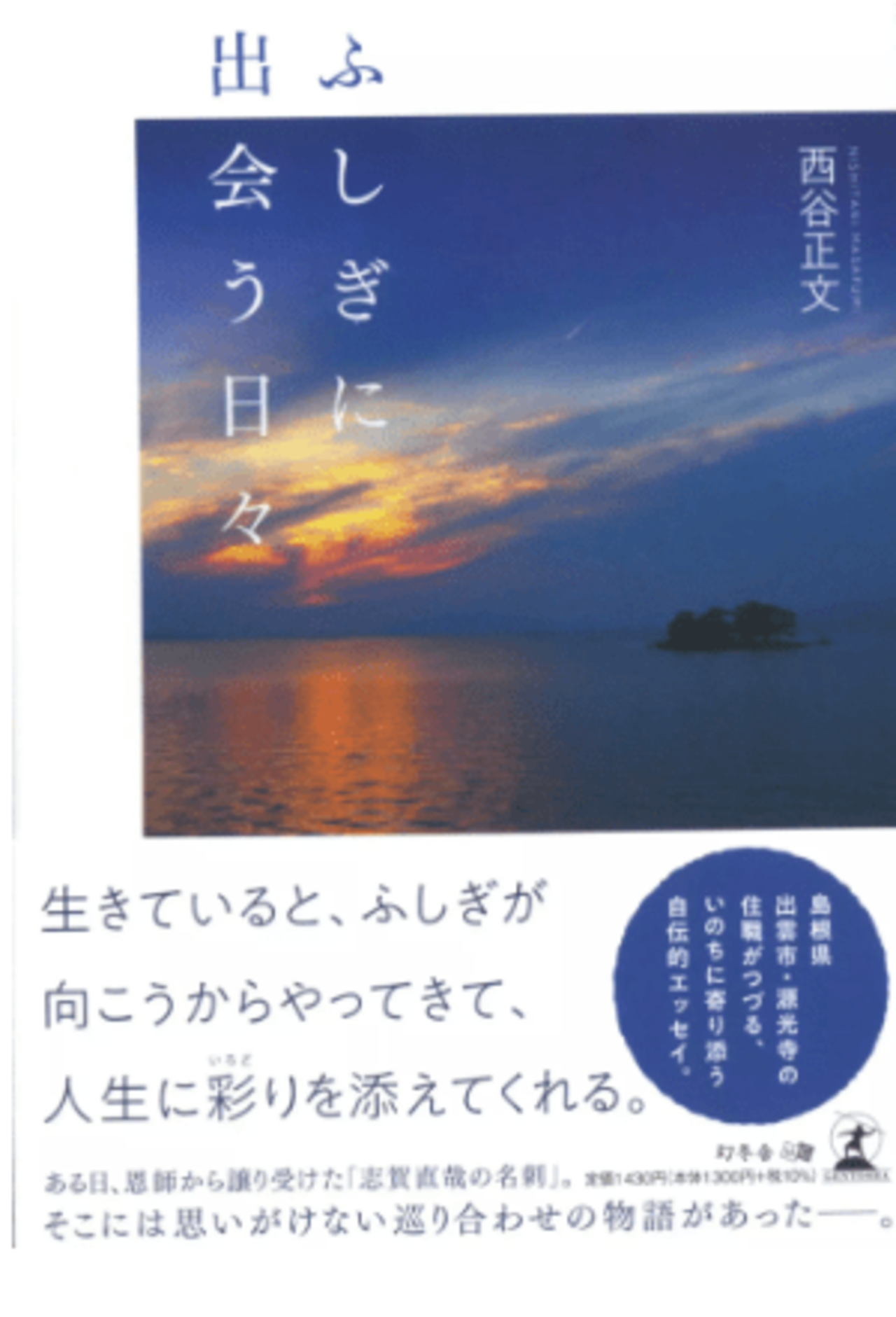ところがここで予想もしなかった、決定的な出会いが待っていた。中村正明さんとの出会いである。
中村さんは慶応義塾大学文学部で美学を専攻し、首席で卒業した方である。美学というとあまりなじみがない学問かもしれないけれど、広く哲学に含まれる分野で、「美」とはなにかを追求したり、具体的には音楽作品や美術作品を解釈したりしていく学問である。
中村さんは、私と同じ高校を卒業した先輩でもあった。美学では、のちにルドルフ・シュタイナーの思想を日本に本格的に紹介した高橋巌に師事し、コリン・ウイルソンの『アウトサイダー』などの一連の翻訳や、チェスタトンのブラウン神父シリーズなどの翻訳を手掛けた中村保男に英語を学んでいた。その中村さんは、この年初めて補習科の講師となり、英語の授業を担当した。
私にとって英語は、あまりおもしろい科目ではなかった。結局は生涯をこの山陰の田舎町で過ごすことになるだろうから、英語を学んでも将来役に立つことはないだろう、と勝手に思い込んでいた。テストでそこそこの点数が取れるならそれでよし。英語を身につけることなど、とんでもないムダな努力である、と中学生のころから考えていた。したがって、受験英語は苦手としていた。
しかし中村さんの英語は違った。単に英語を日本語に移すのではなく、英語を使った文化を日本語を使った文化に翻訳することを教えてくれた。受験英語という枠から外れて、翻訳とはなにかを伝えてくれた。この授業がとても興味深く、また、中村さんの人柄にも強く惹かれていった。
中村さんは最初の授業で、「私は教師ではないので、先生ではなく、さん付けで呼んでください」といって、私たちとの距離を近くしてくれた。気さくで相談がしやすく、どんどん人柄に引き込まれていった。
志望校は変わらなかったが、次第に中村さんが通った慶応大学も受験してみたい、という思いがわいてきた。現役のときには考えもしなかったことだ。合格するとは少しも思っていなかった。ただ、受験してみたい、との思いだけだった。
ところが受験をしてみると、思いがけず、合格してしまった。また、志望していた大学にも合格したので、ここでまた迷いが始まった。慶応大学文学部にも心理学科はあるけれど、実験心理学が主体で、私が考えていた、性格を変える心理学とは異なっていた。どちらを選ぶのか迷いに迷ったが、私は「距離」を選んだ。
つまり、自分の家からできるだけ遠く離れたところに行こう、と決めたのだ。父はきっともう一方の大学を選んでほしかったと思うが、私は頭を下げた。父が生きている間に私が頭を下げたのは、このときだけだったと記憶している。まだ私のすぐ上の姉も大学に通っていたが、父は許してくれた。その分、ぜいたくはいわなかった。そして、「必ず帰ってきます」とひとことつけ加えた。