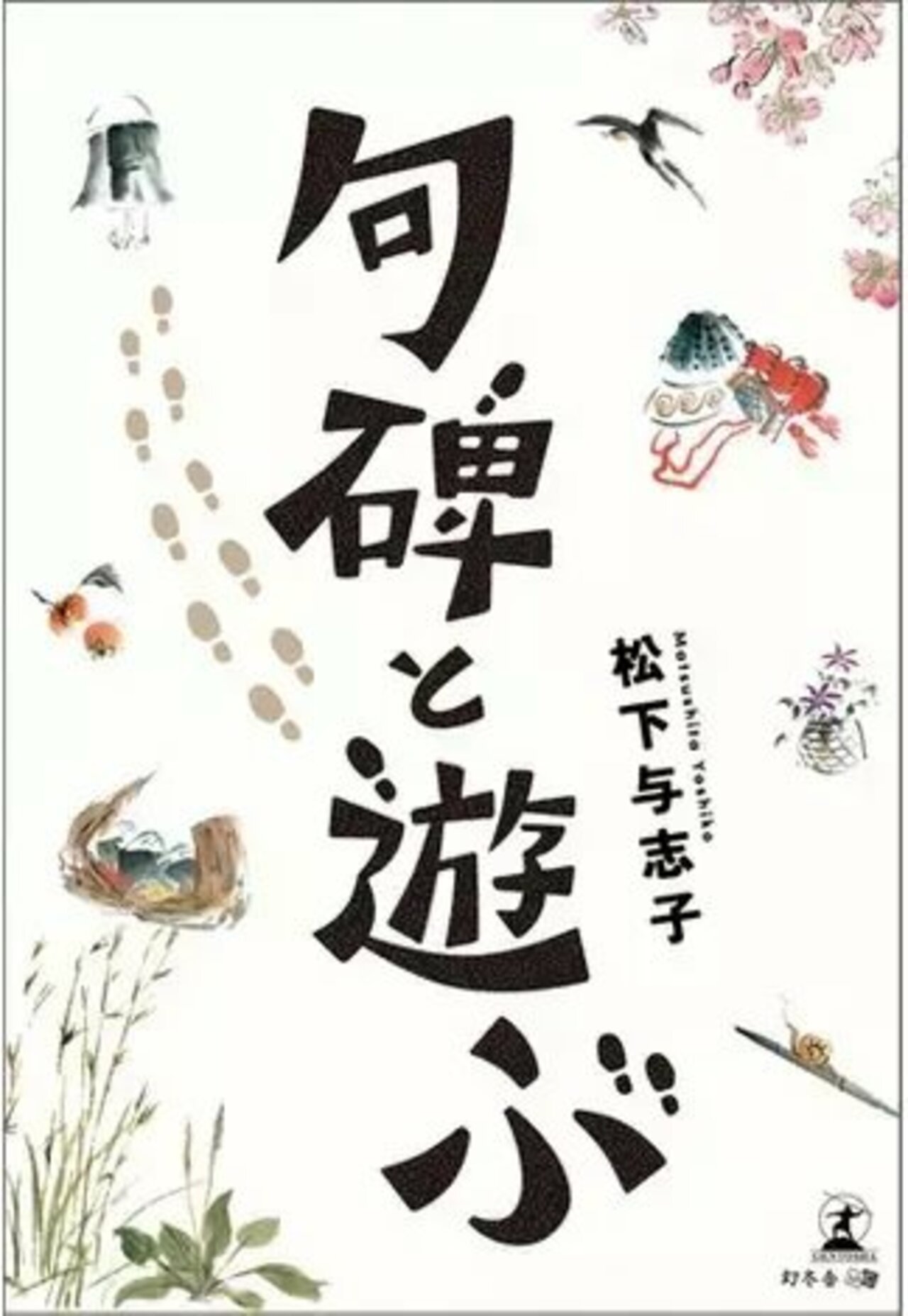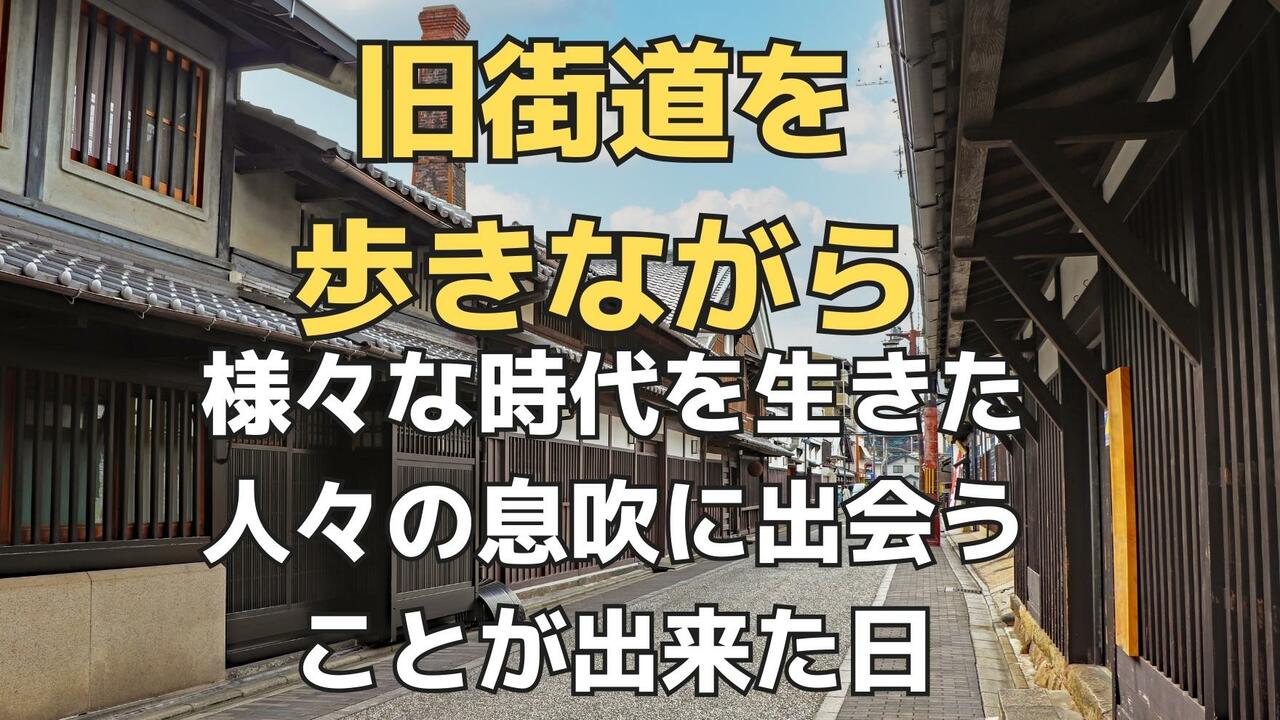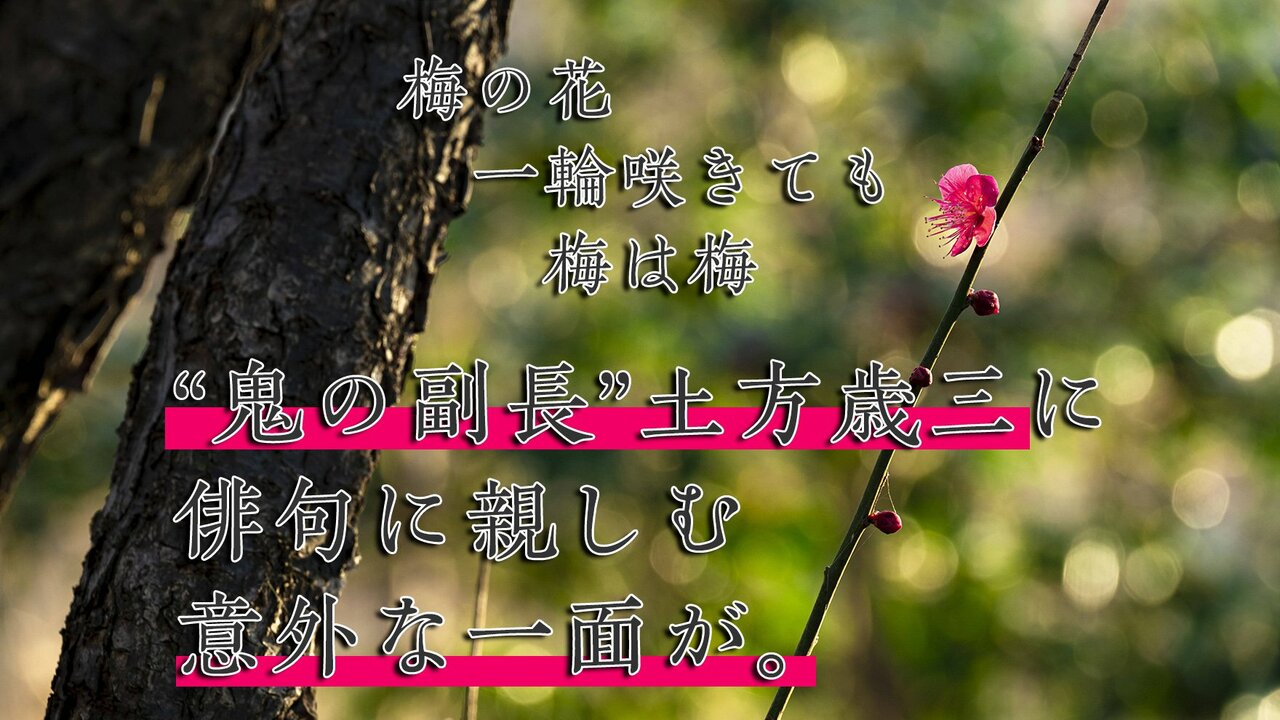愛と悲哀

「ごん、お前だったのか、いつも栗をくれたのは。」
ごんは、ぐったりと目をつぶったままうなずきました。兵十は火縄銃をばたりと取り落としました。青い煙がまだ筒口から細く出ていました。
いつ読み返しても、新美南吉の童話『ごんぎつね』の終りは哀しい。これまで多くの小学校の教科書に、この南吉の代表作が採り上げられてきた。この物語を読んだどれだけ多くの子供たちが、愛と悲哀とを幼い心に刻み込んだことだろう。
哀しみを背中の殻に一杯にした『でんでんむしのかなしみ』の話も新美南吉の作品の一つだが、一九九八年国際児童図書評議会ニューデリー大会で当時皇后の美智子妃殿下は講演をなさった際この童話についてご自分の深い思いを話されたことは有名である。
最近、愛知県半田市の新美南吉記念館を訪ねた。館の壁に「自分は愛と悲哀を書きたい」という彼の言葉が掲げられていた。彼は二十九歳の若さで結核のため亡くなったが、童話の他に童謡、詩、短歌、そして俳句も多く残した。
松籟を雪隠で聞く寒さかな 南吉
手を出せば薔薇ほど白しこの月夜 南吉
冬晴れや大丸煎餅屋根に干す 南吉
何となく童話作家らしい俳句の気がする。半田市立博物館の庭には彼に関係する句碑がある。
たんぽぽのいく日ふまれてけふの花
関係するという意味は、新美南吉が江戸時代の俳人鵤卯のこの句を小学校の卒業式の答辞の中で引用したからである。
彼は4歳の時母親を亡くしている。寂しい幼年期を過ごし小学校を卒業する晴れやかな自身への思いがこの句を引用させたのかと推量してみる。小学生の彼が、この頃から愛と悲哀を感じ取る心を持ち得たことが後の彼の作品に繋がっていったのだろう。
南吉の記念館のある辺りが実際に『ごんぎつね』の舞台なのだそうだ。
「この辺りでは今でも時折狐を見かけるのですよ。」
記念館の館員が語ってくれた。幻のごんぎつねのように人の心には愛と悲哀とが生き続けていくのだろう。
二〇一五年六月