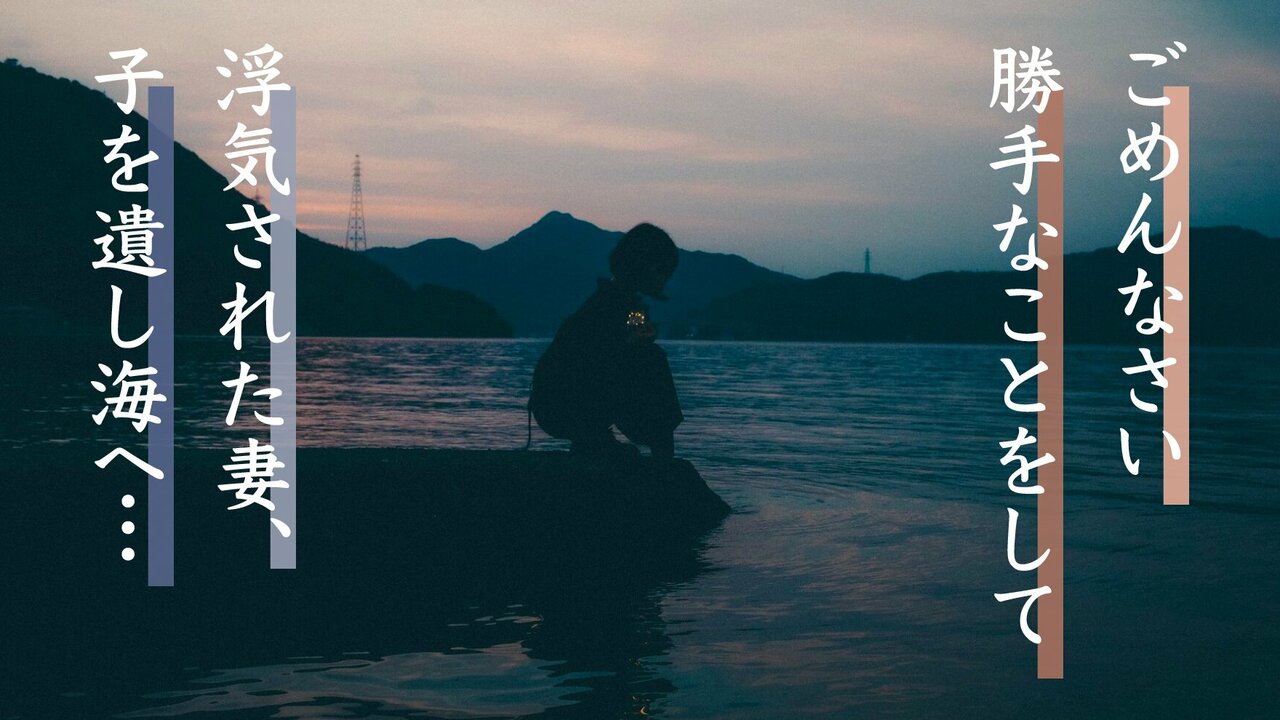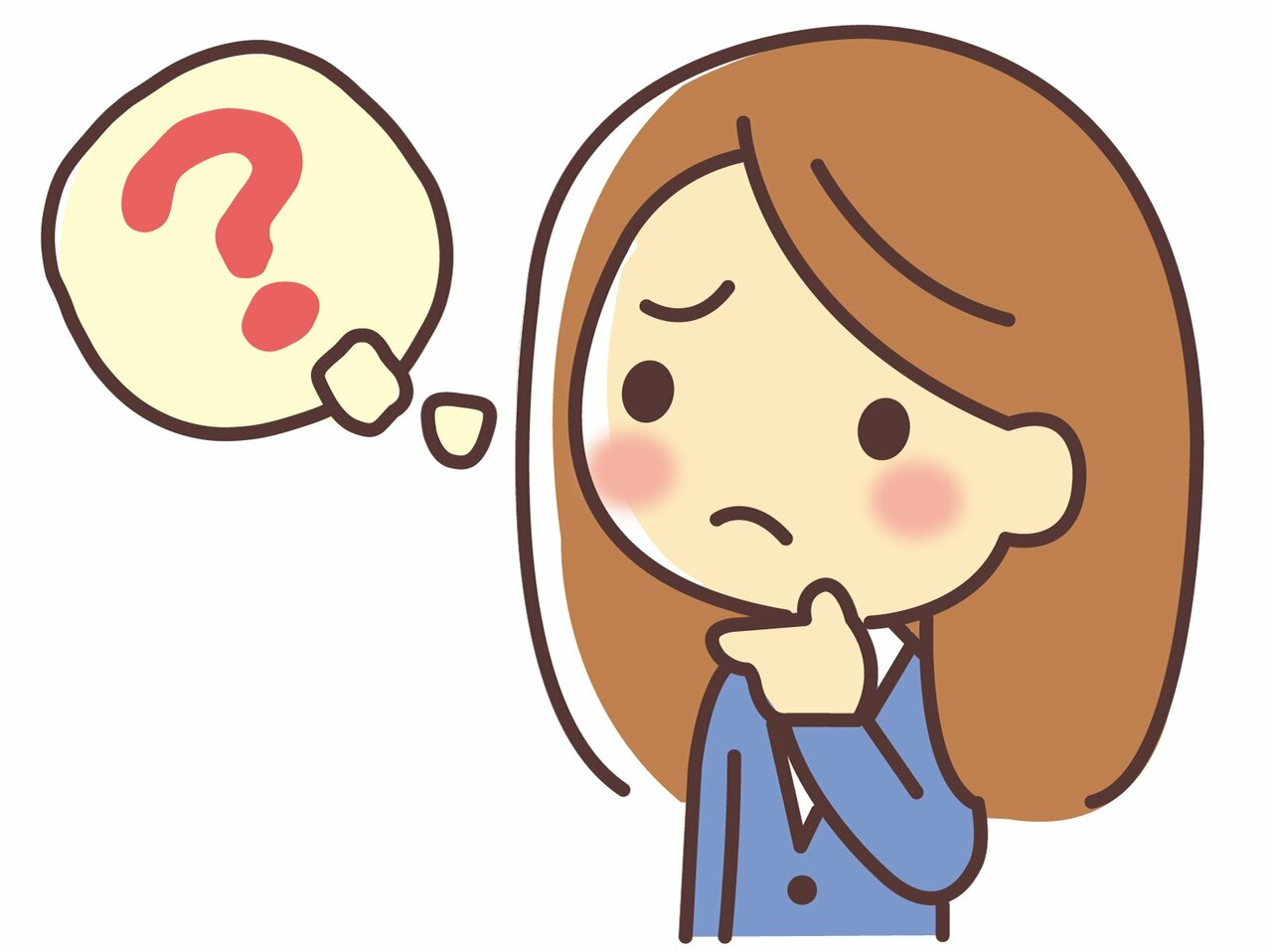第二楽章 苦悩と悲しみの連鎖
Ⅲ 添い遂げたかった愛のカタチ
誠子は実家を出たあと、ひとりで海の見える場所へと向かったのでした。電車に揺られ、外の景色を眺めながら、最後の決断をしていました。自分は今、これからどうしようとしているのか。本当に後悔しないのか。英介になにも話すことはないのか。子どもを残したままでいいのか。両親に相談しなくていいのか。ひとつひとつ、確認しました。
青い空ときらきら光る海面が眩しくて、きれいだなあと思う誠子の心は、まるでなにも心配することがないように穏やかでした。電車を降りた誠子は、海の方へと向かい、崖の先端を目指します。心地よい潮風に乗って漂う磯の香りが、子どもの頃、海で遊んだ楽しい想い出を蘇らせました。
そういえば、わたしって海が好きだったなあ。だから、ここへ呼ばれたのね。きっと、そう! 英介さんとは、山へ出かけたことはあっても、海へは一緒に来たことがなかったかも。一度くらい、誘ってみればよかったね。海のこと、すっかり忘れていた。そんなことを思っているうちに、眼下に広がる一面青の景色の前に、誠子は立っていました。
どれくらいの時間だったでしょうか。誠子は岩の上に腰を下ろし、風を感じながらしばし、目の前の海を眺めるのでした。海鳥の鳴き声が合図になったような気がして、誠子は立ち上がります。両手を広げて数回深呼吸をすると、誠子は靴を脱ぎ、岩の上に揃えて置き、持っていた大き目のハンカチを細長く折ると、それで足首を巻き上げました。
大空を見上げると、燦々と輝く太陽がゆっくりと少しずつ、沈みかけているところでした。
「太陽さん、今までありがとう。あなたが見ている前で、わたしがこれからしようとしていること、すべてお見通しですね。わたしは海へ帰ります。すべて自分で決めました。誰も憎みたくないの。わたしは英介さんのことが大好きです。英介さんのそばにいたい。ただそれだけです。どうか、見届けてください。海と一緒になることを。ありがとう」
そう言い放つと、誠子は海へと静かに飛び込みました。