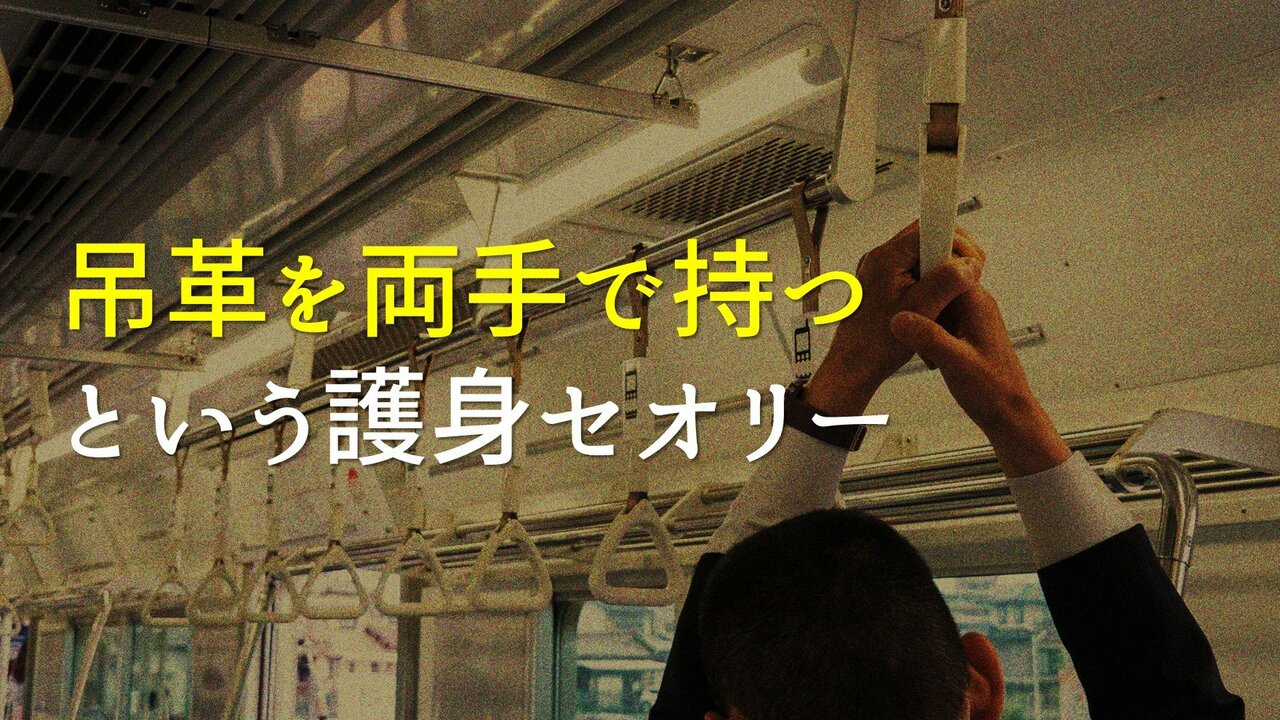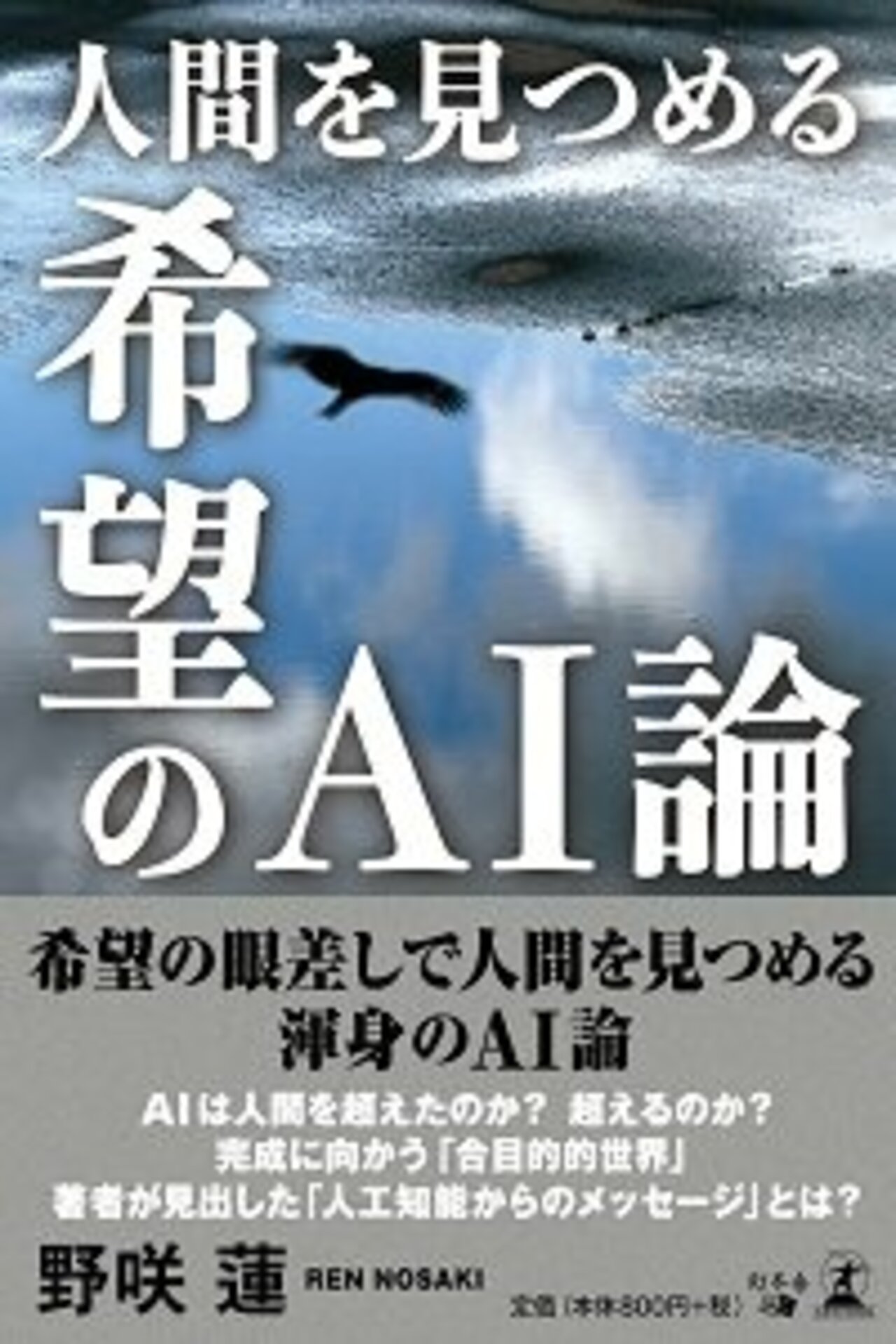第3章 AI INFLUENCE
第4項 希求
1 思い出せない風景
さて、少しここで脇道にそれてみたい。先日、私は久しぶりに東京に行った。新宿、西荻窪、吉祥寺。メガステーション、繁華街、住宅街の駅前横丁。相変わらず何処に行っても途切れることなく人で溢れている。
電車で新宿駅から西荻窪駅まで総武線に乗った。今は地方に暮らし、普段の移動は主に自転車を用いる。電車を始めとする公共輸送機関に殆ど乗らないので、その光景は私には新鮮に映った。
夜の7時頃だったが、車内は混雑しているという程ではない。座席は埋まり、適当な間隔で吊革を持ち立つ人がパラパラと並ぶ。人々はみな、吊革を持って空いた方の手や、膝元の鞄を抑えて空いた方の手や、もともと空いた両の手のいずれかで、スマホを見ていた。
仕事の疲れだろうか、気持ち良さそうに眠っている人が数人。放心に近くぼんやりする人が二人、本を読んでいる人が一人いた。
車内に会話はなく、電車が駅に着くときと駅を出発したときに、自動音声のガイダンスが流れた。乗る人より降りる人の方が僅(わず)かに多い。
窓越しに高架線の両脇に広がる種々の高さの住宅の建物の灯りが微かに見えゆっくりと流れては消える。東京は静かなところだったな、と思い出す。
帰りは夜行バスを用いた。ターミナルビルの待ち合い所はやはり人で溢れ返っていた。シートは埋まり、床に座っている人もいる。そしてやはり、スマホを見ていた。
空間にはたくさん、人がいるが、心はここになく気配が薄い。賑わいのない雑踏。その奇妙なギャップに満ちた光景に手持ちのカメラのシャッターを思わず切った。
誰も反応しない。チラリとすら目を上げず、人々の関心と気配は、手元のスマホの小さな画面から広がる、個々の壮大な情報世界に吸い込まれるように向けられていた。
バスがターミナルに入り、それに乗った。小雨に曇った窓ガラスを手で拭き、白銀灯の照らす誰もいない新宿オフィス街の通りを見ながら、スマホが浸透したあとの人々の帰途の移動風景を私は思い浮かべた。
静かな人々は静かにオフィスや学校やその他の出先から家へと移動していた。それより以前の車内風景はどうだったかな、と思い出そうとしてみたが浮かばない。
高校生の頃は週刊少年ジャンプが1号で数百万部売れていた。新聞を読む人だっていた。痴漢と見紛われぬ様、吊革を両手で持つという護身セオリーがあった。それらを繋ぎ合わせてみても継(つ)ぎ接(は)ぎの風景で何だかしっくり来なかった。
漫画と政治経済に関心がなく読書習慣を持たない人は、何をして何を見て何を考えていたのだろう。不思議だ。記憶なんて、習慣化された事柄に含まれる事象は殆ど覚えていない。
それにしても、ここまでスマホが日常に広く深く浸透した理由は何なのだろうか。バスは高速道路に入り、風景はなくなった。消灯して眠気が訪れるまで、私はぼんやりと考えを巡らせる。