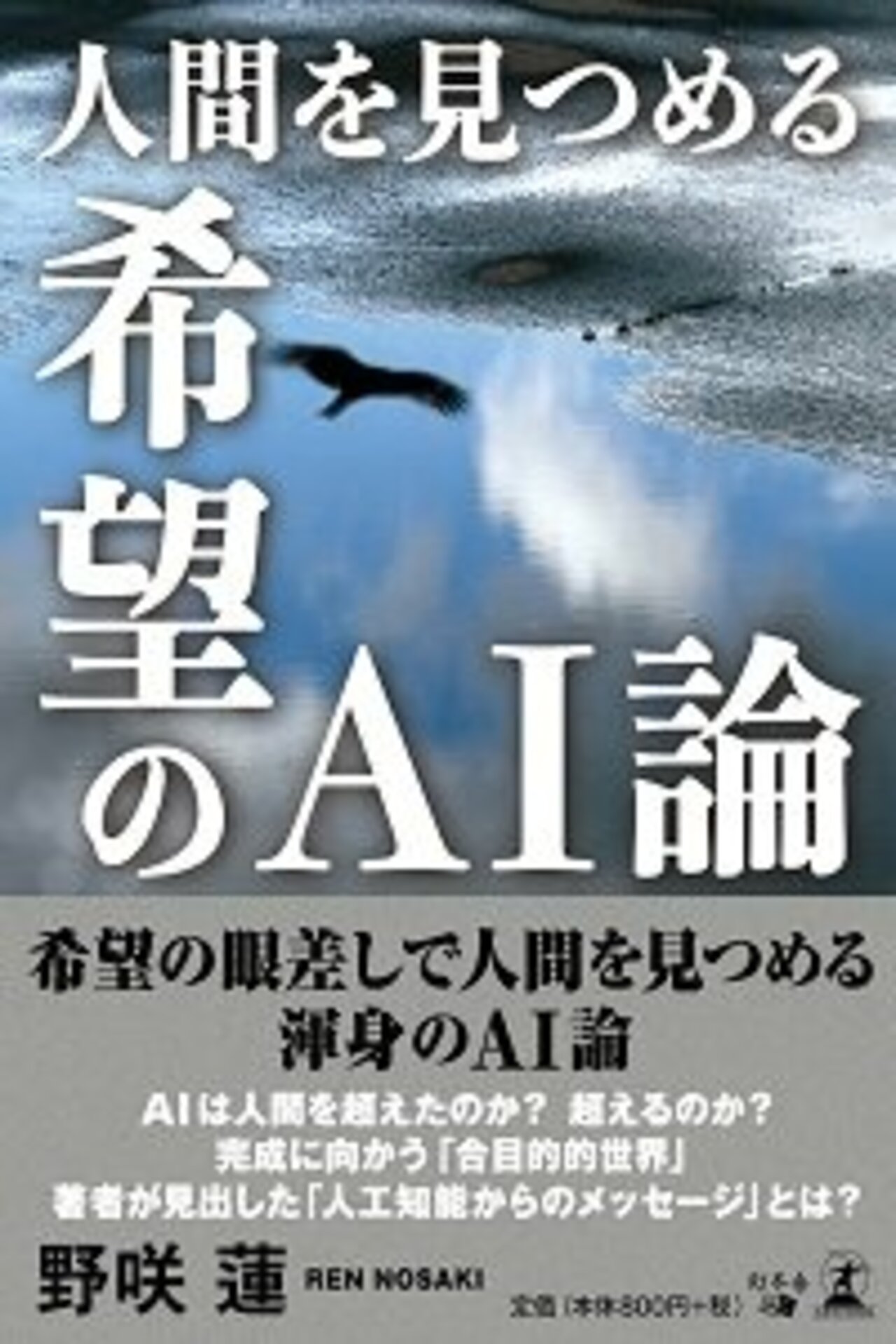第4章 合目的的なる世界
第5項 我々が選び、歩んできた道
「ある朝、グレーゴル・ザムザが何か気がかりな夢から目をさますと、自分が寝床の中で一匹の巨大な虫に変わっているのを発見した。」(フランツ・カフカ『変身』高橋義孝訳より)
世界で最も有名な書き出し(の一つ)から始まるこの小説は、たったの一文で、決定的な個人と世界の関係図に読者を唐突に放り込む。
前兆も予感もなく、端的にグレーゴルは虫になる。実生活を営めなくなったその虫を家族は打開策の持てぬままに軟禁する。しかし、“心と躍動しない身体”という実存の核心のみの残存を許容する重みに堪えきれなくなったザムザ家族(父母と妹)は、遂には「これ(彼)はグレーゴルではない」と言い切り、それを死に至らしめる。
実社会構成員としての機能性にのみ囚(とら)われきり、家族の間にあってさえ、その人の実存を見失う悲劇。この繊細にして致命的な存在論についての僅(わず)か百ページ足らずの短編小説は、我々の個人・家族・社会・世界の在り方について、人々の心に不条理のざわめきを起こすという文学的手法で警鐘を鳴らし、国境を跨ぎ世界中に広く読み継がれ、しかし問題の解決は為されず、100年近くの時を経た。
カフカが、例えばディケンズが『クリスマス・キャロル』の憐れなスクルージ爺にした様に、ザムザの憐れな転落に至る背景を詳細に(というより殆ど)描かなかったのは、この存在論の問題が個人に起因し個人に解決できる問題ではなく、誰にでも起こりうる(“That could be me”)、謂わば世界の在り方に起因する問題と捉えていたためだろう。
ちなみにこの年代に希代の文豪が、例えばアメリカ(アーネスト・ヘミングウェイ、1899~1961)に、フランス(アルベール・カミュ、1913~1960)に、チェコスロバキア(カフカ、1883~1924)に現れたのも、歴史の大危機個人発光原理に見て、偶然ではない。彼らの作家としての発光の源泉には、第一次世界大戦とそれを起こらしめた原理への壮大な危機感がある。