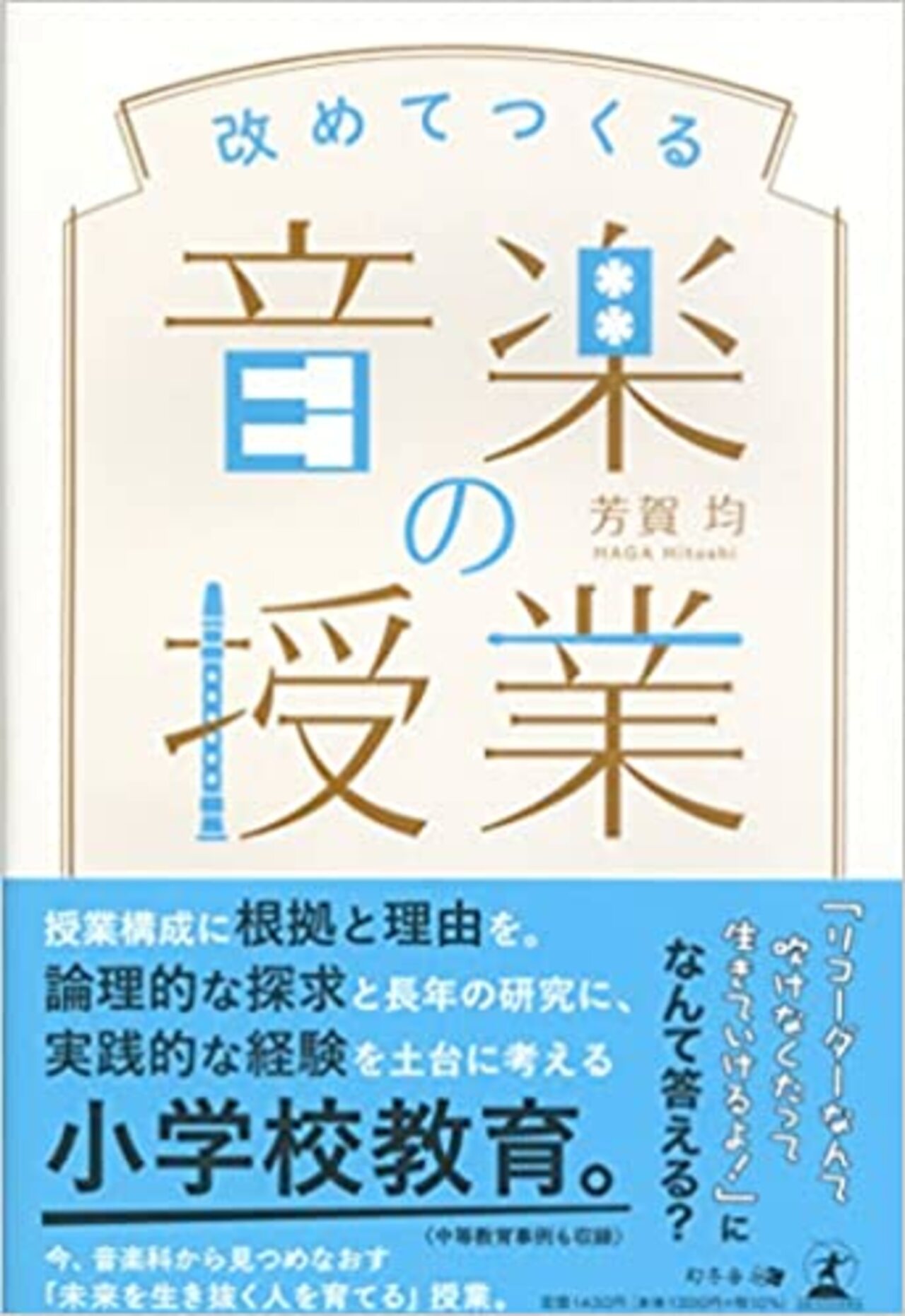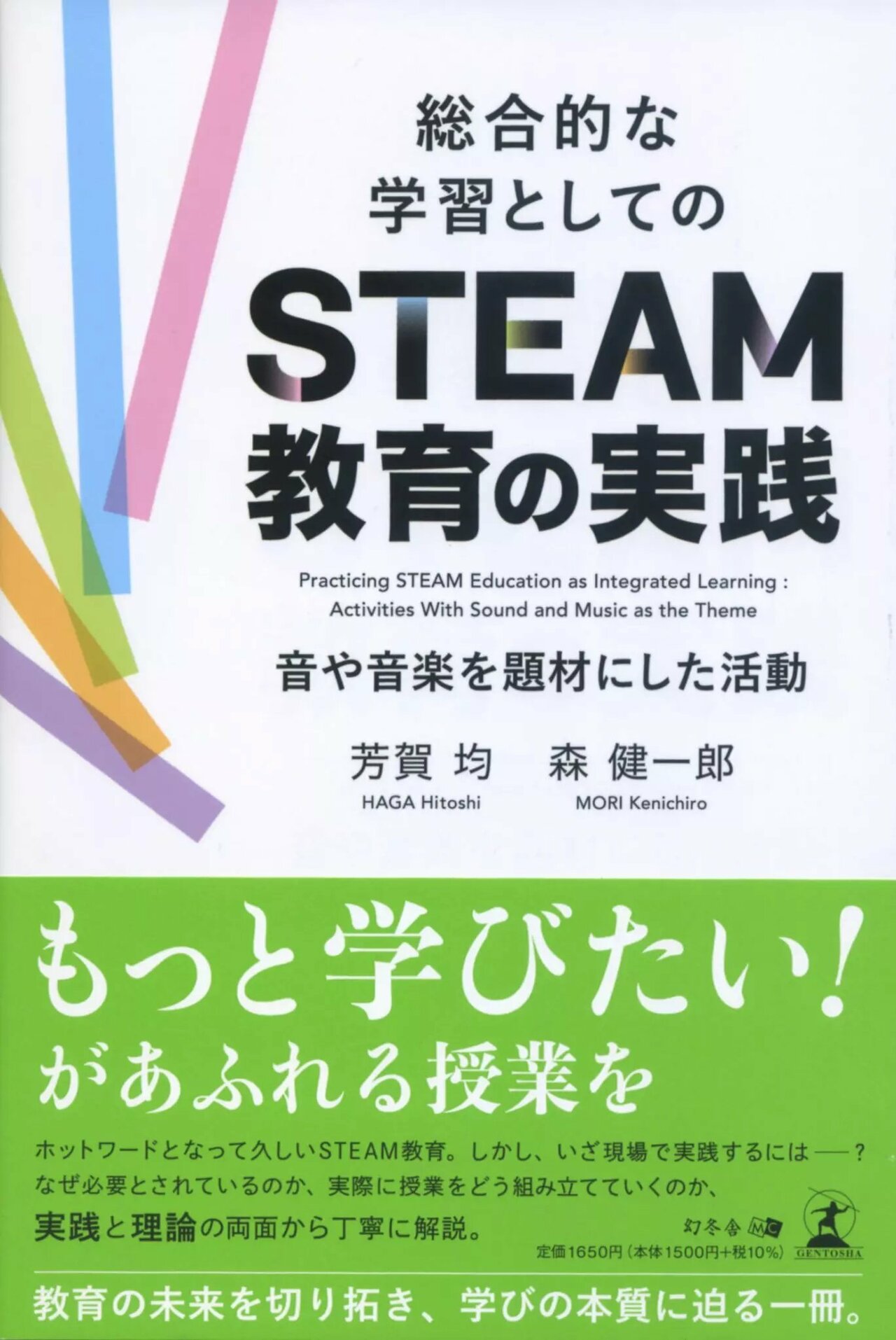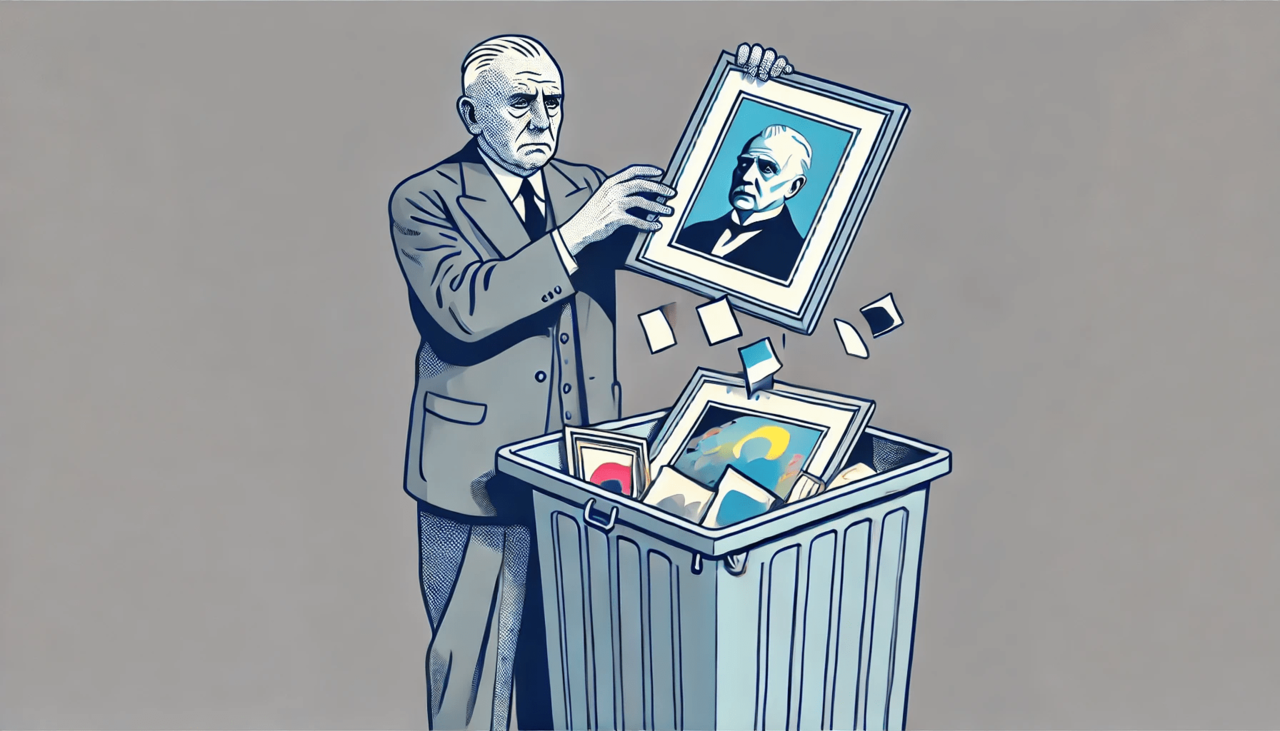なんと、文字面を眺めたら、この先「厳しい時代がくる」「どうなるか分からない」「このままでは持続不可能なのか」と、かなり衝撃的なことが書いてあってハラハラしてしまいます。
それに対して「創造性が期待される」「人間らしさが重要」「みんなで協力して知識を再構成して有機的なものにしていくことが大切」という、コンピュータでも可能な計算や暗記に留まることのない確かな人間らしさが重要であると書かれている印象を受けます。
これを大まかにいうならば、「これから先のどうなるか分からない世界をみんなで生き抜いていくための人間としての力を育成する」ということが、学校のお勉強に求められているといえるわけです。もはや、今の大人の知っている筋道とは異なった世界が展開されていく可能性があると考えられますから、教師をはじめとする大人自身が教わったように教えるということでは不十分、教わったようにしか教えられないという在り方では望ましくないということでもあります。
文化遺産の伝達は学校の大切な機能の一つではありますが、新しい価値を創造していける能力を育てていかなければ、自分たちの暮らす世の中が持続可能でなくなるということです。
これらは矛盾させるものではなく、文化遺産は生き抜いていくために重要であるという実感がもてるような学び方が求められます。
人工知能(AI)やロボットに取って代わられる(代わらせる)仕事や状況が増してくるにしたがい、それらに対して人間として関わっていくためにも、資質・能力(大まかに、これを心(ココロ)と頭(アタマ)と捉えてみることにします(〈1-2〉で後述))の育成が第9次学習指導要領に掲げられました。そして、それをすべての教科等で行っていくことになります。
もちろん音楽でも取り組むべしということですが、音楽という教科は試行錯誤を伴う活動に大変適しています。何といっても最大の特性は、「自分たちが行った試みのレスポンス」※3が速く、しかもそこに快・不快が伴うということが挙げられます。
自分たちのパフォーマンスがすぐに結果として現れ、しかも何度やり直しても作品がだめになってしまう(水彩絵の具で何度も描き直したり、彫刻刀で削りすぎたり、ダンスを何度も踊り直して体力を大きく消耗したり……)ことはなく、達成したら快感が得られるという点で、大変有利な教科であるといえます。そうした特性を最大限に生かすことができると考えられます。
※3 芳賀均・森健一郎『楽しい合科的学習の実践─音楽と他教科の合科・STEAM 教育を考慮した教科横断的な学習─』文芸社、2020、p.125. 他。