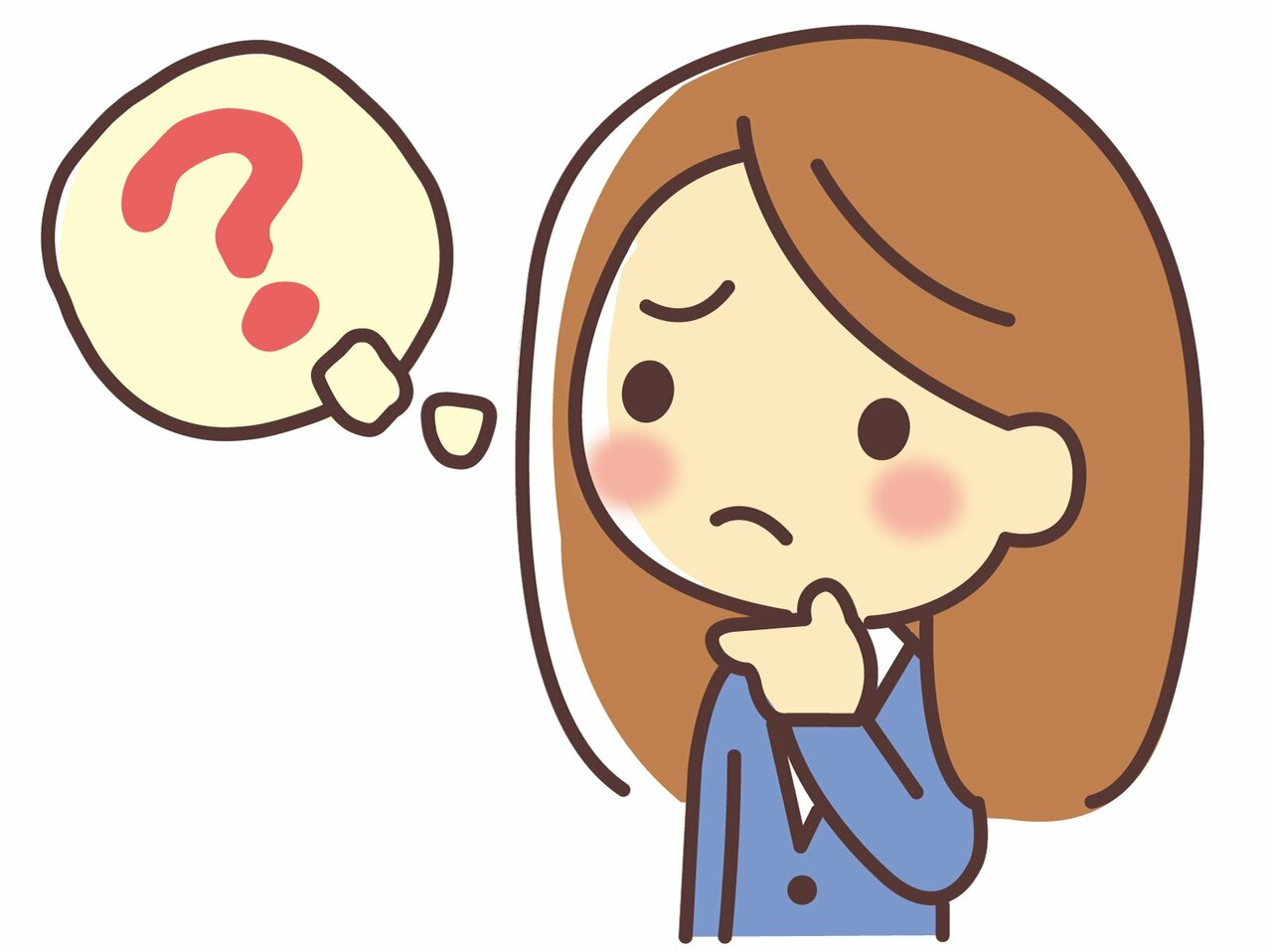Ⅱ 家族を守るために
農村のような風景が広がっています。どこの家もあまり豊かには見えなさそうな部落です。それぞれがわずかな田畑を耕し、精一杯の日々を暮らしながら、家族としての営みを大事にしていました。
のどかに見える風景だけが、いつもと変わらない、自然からの贈り物になっていたのでしょうか。自然とともに生きること、部落での共存がふつうになされていた時代のようです。貧しくも、笑いが絶えないというそんなイメージが浮かんできます。恥ずかしいという感覚さえ持ち合わせていない、とても純粋で美しい命として存在している世界のように感じました。
両親の家計を助けるため、まだ幼い妹や弟の将来のため、碧衣は早くから奉公に出ることを決意しました。親もとを離れ、家族と離れ、初めて暮らす他人の家でのなにもかもが初めての生活でした。
子どもながらに精一杯の毎日は、本当に大変だったと想像できます。いや、もしかしたら、私の想像をはるかに越える現実だったかもしれません。
奉公先の家には、どんな方々が住んでいたのでしょう。大勢の人が出入りしていた商いのお家だったように感じました。雇われ先の旦那さん、女将さん、子どもたち、他の奉公人、お得意さんなどなど。
そのようななかで、叱られることは当たり前でした。できて当たり前です。たまには、褒められたこともあったでしょうか。懐かしい家族の顔を思い出しては、辛いこともひたすら耐えた、忍耐の連続だったかもしれません。
心配をかけちゃいけないんだ。わたしががんばるしかないんだ。そう、わたしは家族のために、今ここにいる。両親を少しでも楽にさせてあげたい。弟や妹がちゃんと大きくなるように、よその子から笑われることのないように、不自由さを感じることがないように、みんなで笑って過ごせる時間が増えるように、わたしが働くことで叶うなら、ここで頑張るんだ。
なんどもなんども、碧衣は涙をこらえながら自分にいい聞かせていました。