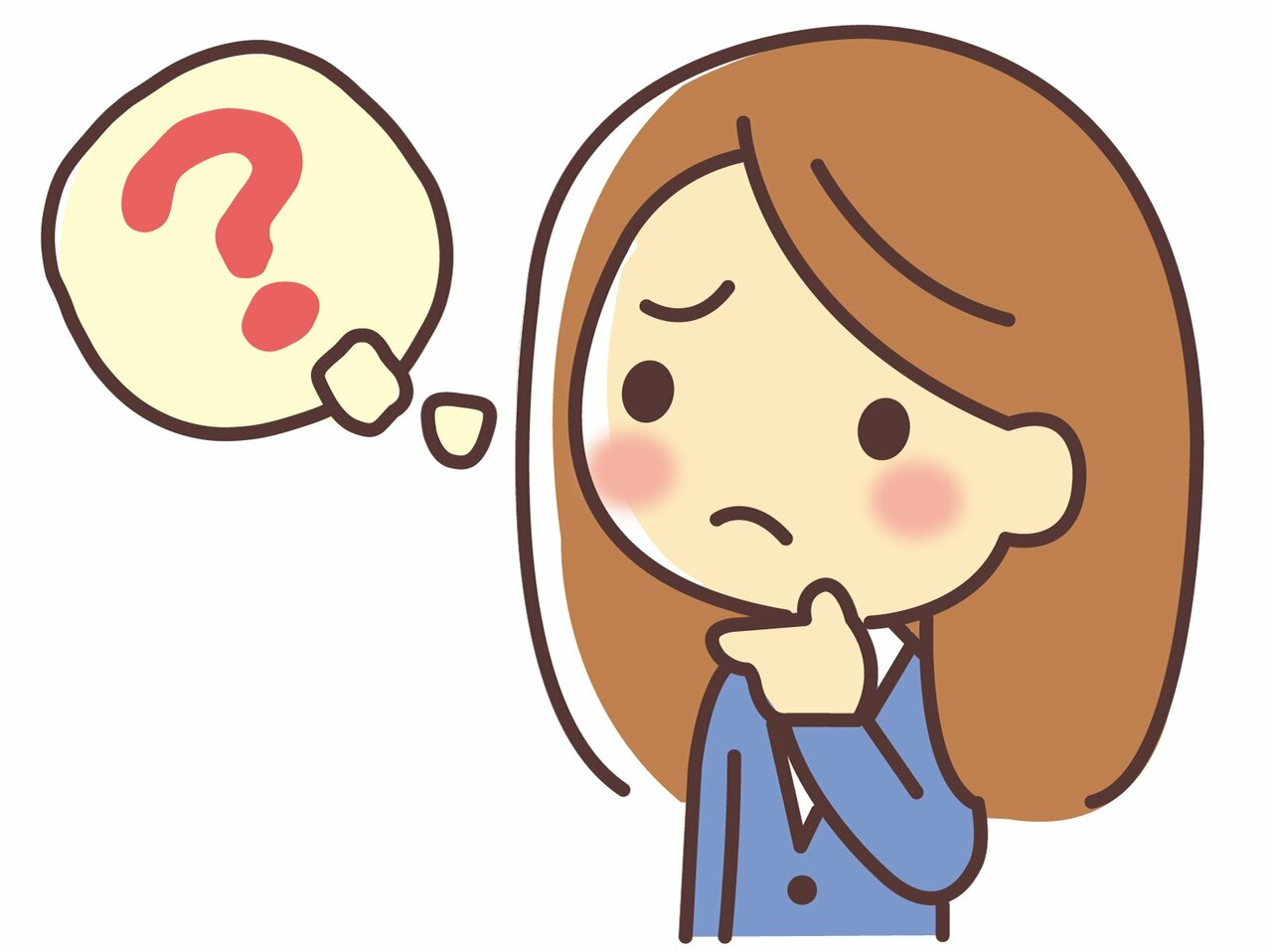第二楽章 苦悩と悲しみの連鎖
Ⅱ 家族を守るために
あるとき町中で、初めて目にした花魁の姿に、碧衣は目を奪われます。
「なんて綺麗なんやろう」
歩く姿にも、顔の表情にも、身のこなしにもすべて、女性としての最高美を言葉にならない感覚として、碧衣はキャッチしたかのようでした。
その晩、碧衣はなかなか寝付けない夜を過ごしました。昼間に初めて見た花魁の姿が頭から離れず、ほぼ一晩中、想像を巡らせていました。
翌日、仕事を終えると、奉公先の旦那さんに時間を作ってもらい、碧衣は真剣な眼差しで旦那さんに、どうしても聞きたかったことを伝えたのでした。
「昨日、あでやかな着物を着た人を見たのですが、あの女の人はなんなのですか?」
旦那さんはまだ何も知らないであろう碧衣に、ゆっくりと説明をされました。女郎が男の人の相手をするとはどういうことなのか。女郎になるためには、たくさんの芸事や教養も必要なこと、花魁になれるのはほんのひと握りの女郎だけであること、またそこは、とても厳しい世界でもあることなどについて、碧衣は黙ったままじーっと聞いていました。
碧衣の頭の中では、ぐるぐるといろんなことを想像していました。学問も芸事も知らない碧衣には、女郎なんて到底できっこない。いったいこの子は何を考えているのだ。せっかくうちで、ようやく使えるようになってきたところなのに、今更なにを言い出すのやら……。
旦那さんはまさか、女郎になりたいなんぞ言い出すまい。ただ初めて見た珍しさから聞いてきたのだろうと、軽く思うことにしたようです。話を聞き終えた碧衣は丁寧にお礼を述べ、部屋をあとにしました。
さて、布団に横になった碧衣は、先ほど旦那さんから聞いた女郎の話を、頭のなかで再現しながら自分の姿と重ね合わせていました。自分にもできるだろうか。学問も芸事も今から習って上達するものなのか。どれくらいお金がかかるのだろう。でも。もし、女郎になれたなら、今よりももっとお金はもらえるのではないだろうか。そうなったら、お母さんを早く楽にしてあげることができるのではないか。
わたしは今よりもお金が欲しい。そのためなら、男の人と床を一緒にするのは……、仕方のないこと。これまでだって、ガマンをしない日はなかったのだから。ガマンの内容が変わるだけの話ではないか。あんなにきれいであでやかな着物を着られるのは花魁だけなら、わたしも着てみたい! そうなら、まずは女郎になるしかない。明日、旦那さんに話してみよう。
碧衣の心は、美しい花魁として町を歩く道中の姿だけが目に浮かび、初めて見出した希望の灯に、どことなく軽いあたたかな感覚に包まれていたようです。