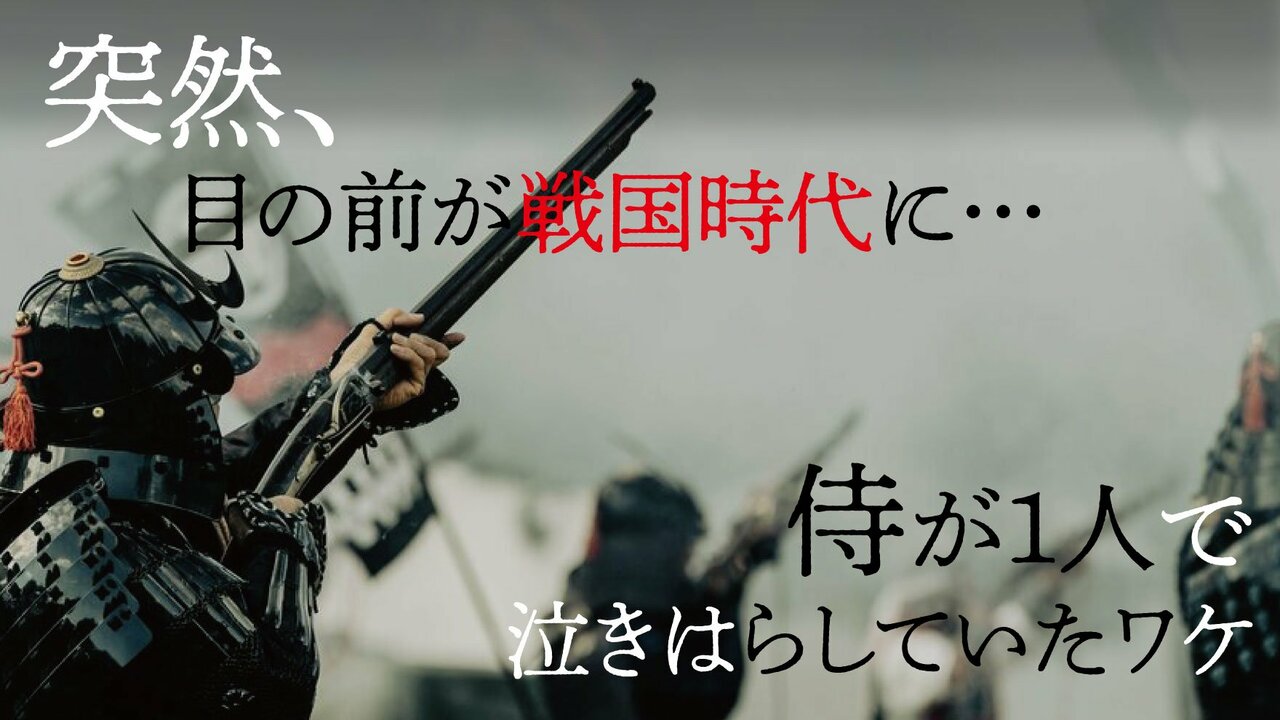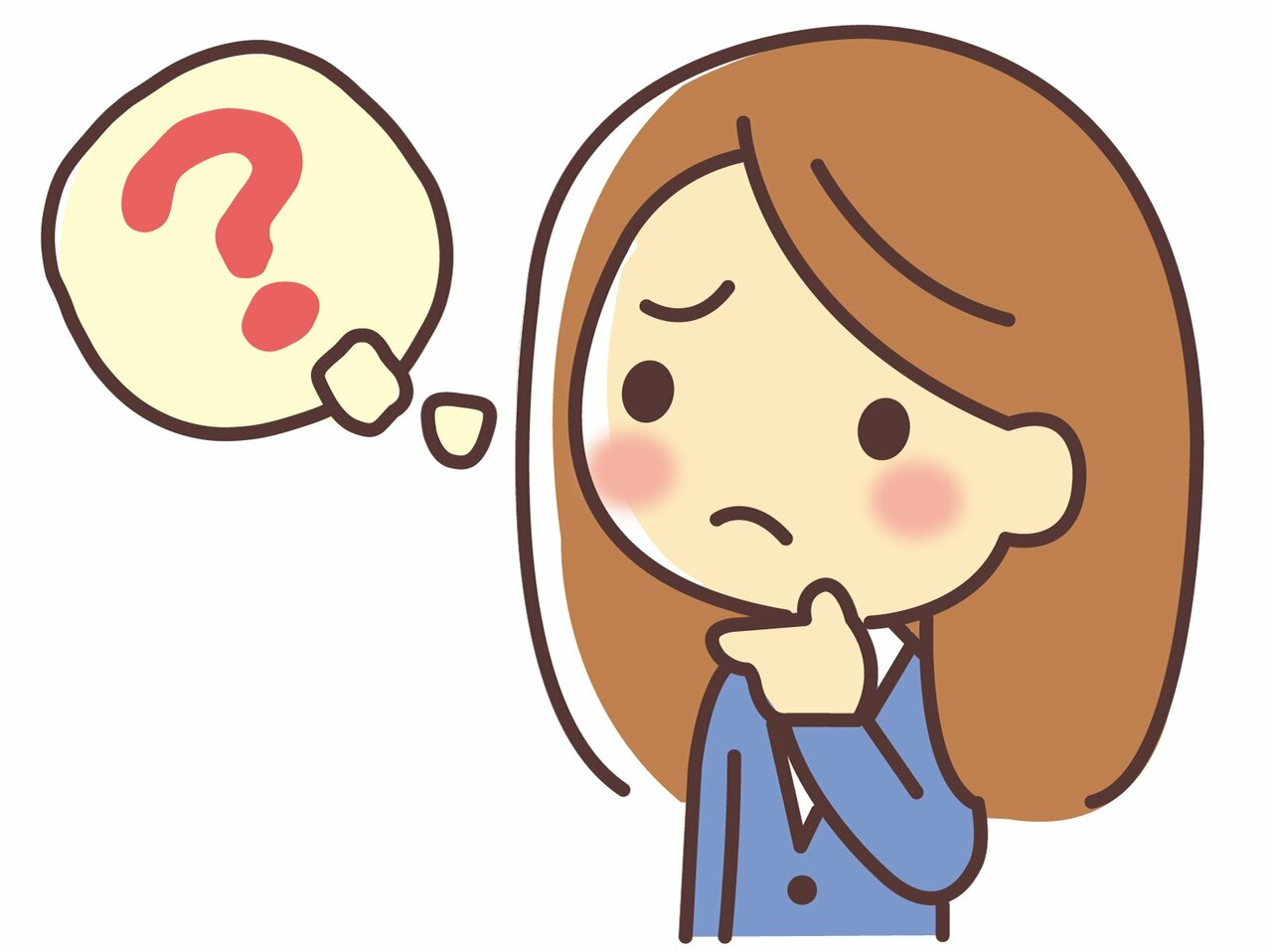第二楽章 苦悩と悲しみの連鎖
Ⅰ 家族を守れなかった悲しみにくれて
普段わたしたちが何気なく言葉にしていること、あると思いますが、自分なりの信念みたいなものであったり、勝手に思い込んでいることだったりですね。日常的な会話のなかで、口ぐせのように繰り返し話すこともあるかと思います。誰かとの会話でそんなとき、軽く聞き流してスルーすることもあれば、後になって急に思い出すこともありませんか。
そんなふとしたことがきっかけで、そういえば、あんなこと言っていたなあと本当に軽く思い出したときに、このような言葉が浮かんできたのです。
「神も仏もいるものか。私はそんなものは信じない。信じるものかっ……」
あまりに突然に、ある光景が頭のなかに映しだされました。辺りは薄暗い場所です。どこかのお堂のような、ヒンヤリとした空気が張り詰めているように感じました。床に座ったまま、膝の上で両方の拳をキツク握りしめ、わなわなと震わせながら、絞りだすようにして声を放つお侍さんが、目の前に現れました。
一夜にして家族のすべてを失ったことへの怒りと悲しみに、泣きはらした目は赤く腫れているようでした。たった一晩、仕事で家を留守にしたばかりに突如として起こった惨状を受け入れることは、このお侍さんにとっては、絶望の底へ一瞬にして突き落とされたかのような出来事だったようです。
その後、片手で刀を持つと床に立て、真っすぐに前を見つめるふたつの眼は、しっかりと見開いてはいるものの、どこか遠くを見ているような、見えない姿を必死に追いかけているような、途方にくれて悲しみのどん底に突き落とされまいと、身体の奥深くに灯る命の熱さを確認しているようにも見えました。蝋ろう燭そくの炎がゆらゆらと、わずかな灯りを放っています。
“俺は……、一家の主として、大事な家族を守れなかった。この手で守りたかったのに……。守ることができなかった。なんという無念極まりなきこと……”