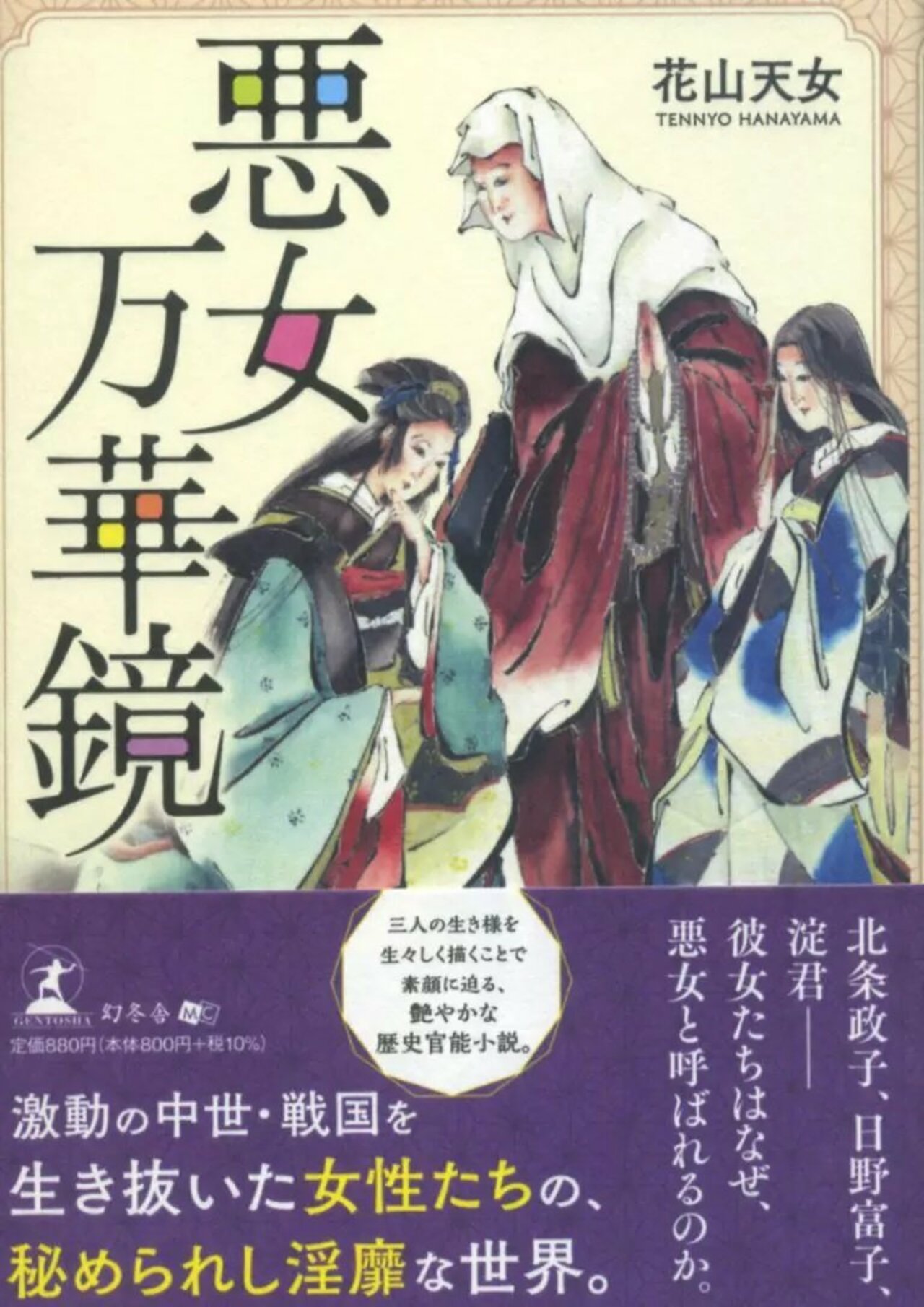二 新鉢を割る
(今宵こそ何としても、私は佐殿と夫め お婦との契りを交わさなければならぬ)
頼朝に想いを募らせていた政子は、判官邸へ輿入の夜半、思い切って山を一つ越え、伊豆山権現の頼朝のもとへ走った。現在、熱海市伊豆山に鎮座ます伊豆山神社のことで、ここは、かつての大旦那であった源氏に好意を抱く多数の僧兵を擁しており、一介の地方豪族の手に負えるものではなく、二人が堕ち合うには格好の場所であった。『源平盛衰記』によれば、政子は自分で
「暗夜をさまよい雨をしのいであなたの所に参りました」
と話したと言う。
時に治承元年(1177)三月、頼朝三十一歳で政子が二十一歳、頼朝が配流されてからほぼ二十年が過ぎていた。政子は宿坊内の頼朝の寝所へ忍んだ。
あらかじめ、判官との婚礼を逃げ出す覚悟を側近から伝えられていた頼朝は、愛しい女を迎えるため、前夜から身体を入念に洗い、ことに一物の左右裏表、根元から雁かり、包皮の内の隅々まで、一点の恥垢も留めないように磨き立て、用意万端、褌も脱ぎ捨て、丸裸の仁王立ちで待っていた。
「本当によう来てくれた……」
佐殿のやさしい言葉は何度聞いても政子の心を熱くする。が……、いきなり男の股間が政子の目の前にあった。時には湧き出る情欲も心のなかだけに納め、彼女が今日まで千秋の思いで待ち焦がれた頼朝のそれは、予想に反し暗い藪の中に身を潜めて恥じらう蓑みの虫むしのようであった。とたんに政子はガッカリした。
(これは一本の肉の箸のようではないか、陰毛の中に隠れてしまっていて、痒いところをこするほどのもので、いざという時はお役目を果たすことができるのかしら……)
政子がいつかこの日のために秘かに求めた枕草子のように、佐殿のご一物は、怒り狂って天をも突かんばかりの青筋を浮かべた逸物でなければならなかった。
春画に登場する男性の一物は、いずれもその様な逞しさと怒りを表現しており、この齢になるまで未通女であった政子は男性の一物とは、みなそれが当たり前と思っていたのである。それにしても最前に目にした判官の一物は、ずいぶんご立派だった。
「政子どの、貴女は私の一物がどんなに大きくて、威々しいものかと期待していたのでしょうね、でも残念ながら、今はその思いが外れて後悔の気持ちでいっぱいなのではないのですか」
政子は何といってよいのやら、言葉を見つけることができなかった。期待した男のご本尊がこうと知っていたら、初めから父、時政の指図どおり、赤ら顔で品のない大入道ではあるけれど、その場を逃げないで、素直に留まっていればよかったのかもしれない。