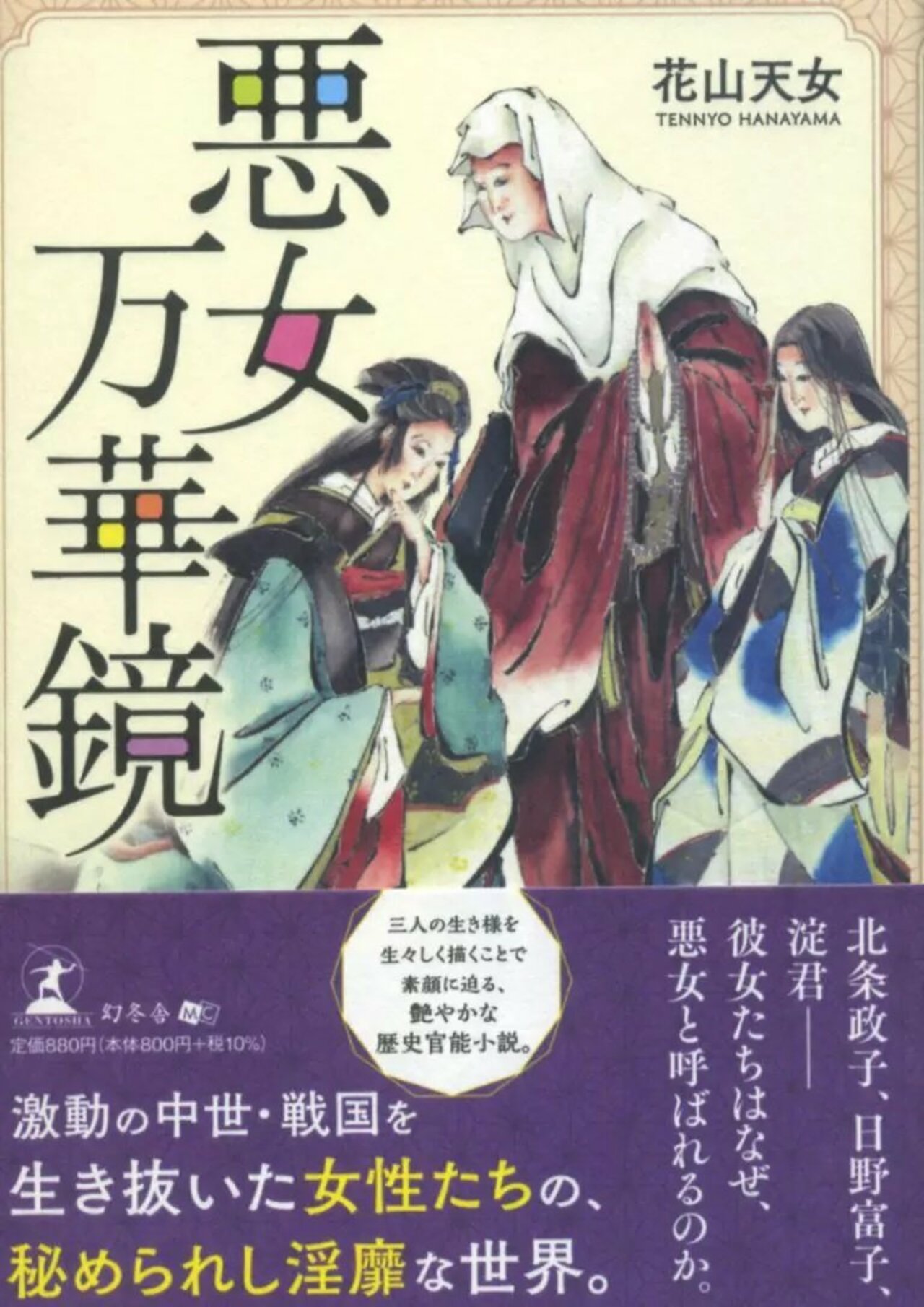第1部 政子狂乱録
一 蛭ヶ小島
巨大な蝮が女の花門を、ぬるり、ぬるり~と背後から攻めたり引いたりを繰り返す度に、女の狂おしい喘ぎに併せて、夥しいほどの淫汁がその繋ぎ目から漏れ出している。そして女の桃色に膨らんだ花弁が、男根と調和しながら挑発するように開閉を政子を目の前に繰り返していた。
政子は、このすさまじい快楽の地獄絵に頭が真っ白になってしまった。恥ずかしいけれど、彼女の股間にも夥しい潤いが感じられ自然とそこへ手が巡る。
(あのお豆殿の歓びようはなんとしたものであろうか、男女の契りとは何と激しくて淫靡なものか、私もお豆殿のような悦びを感じることができるのだろうか)
判官は女を早く快楽の頂上へ追い込もうと背後から激しく揺さぶりを繰り返す。女の悶えや喜悦の呻きは異様なくらい荒々しいものになってきた。奇妙な格好で恥ずかしげもなく男をしっかり咥えこんでいる女の熱い粘膜は、緊縮力を加えて、さしもの判官も酔いしれた表情が窺われる。
「ああ、もう、たまりませぬ~、もう逝いきまする、もう逝かしてくだしゃりませい~」
女は汗に濡れた背中を男の胸にぐっともたれさせ、後向位で繋がった裸身を男の膝の上に乗せ上げ、甘えかかるように首をねじって男の唇を貪り続けた。もはや判官とお豆の方は、政子の存在など忘れたように狂態を繰り広げ、最後の仕上げへと向かっているようだ。
「ああ、もうダメつ~」
男から唇を離した女は上半身をのけ反らせ、絶息するような呻きを漏らした。
「お豆、儂も逝くぞ、そなたと一緒に極楽を見ようゾ」
(嫌らし! 判官は何というお人か、こんなこと判官殿にされたら、私のおめこは壊れてしまいそうじゃ、佐殿と情を交わしたい、ああ佐殿に早く抱いてほしい)
佐殿とは頼朝のことで、流罪前には右兵衛佐の官についていたので、今でも佐殿と呼ばれていた。判官とお豆の方が、延々と繰り広げる狂気の情景に、いたたまれなくなった政子は、御免なされとばかりその場を逃げ出した。