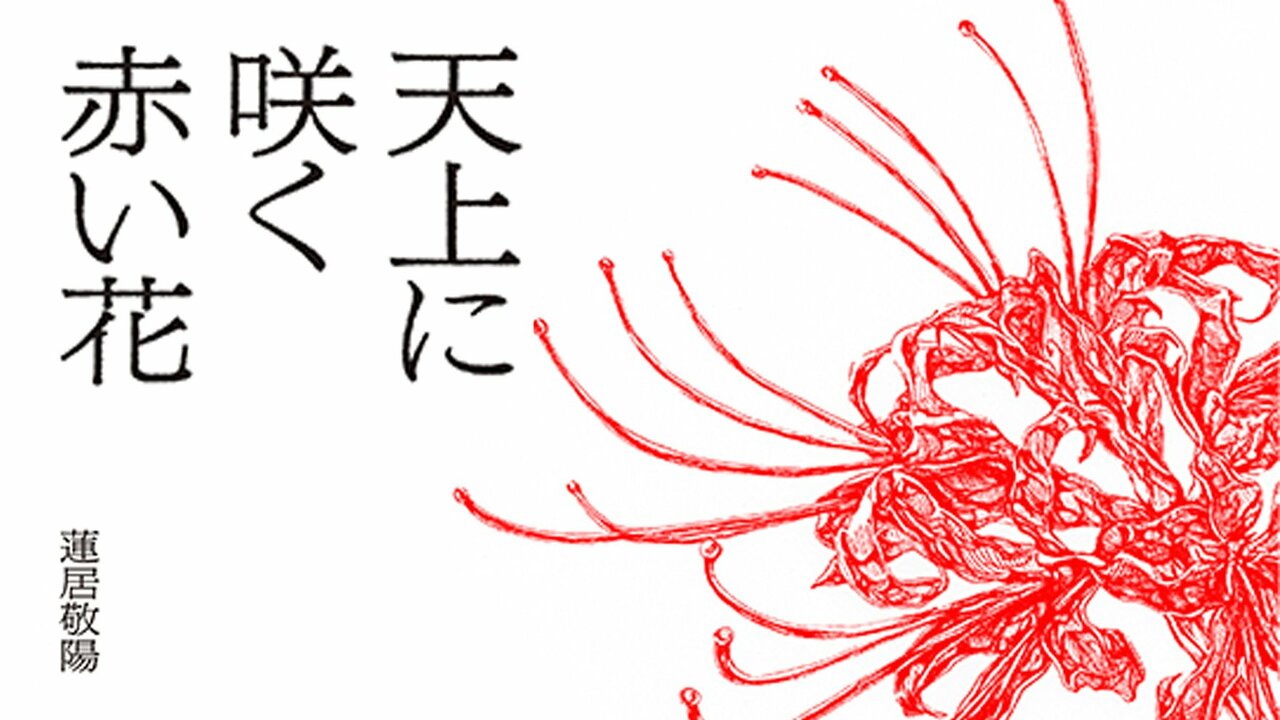一部 事件発生と、幼なじみの刑事とお巡りさん
二〇〇五年九月二十三日
「お前の考えていることは、分かってるんや。昔俺に注意したうっとうしい小母さんは、今回殺され掛けた女やと思っとるんやろう。そんな偶然がある訳ないやろう。大体そのおばさんが誰なのかさえ知らん。事前に教育委員会に届け出ていない者に、学区外通学を許す訳にはいかないと急に言われて、転校することになったのは、たぶん誰かが密告したからやろ。
その後転校した中学で、俺は随分いじめられたよ。転校しなければ、放火することもなかったしな。仮に今回事件に巻き込まれた女が、密告した張本人だったとして、今になって俺がその女を殺したって言うんか! 少しは頭を働かせたらどうなんや。恨んで殺すならとっくに殺してるやろ」
岡島竜彦の言葉には説得力があった。元々高倉豊だって、彼を疑っていた訳ではなかった。とは言え、岡島竜彦にここまで言われては、引くに引かれず、形勢を逆転したくもなった。
「じゃあ、何で赤穂に戻って来たんや。お前が戻って来て三ヶ月もしないうちに、中原純子は死に掛けてるやないか! これが偶然と思えるか! お前には動機があるやろうが!」
高倉豊は語っているうちに、どんどん強い口調になっていった。
「三ヶ月って、あほか。時間が経ちすぎや! そんなもんが動機と言えるんか! 俺は生まれ育った町に帰って来ただけや! それがそんなにいけないことなんか! もう、帰ってくれ!」
岡島竜彦も負けじ魂を発揮して、高倉豊に言い返しながら引き戸を閉めた。もはや高倉豊の知っている、岡島竜彦でなくなっていることは明白な事実だった。
高倉豊は部屋から追い出されたような気持ちになって、閉められた引き戸を黙って見つめることしか出来なかった。これで岡島竜彦が、中原純子の事件に関与していないことは確定的となったが、自らの過去の過ちを告白することが出来なかったため、高倉豊は虚しさを感じていた。