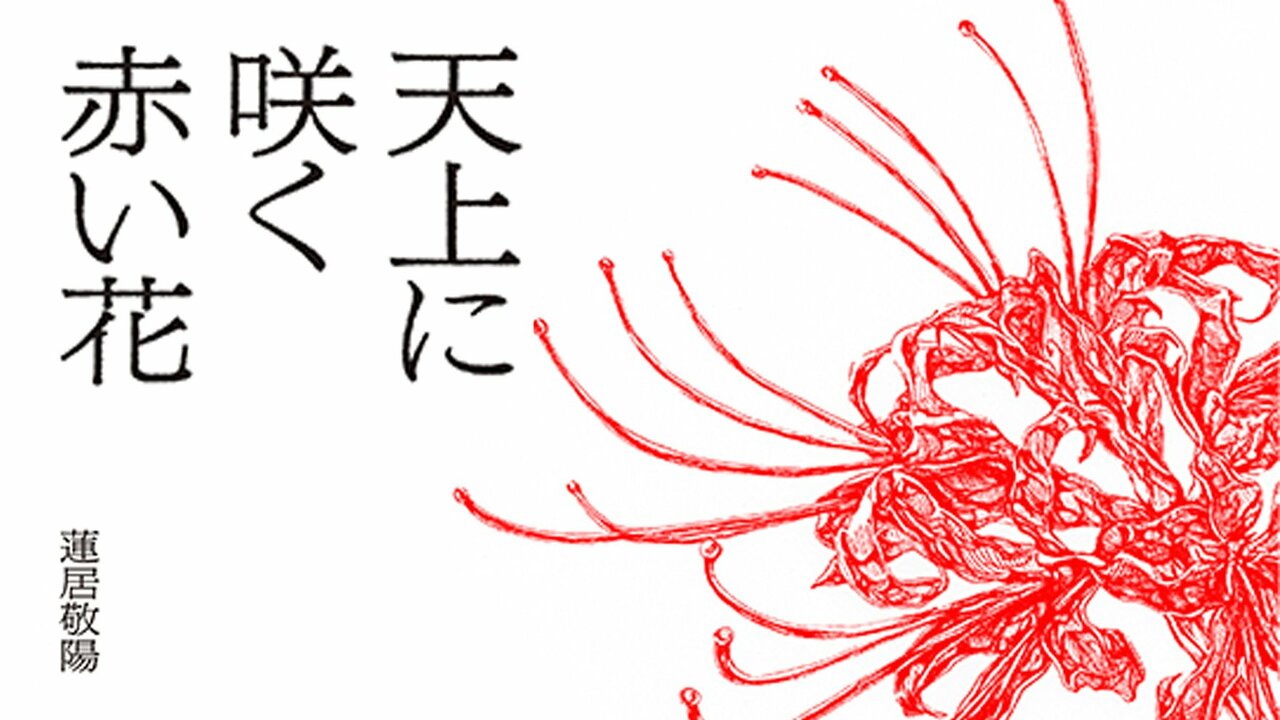一部 事件発生と、幼なじみの刑事とお巡りさん
二〇〇五年九月二十三日
高倉豊は、江藤詩織の不幸な過去に同情し、彼女が罪と考えるものに肩入れしたくなっていた。そのような気持ちが芽生えたことは、一人の警察官として、否人間として間違いではなかった。
問題なのはその気持ちに加えて、江藤詩織の両手から伝わって来る温もりが高倉豊に、彼女との一体感を与えるようになっていたことにあった。その御蔭で彼の心は、何とも言い様のない幸福感で満たされつつあった。そこには江藤詩織への同情を超えた、恋愛感情がしっかりと形成されてしまっていたのである。
「明日、俺は岡島に会うつもりなんや。会ってあいつが事件に関与していないことを確認したい」
「そのときに謝るつもりなんかな」
「何とも言えん。でも、本当のことを言うと、今更謝罪したってという気持ちもあるし、言い出し難いというのもあるしな」
「自分の罪を認めて謝罪するのは、勇気の要ることやと思う。岡島君に受け入れてもらえるかどうかも分からへんしな。私は謝れんかった。せっかく病院で一週間一緒に居たのにな」
「入院してたんか」
高倉豊は、二人は何の病気だったのだろうと思いながら尋ねた。
「岡島君がね。私は市民病院で看護師をしているの。岡島君の担当になったときは驚いて。よそよそしい態度やったかな、二人共。ほとんど話らしい話はしなかった。悪いと思っていても、それを言葉にするのは難しいんやね」
「江藤が謝ることはないんや。人の弱みに付け込みやがって」
「でも、私がそうなる原因を作って、更にもっとひどいことをしてしまったんやから」「あいつの方がひどいやろ。それが分かっているから、江藤に対して何も言えんかったんや。放火事件を起こした、気まずさの方が強かったかも知れんけどな」
「ありがとう。そんな風に言ってもらえると気が楽になるな。また会ってもらえるかな。岡島君とのやり取りを聞かせてもらいたいから」
「分かった」
二人が話し終えるそのときまで、江藤詩織の両手は高倉豊の片手を温かく包み込んでいた。