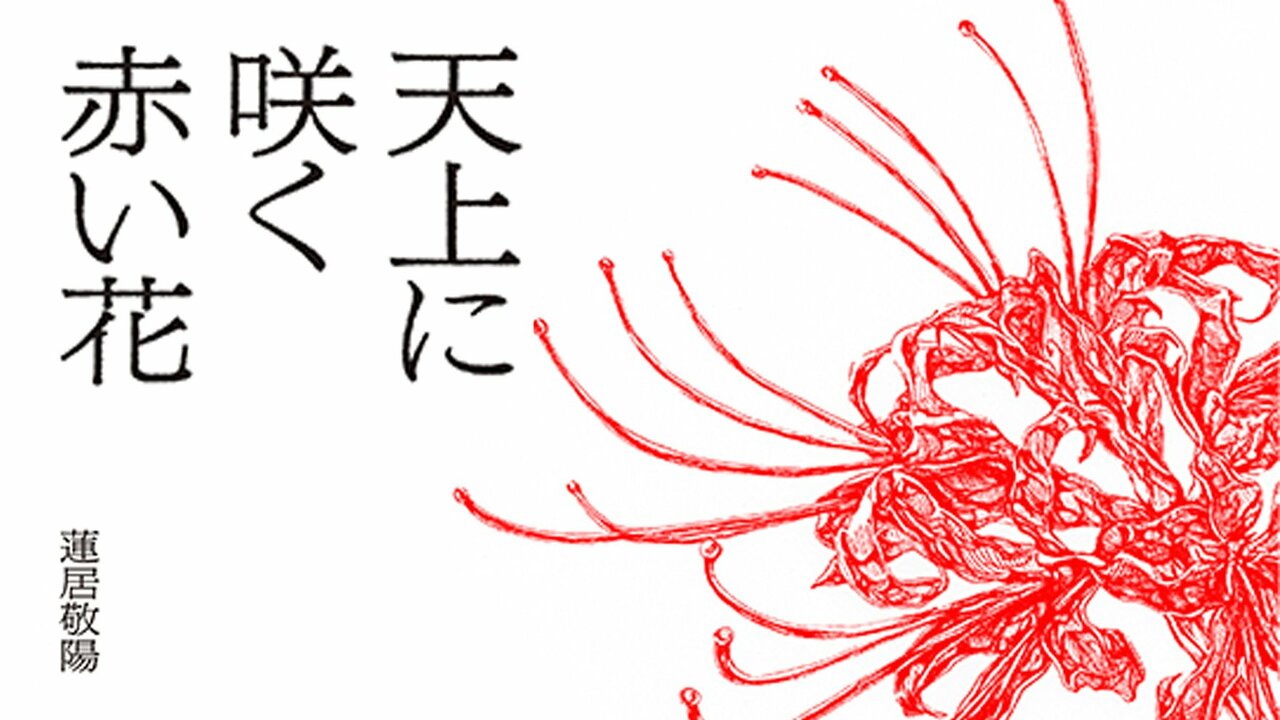二部 高倉豊、警視庁に合流
高倉豊がその部屋に入ったとき、その男は扉の直ぐそばまで来ていて、手を差し出した。高倉豊も手を差し出して握手した。彼が扉をノックした時点で、中から高倉君かと聞かれていたので、そういうことになった。
他の捜査員は出払っているのだと、その男は言った。高倉豊が警察手帳を上着のポケットから取り出して、正式に自己紹介をしようとすると、その男は握手した方の手を軽く上げて、
「いいんだ。君の書類は届いている。顔さえ確認すればね」
と言った。その態度はいんぎんと言うには、丁寧な言葉遣いが欠けていたものの、礼儀正しくはあった。高倉豊は、警察手帳を上着のポケットの中に仕舞った。そして彼はその男に促されるまま、可動式のホワイトボードの前に立った。もちろん、その男も一緒にである。
その短い間に高倉豊は、相手の値踏みは済ませていた。その人当たりのいい柔らかな物腰と、適度に威厳のある態度から、彼が係長であることは間違いないと判断していた。果たしてその男の簡単な自己紹介には、係長という言葉が聞かれた。
氏名は、ワカタベカズヨシ。五十歳前後に見える。ホワイトボードには写真が二枚、磁石で留めてあり、その下には左から、黒沢秀樹(五二)、古賀義隆(五三)と横書きで書いてあった。
「二人は別々のホテルで、九月二十四日に毒殺されそうになっている。彼岸花の球根が置いてあったんだ」
「えっ! 中原純子のときは花がそのまま」
「だから君に来てもらった。ただし、中原純子のように首は絞められていないがね」
「同一犯による、連続した事件ということですか」
「そのようだ。死んではいないから、連続殺人とは言えないが。この二人の場合は、バーボンだ。どちらもホテルの部屋で被害に遭っている。彼岸花の毒の成分は水溶性だから、予め球根から抽出したリコリンを、酒の小瓶にでも入れて携帯していれば、アルコールに少しずつ混ぜて飲ませるのは簡単だろう。あるいは先にバーボンの小瓶に混ぜておいたのか」