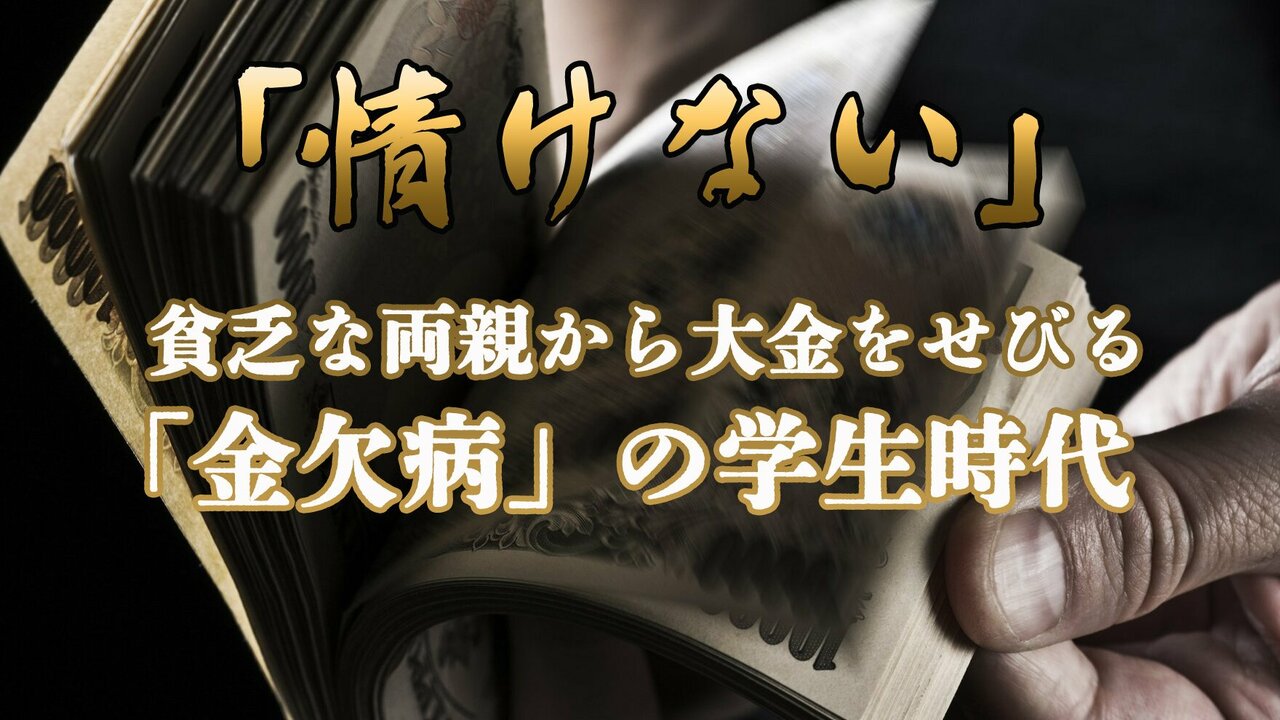食事が終わると直ぐ予備校へ行く時間が迫る。毎日の配達仲間には城間がいる。名門予備校の山手ゼミナール通いである。雄太が通う国鉄水道橋南口から徒歩五分にある水道橋予備校よりは近いのではないか。城間は雄太に
「居眠りすんなよ、しぇんしぇいの講義眠くなったら、頬をつねろよ!」
と注意するのも毎日の提言である。とは言っても予備校講師の講義を聞いているうちに、雄太には子守唄へと変わり、居眠りを始める。白河夜船だ。満腹のため、腹が張っていてしかも疲れも重なり、ついうとうと。机によだれをたらすと講師が見兼ねたのか
「おい、そこの学生、先生が今教えた講義文分かっているのか。今の講義解説は今度の試験の問題集に出る予定なのだよ」
と手のうちを明かしてしまう。興奮したのか名指しで注意される。一週間に一回は模擬テストがあるが、このような具合だから二百名程の予備校生のうちの成績は芳しくなく、上位五十位に入ることは少なく、中位を上下するのがせいぜいであった。名門予備校の神田予備校や山手ゼミナールには及ぶべくもない存在の水道橋予備校は一枚割り引く予備校であったのだ。
とは言えこういう生活が毎日続くといくら雄太でも、来年の受験には不安で希望が持てなくなるのは自明の理だ。
夏のお盆休みの新聞休刊日と重なる時に、郷里である千葉県九十九里浜へ帰省した。丁度九十九里の中程に位置する。母親の信江は息子の帰りを待ちわびていたのか喜んで迎えてくれて、雄太の好物の西瓜やメロンの果実類を大切に育てていた。井戸水で冷やした西瓜は大変美味しい。因みに水道はまだ普及していなかった。
雄太の帰省を喜ぶ風情を顔に表さない父親の敬郎は帰省するや雄太に話しかける。口数が少ないながら、いきなり
「雄太、今後どうするつもりだ」
とばかりに雄太が心の準備もしていないうちに、さも受験を諦めてくれないかとの腹づもりのように見えた。
酒を飲まない家系であるから、夕食にはアルコール類は出ない。この頃、昭和三十五年当時、食事時に郷里では武家時代と同様の風習が存在した。一人一人御膳に盛られた夕食のオカズの品々の中には、それでも家族が好物としていた、多分鮪であったと思われる刺し身も載っていた。
雄太は両親に
「新聞配達でどうにか生活できるが、配達でくたびれて学校の成績が上がらない。このままの状態だと、一流大学への入学は難しい。どうにかならないか、どうにかならないか!」
との絶叫に似た連呼で今の苦境を訴えた。暗に新聞配達の免除を願った。親父は
「何もお前に一流大学の入学など期待していないよ。分相応の大学でいいのだ。自分の頑張りで道を開けばいいのだ」
と、どうせ頭のいい家系ではないのだから、と諦めている風情であった。母親も心配してか、雄太の肩を持つように
「父さん、何かいい方法ないものかねえ」
と父親にいい知恵がないかと、早くも新聞を読む顔に向かって思案気に窺った。