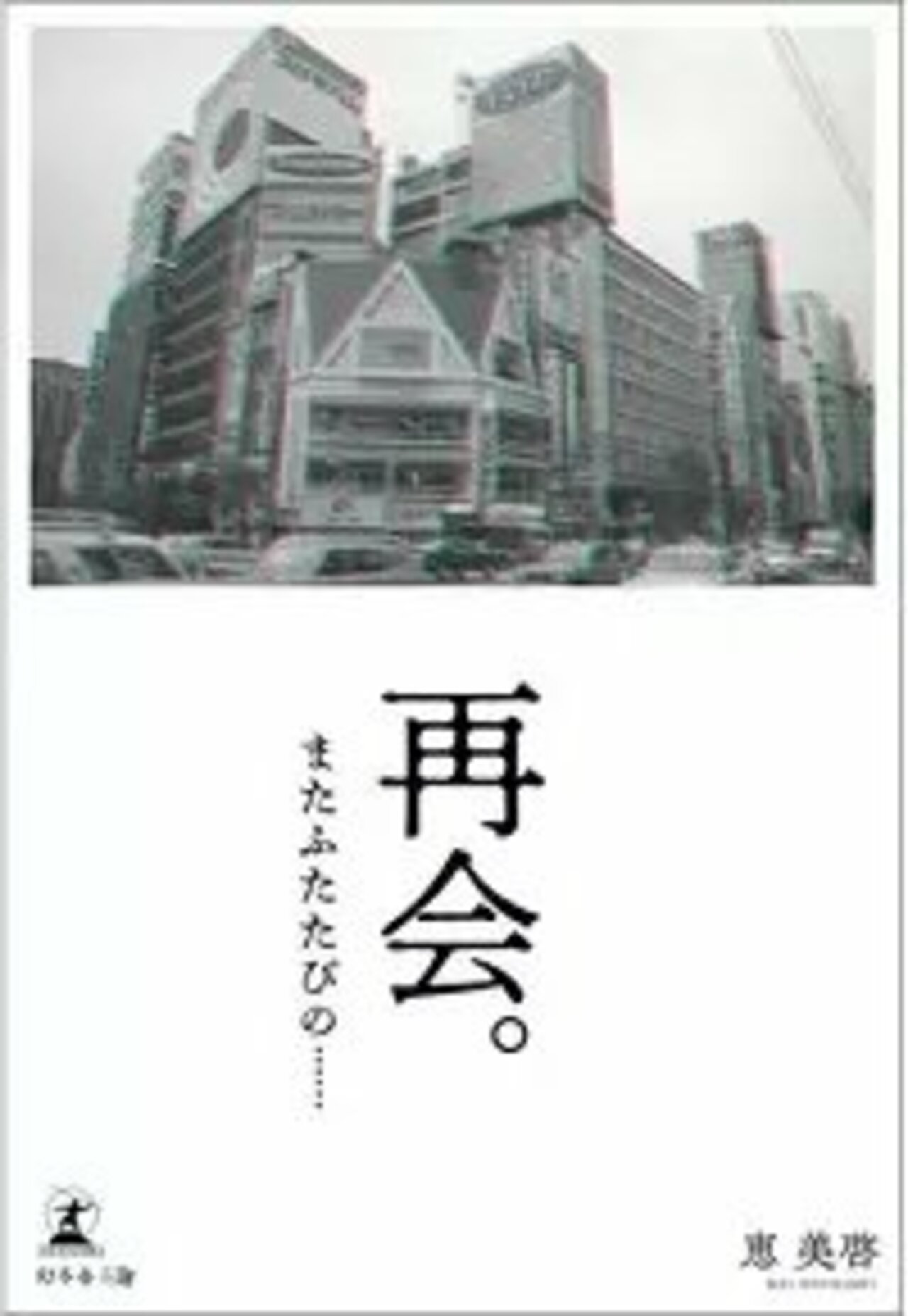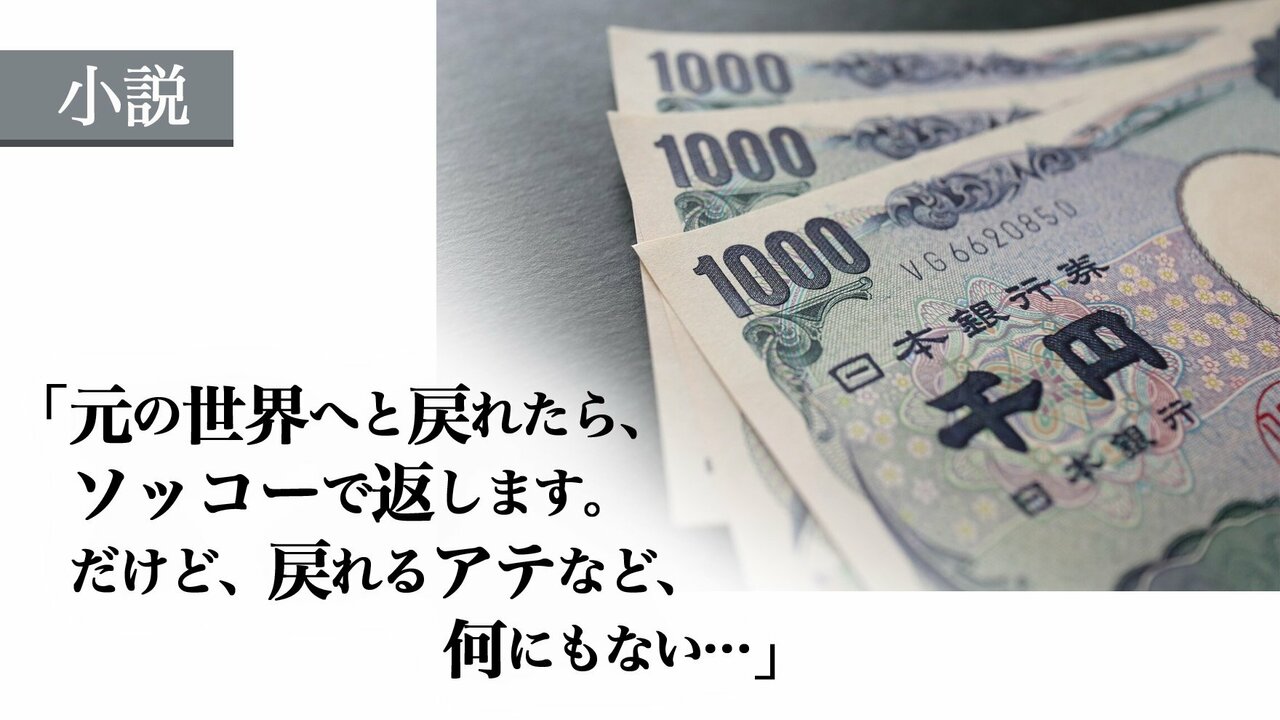プロローグ
「きょうは、担任の先生に報告に?」
智洋は、聞こえてきた会話から、そう想像し、ノッポに視線を向け、尋ねた。
「ええ、一浪しちゃいましたが、ま、何とか彼もぼくも受かったんで。残念ながら、どちらも第一志望はダメだったんですけどね」
「どこ?」
「第一志望ですか?早稲田の文学部で。二年続けてフラれました」
「あら、残念。わたしの後輩になるとこだったのね」
「あっ、そうですか……すごいなあ、あそこは難関で……」。
ズングリの言葉に社交辞令の響きはなかった。
「もう卒業されたんですか?」。
「えぇ、去年」
「六六年の入学……ですか、まだね、そのころならね……」
ズングリの言い方に智洋は引っかかった。
「というと?」
「いや、ぼくらは六九年度の卒業ですが……つまり、東大が入試中止になって、そのせいで、ぼくらの受験のときには、二年分というか、東大入試を一年遅らせた人が多くて。で、玉突きで、今年の受験は、見た目の倍率の数字はともかくとして、質が高かった、というか……」
「よくわかんない……」
「説明がダルいし、たぶん、いま受験生でなきゃピンとこないと思うぜ」
と、ノッポが窘め、続けた。
「去年、東大に行く予定の人が行けなくなったので、今年に回ってきて、実質的に従来に比べ二倍の競争率になってしまったわけです。当然のように、滑り止めというか、そもそも東大受験のやつらって次の志望に早稲田を選ぶ割合が高いので、結果的に、まあ、多くは政経ですけど、だから、政経も厳しくなってしまって、そのあおりを文学部が受けた、ということで」。
依然、話が見えない。
「おたくの説明も的確とは言えないと思うけどね……ハナから早稲田一本の、ぼくらのような受験生がワリを食った、ということです。とはいえ、まあ、アタマがよくないっていうか、しっかり受験勉強しなかったわけで、つまりは言い訳ではありますけど」
と、ズングリが自虐的に言い、ノッポも自嘲的な笑みを浮かべた。
「ああ、なるほどね」
智洋は、適当に頷き、懸命に、不得意な暗算を試みた。去年の卒業で入学を六六年とした、昭和六十六年ではない、西暦。一九六六に四を足して一九七〇、そう、かれらは一浪したというから、六九年度で、実際には一九七〇年の三月に卒業、だから、プラス一で一九七一年だというのね……いまは。
「間の悪いときに受験ってなっちまったなあ……ってね。はい、言い訳です、わかっています」
ズングリは、自分を卑下する傾向があるのかもしれない。
「でも、まあ、二人とも大学生になるんでしょ、この春から」
さっき言ってたよね、来月四月からって、だから、いまは三月。日にちが十日かはともかくとして、春だよね、三月ね。そうよ、この季節感、さっきまでと変わらないし……真冬でも夏でもないのは間違いないと智洋は確信した。
「彼は、それでも第二志望ですが、ぼくは第三志望というか、実のところ、志望してなかった大学なんですけどね。でも、二浪は、さすがに……」
やはり、ズングリは、自嘲を好むタイプのようだ。