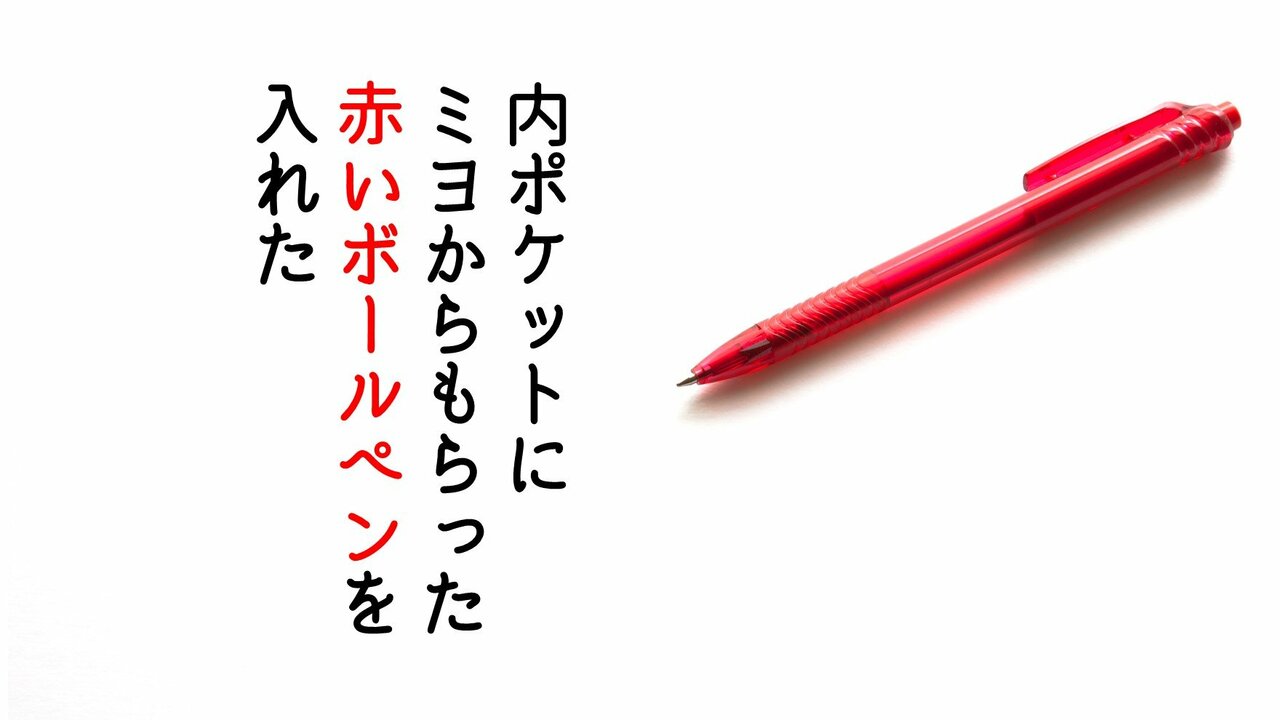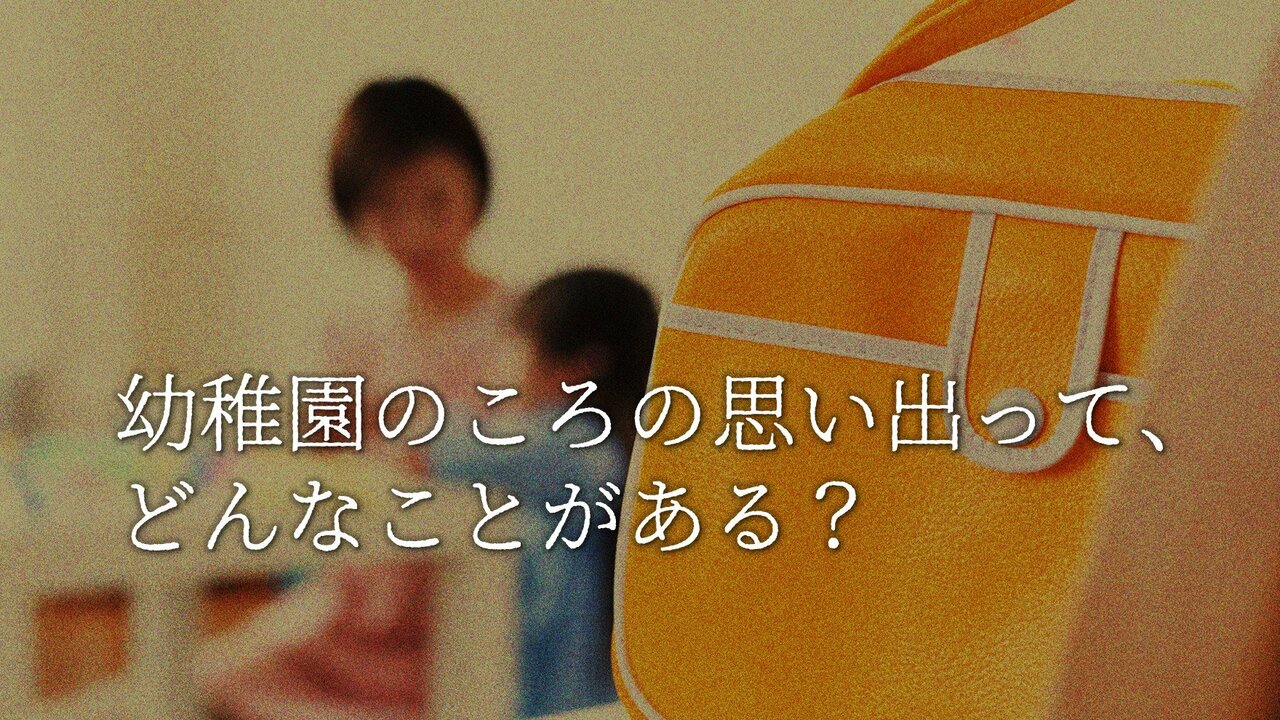第二章 希望
「ははーん……。そういうことね。今日は勝負の日なのね?」
わけがわからず、ぽかんとする達也に実花が話を続ける。
「するんでしょ? こ・く・は・く」
あっけにとられた達也の手を、実花は両手で優しく握った。
「だからずっとここで練習してたのね、一人で。大丈夫! 勇気をだして! お姉さん、応援してるから。言っておくけど、結花を泣かしたりしたらお姉さんが許しませんからね。うまくいくことを祈ってるわ! またね! キャー!」
赤くなった頬を両手で隠し、実花は校舎の方へと走り去った。徐々に小さくなっていく後ろ姿を見ながら、達也はミヨとの時間を思いだしていた。
「告白か……」
「なあに、ニヤニヤしてんのよ」
振り向くと、腕を組み膨れっ面で結花が立っていた。
「遅い、遅い、遅い、遅い、遅い! 一体、こんなところで何油売ってんのよ! 全くー」
「ごめん、ごめん。つい話が長引いちゃってさ」
結花は辺りをキョロキョロと見回している。
「お姉さんならさっきまでここにいたんだけど、走ってまたどっか行っちゃったよ」
「んもう、お姉ちゃんったら」
機嫌を損ねてはいるものの、結花はどこかうれしそうだ。
「だけど、よかった。お姉ちゃん楽しそうで」
新しいストラップがついた携帯を取り出し、結花は一度それを見つめた。携帯を胸にそっと抱きしめたが結花の表情は曇っている。
「お姉ちゃんね、中学の時、同じ塾で知り合った、とっても仲がいい友だちがいたの。二人ともこの高校に合格して、発表の日も二人でこの高校に確認しに来たんだって」
結花にしては珍しく、物悲しさを感じる。
「その友だちが、お世話になった塾の先生に報告しに行こうって。実花ちゃんもいっしょに行こうよって、誘ってくれたそうなの」
結花の瞳が潤んでいる。
「でも、お姉ちゃんは……すぐに家に帰って妹の私に合格したことを教えたいから、塾の先生には電話で報告するねって」
心配する達也に、結花は続けた。
「当時の私ってね、心配性で臆病で、気の小さい、泣き虫な子だったから。何があってもいつもお姉ちゃんが私のことをかばってくれて。この日もお姉ちゃんのことが心配で落ち着かない私のために、お姉ちゃん、早く帰ってきてくれたんだと思う」
結花の頬を涙が伝う。
「お姉ちゃんと手を取り合って喜んでいた時だったわ。家に電話が入って、その友だちが交通事故で亡くなったって。入学してからもしばらくはショックでお姉ちゃんずっと元気なかったから。だから、だから私」
初めて見る結花の涙。学校では常に、明るい笑顔を絶やさなかった結花。もしかしたらそれは、大好きな姉をなんとかして元気づけたいという結花の優しい心の表れだったのかもしれない。細くて小さな両手からあふれた結花の涙が、夕陽に照らされたグラウンドにこぼれ落ちる。結花は、濡れた手の甲で、止まらない涙を拭う。
「今度は私が……私がお姉ちゃんを助ける番なんだっ……て……どんなことがあっても泣いたりしないんだって……泣いたりなんか絶対しないんだっ……て」
結花の目から涙がとめどなく流れる。
「結花、もういいよ」
「私のせいなの。私がもっと強い子だったら、友だちは死なずに済んだかもしれない。私がもっとしっかりしている子だったら……お姉ちゃんは! お姉ちゃんは!」
「結花!」
達也は結花の、涙で濡れた手を両手で優しく包んだ。
「誰のせいでもないよ」
声をあげて泣く結花。達也は、物陰から二人に向けられた視線に気づくことはなかった。