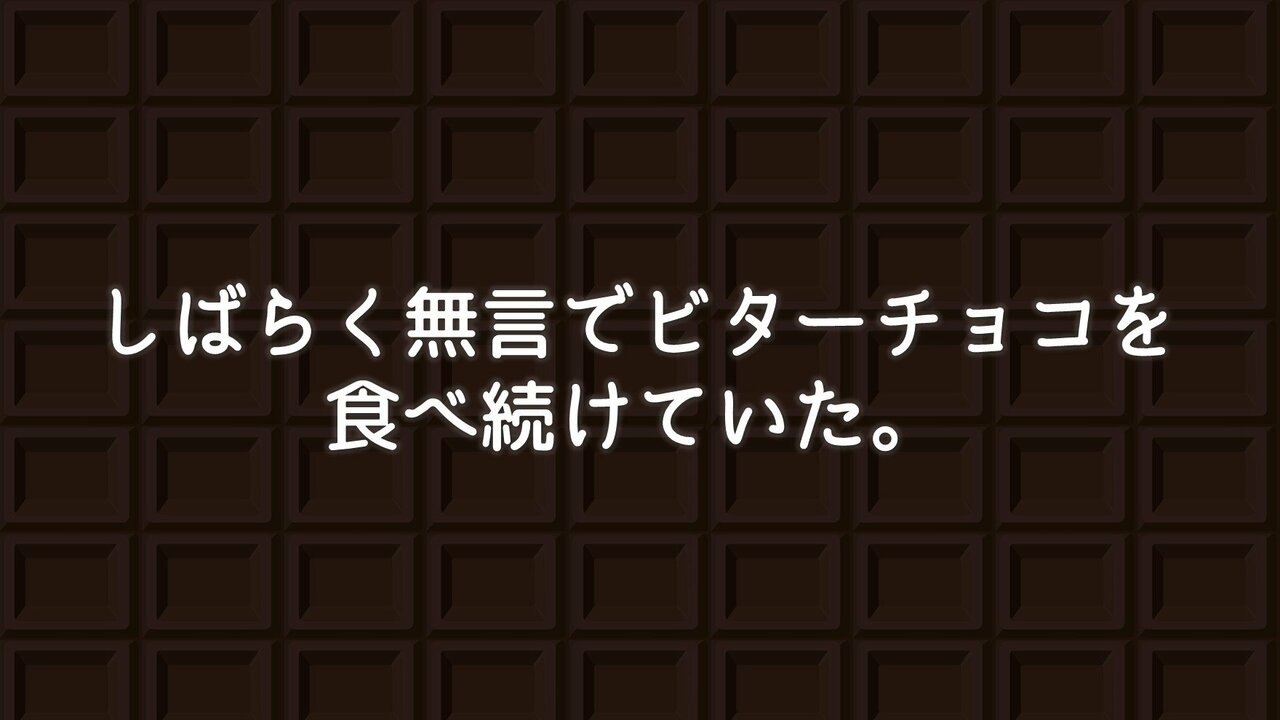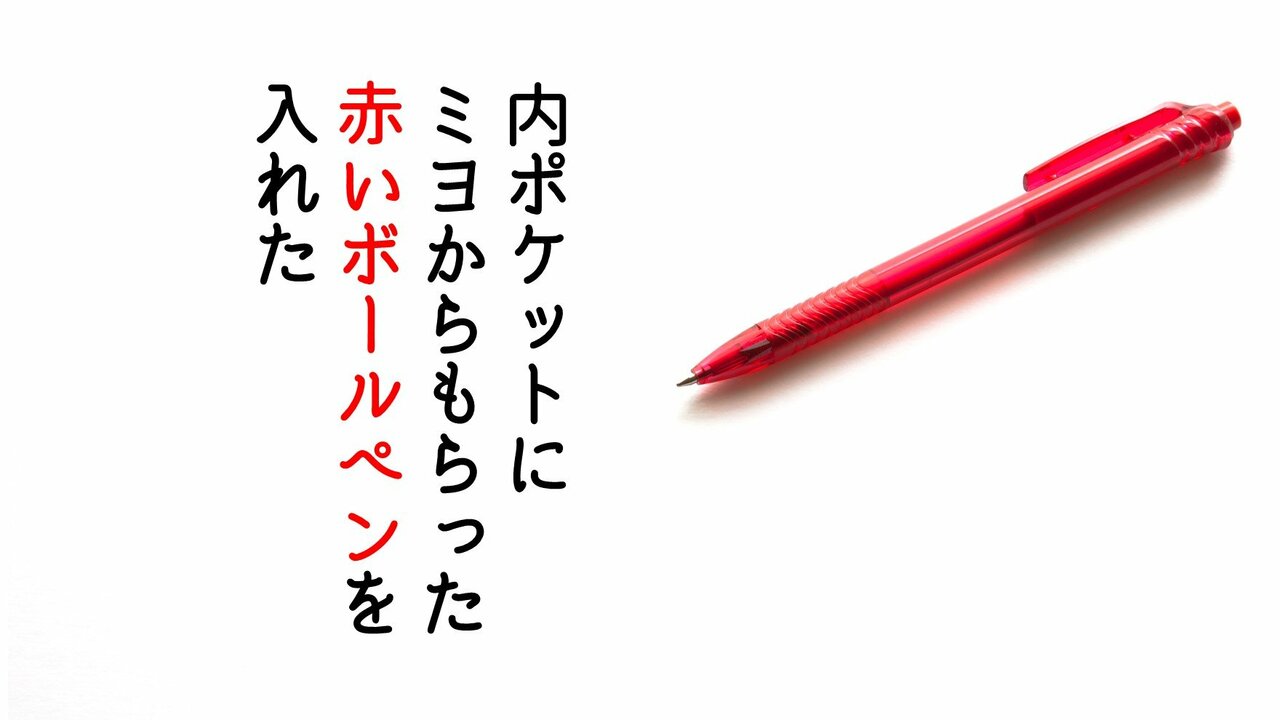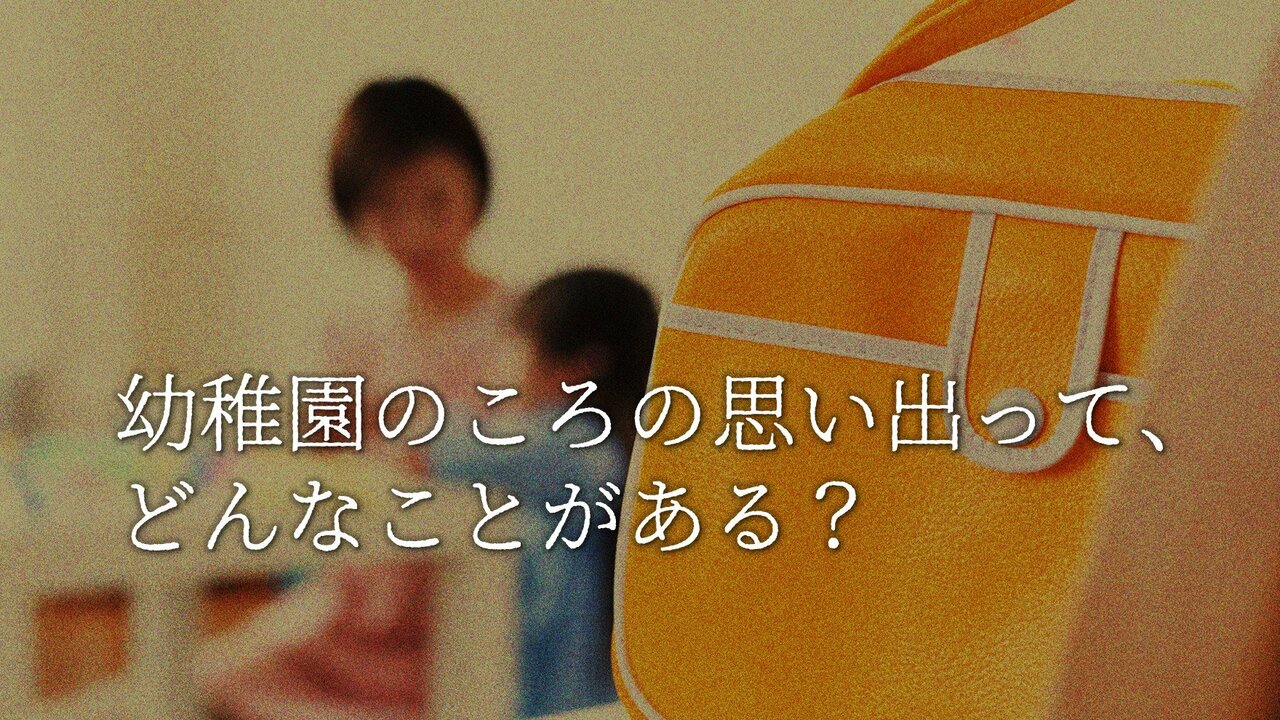第二章 希望
「うん、爽快だ」
喉を鳴らしながら炭酸を飲み干し、達也がふとミヨに目を向けると、こげ茶色の板チョコを一口サイズに割って味わっている。隣で見惚れている達也に気づくと、チョコを運ぶ手を止めた。
首をかしげ、目を見開き、パチパチと瞬きをすることで「何?」と言っているかのような仕草を見せた。
「いや、先輩があまりにも美味しそうに食べているから」
ミヨは軽くうなずくと、満面の笑みで再び口の中に広がる至福を味わいはじめた。普段は無表情なミヨのうれしそうな顔を見て、達也は癒(い)やされていた。
「好きなんですね、ビターチョコ」
ミヨの手が一瞬ピタリと止まる。
「先輩?」
達也の言葉に、再び口にふくみはじめたミヨが微笑んだ。
「うん、大好き。小さい時からずっと……」
「そうだったんですね。たしかに僕もたまに食べたくなるもんな。苦いやつ」
ミヨはそのあともしばらく無言でビターチョコを食べ続けていた。
「先輩、僕」
口を開いた達也を、またもや制するようにミヨが言った。
「達也くん、あのね」
色白のミヨの頬がかすかに赤らんでいく。
「今度から、私のこと」
達也の胸の鼓動が高まっていく。
「私のことミヨって……呼んでほしい」
胸に両手をあてたミヨは恥ずかしくて達也を直視できないのか、視線を泳がせている。
「ミっ、ミヨ……先輩」
達也も照れくさくなり、右手で頭をポリポリと掻(か)く。恥じらうミヨを、達也は愛おしく感じていた。
達也が距離を縮め、ミヨの肩に両手をかけようとしたその時、携帯のメロディが鳴った。
ミヨがすぐに電話にでてしまったのであまり聞くことができなかったが、バラードのようだ。
達也は通話し終えたミヨに言った。
「先輩、そのバラード曲、すごいかっこいいですね」
「最近ダウンロードしたばかりなの」
「なんていう曲なんですか?」
「『ブリリアント・スノー』。来月リリースの新曲なの」
ミヨは大事そうに携帯を握っている。達也は興味津々だ。
「この歌はね、もう二度と会えない大切な人へのラブソングなんですって」
「大切な、人」
達也の気持ちは再び高まる。
「大切な人がもしいなくなってしまったら私、きっとその時も、この場所から夜、星に願うんだろうな。歌詞のように『また逢えると信じて』……会いたいって」
お互いの目が合う。
「ミヨ先輩」
「達也くん」
二人はほぼ同時に言葉を発した。少し間を置いて、ミヨが言った。
「達也くん、あのね。私、実は」
遠くの方から達也を呼ぶ声が近づいてきた。
「たつやくーん……どこにいるのー?」
ミヨは達也を見つめる。
「実花先輩だ。結花っていう妹が僕のクラスメイトなんですよ。しまった、すっかり忘れてた」
「実花……? 実花」
ミヨが名前をつぶやく。
「そういえば実花先輩と同級生ですね? 知ってます? 朝倉実花先輩」
「ごめんなさい、達也くん。また連絡するから」
ミヨはあわてた様子で校舎の方へと去っていった。達也はミヨを呼び止めようとしたが、実花に声をかけられた。
「あ! いたいた。達也くん、何やってるの? こんなところで」
実花は呼吸を整えている。きっと達也を探し回っていたのだろう。
「ちょっと知り合いと話してました。実花先輩と同級生なんじゃないかなあ。あそこにいる……あれ?」
しかし、そこにはすでにミヨの姿はなかった。
「誰もいないじゃない。それに、私が達也くんを見つけた時、なんだか達也くんずっと一人で喋(しゃべ)っていたみたいだったけど」
「え? 一人でって?」
実花の言葉に達也は眉をひそめる。
「達也くんから連絡が来ないって、結花がまた怒ってるのよ。あまりにもうるさいから、クラスの出店を抜けだして、達也くんのこと探しに来たんだから」
姉妹だけあって、頬を膨らませて怒る癖は結花そっくりだ。
「ごめんなさい!」
達也はあわてて結花にメールを送る。