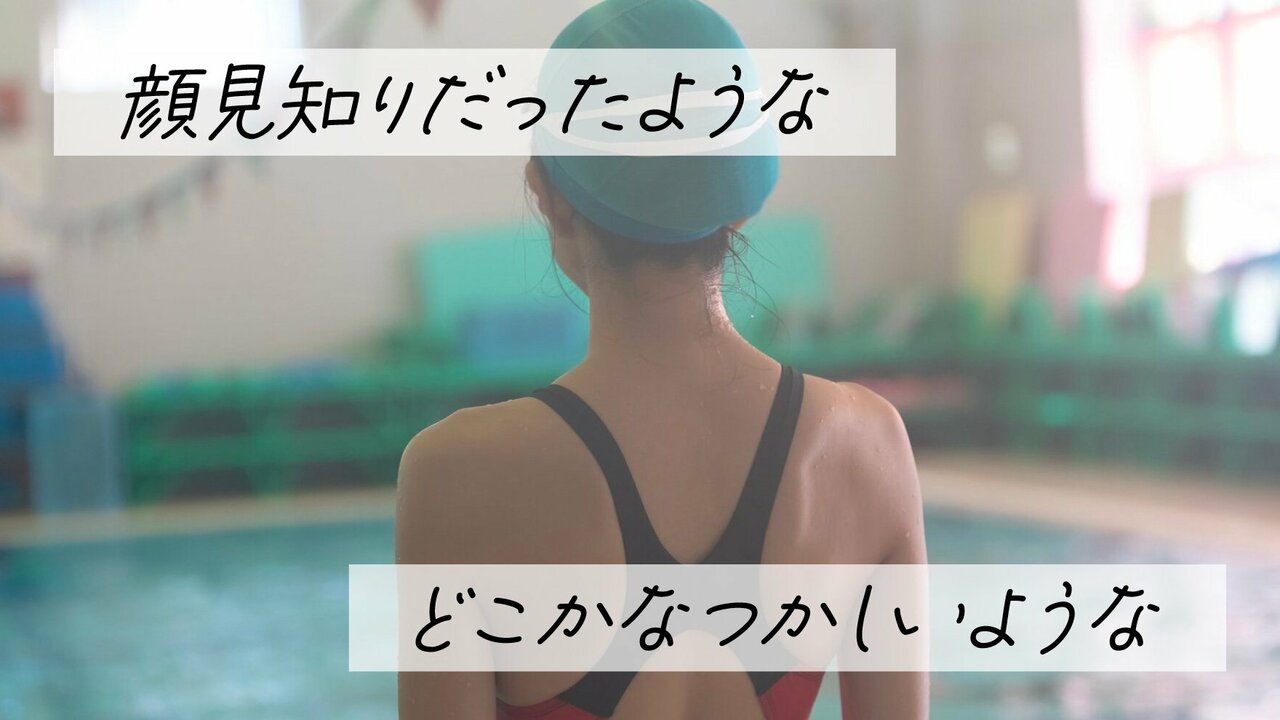自分史の「力強さ」
生まれてから執筆した当時までを振り返るオーソドックスな自分史だったが、智之輔の若い頃の話は感涙ものだった。昭和四年、長野県北安曇野郡八坂村の農家の二男に生まれ、昭和十九年、東京の立川市の飛行機製作の軍需工場に就職する。部品管理の地味な仕事だったが、戦局が低迷してきたことは、工場内の雰囲気でも明らかだった。
やがて、その整備工の少年たちからも飛行機乗りを募るようになった。いわゆる特攻隊だ。智之輔少年は御国のためと血気盛んだった。志願して、検査に合格した。
矢先に実家から兄が死亡したとの知らせが届いた。長男の兄は華々しく出征していたが、スマトラで食料不足から体を壊し持病の肺結核も発病して、軍隊を除隊された。実家に戻って療養していたが、そのかいもなく若い命を落としてしまった。
すさんでいく戦局に智之輔少年は特攻隊志願をしたことを後悔し始めていた。兄の葬儀の後、結局立川には戻らないことに決めた。二週間ほど経った後、早く工場に帰れとの電報が来た。帰ったら死ぬのは目に見えていた。
帰らなければ逮捕して軍法会議にかけるぞと脅しのような手紙が数度届いたが、わざわざ長野まで来て、連れられて行かれる様子もなかった。そうこうしているうちに終戦を迎えた。逃げのびた、智之輔少年は思った。
感動的な話だった。読みながら涙が滲んだ。自分史にはフィクションにはない力強さがある。生と死の狭間のドラマを、この世代の人たちはリアルに経験している。
癖のない文体で、誤字脱字を直していけば、大幅な校正作業は不要なように思えた。商業目的がないので、営業部に作成してもらった見積書で社内はすんなり進んだ。
数日後、西木の指示で、万里絵は教えられていた山崎の電話番号に連絡を入れた。
「とても、素晴らしい本になりますよ。いただいて読まれた方もきっと、きっと喜ばれると思いますよ」
演技的に力強さを声に込める。山崎は声を詰まらせ、沈黙した。
その後、契約や数度の校正、カバーや帯の作成確認などやりとりの必要があるたび、山崎は社に来た。郵送か電話で済むと思うことまで、わざわざ自分の休みの日に合わせて社に来るのだった。地方から上京してくる依頼主もあるのだから、熱心なのだと思えばそれまでだったが、その割にはプランを提示すると、「お任せします」の一言きりだった。言いたいことがありそうなのになかなか言い出せない、そんなシャイな雰囲気を感じてはいた。