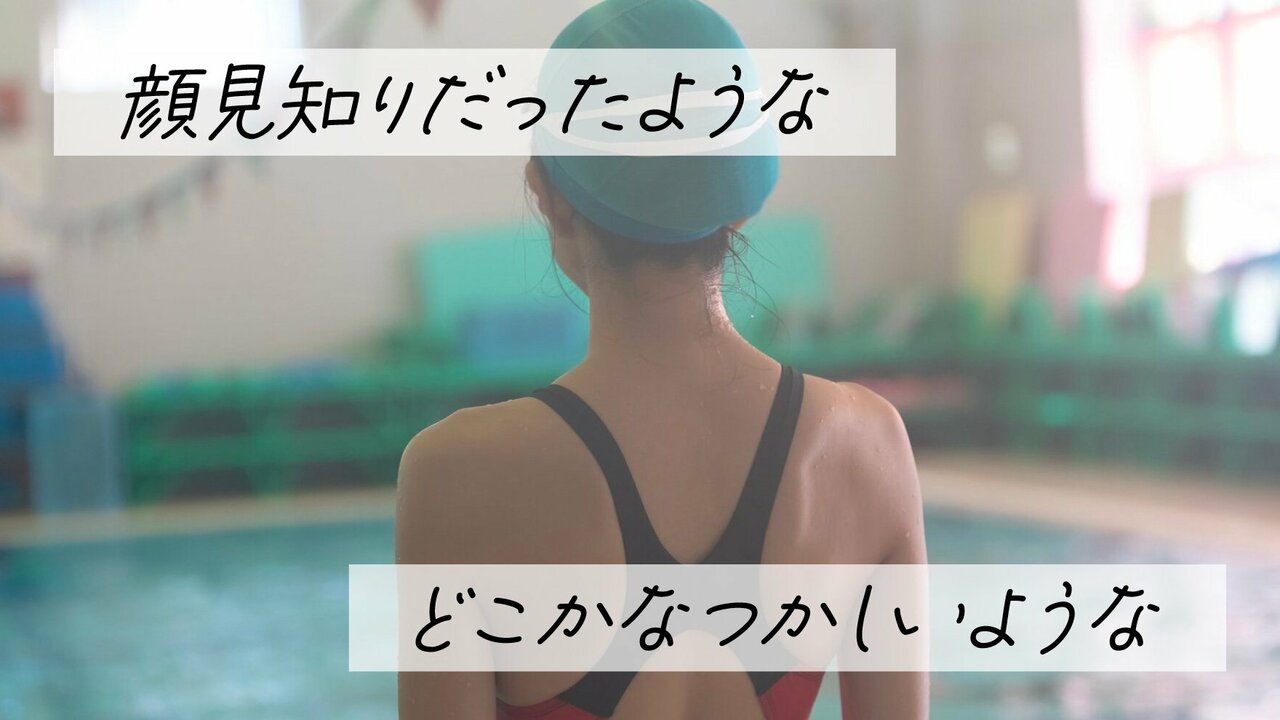何度目かの打ち合わせの時に、西木が不在で山崎と二人だけになったことがあった。
「木賊さんはこの仕事が大好きなんですね。イキイキとしている」
万里絵は不意をつかれて笑い出した。
「ええ。とにかく子供の頃から物語を考えるのも読むのも大好きで、本のとりこになってしまって。本の紙の色とか匂いとかまで大好きで」
笑い返された山崎の顔を、初めて身近に感じた。
「山崎さんは、どうして警察官に?」
仕事以外の話をしたのも初めてだった。
「子供の頃、友だちと二人で学校から帰る道で百円玉が落ちていて、長野の山道ですよ。そんなことはめったにない。見つけた自分はそれを拾って、友だちと半分わけしようと言いました。そしたら友だちがそんなことはいけないと言い張って結局二人で交番に届けました。そしたらおまわりさんが、君たちの正直な心が偉いと言って、自分のポケットから五十円ずつお小遣いをくれました。本当は、自分は不正直だったのに、いい子だと言ってもらえて、恥ずかしいけどうれしかった。こんなやさしいおまわりさんになりたいと思ったのがきっかけですかね」
「良いお話ですね」
「今じゃ、警察官がそんなことをしたら叱られますがね」
公僕、正義の味方、ヒーロー。山崎の顔に、万里絵はふとそんな言葉を重ね合わせていた。
本が完成して納品を済ませると、支払いを現金で持ってきた。経理課に案内して、領収書を手にすると、どこか名残惜しそうにその数字を眺めていた。