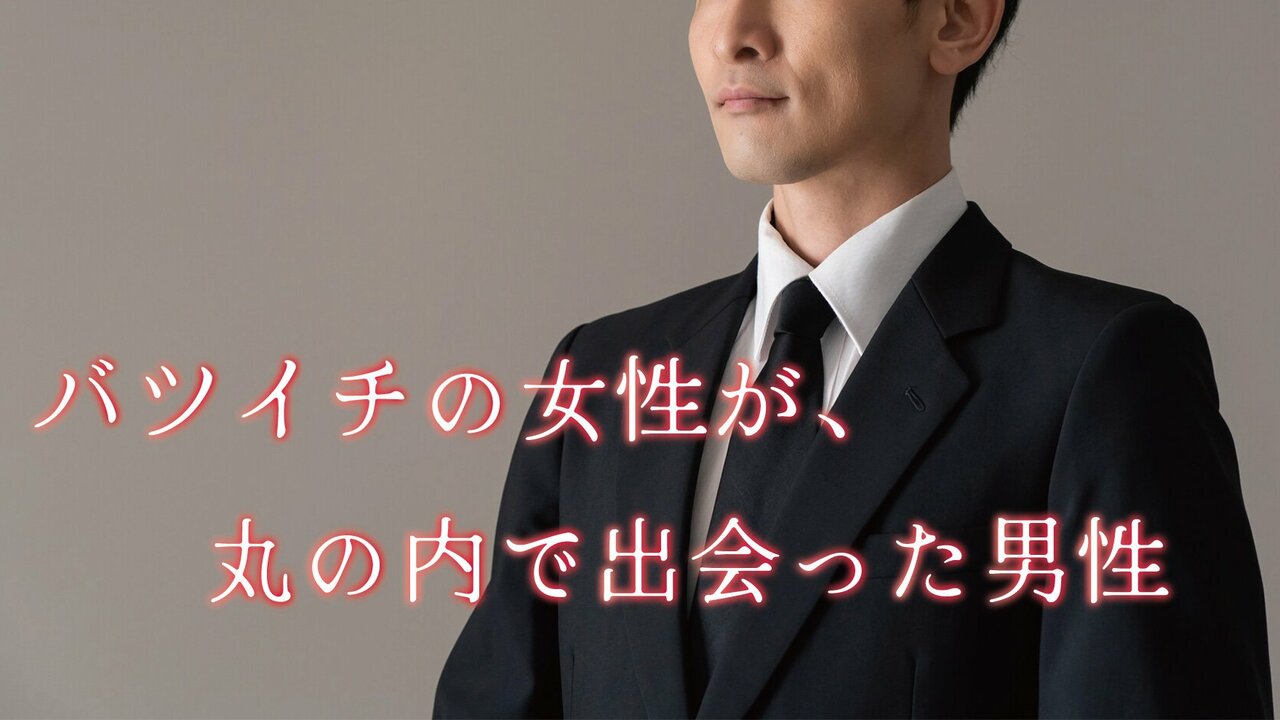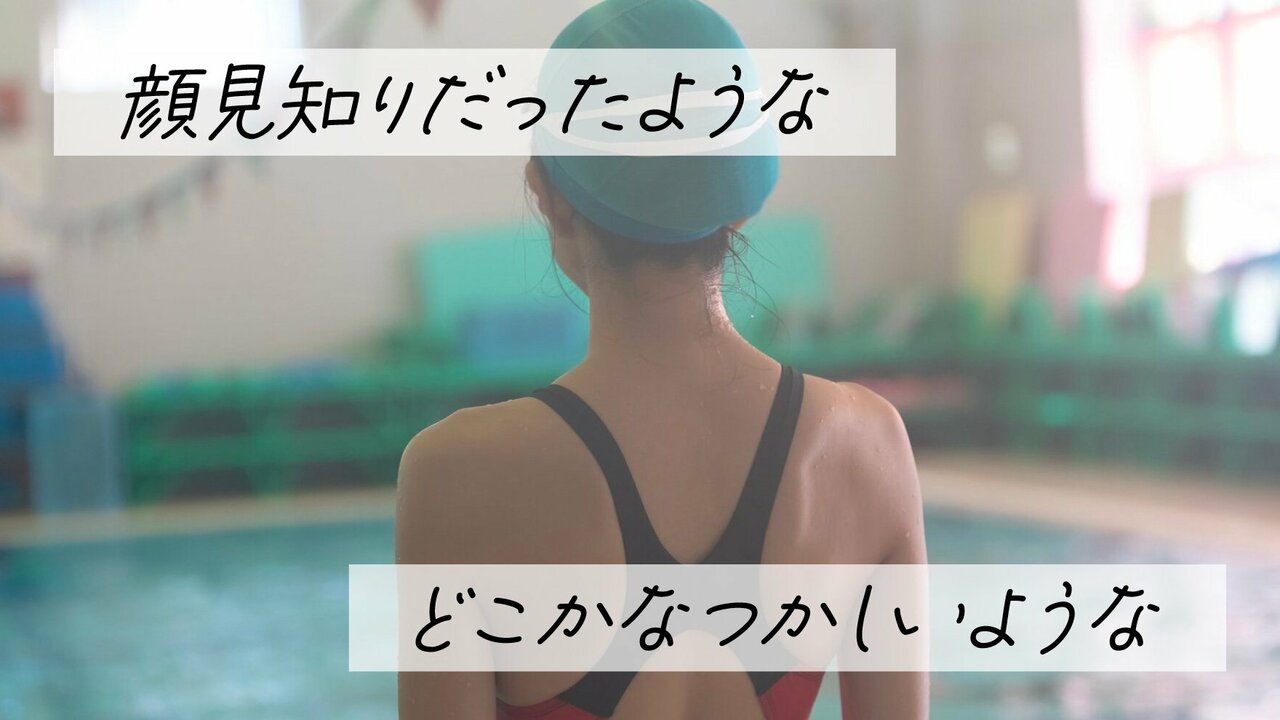二〇一九年十一月
会社からマンションまでは徒歩で三十分、乗り物を利用しないことに決めている。往復一時間の徒歩は、デスクワークの木賊万里絵にとっての貴重な運動時間だ。会社を出たのは午後七時半、勤務する出版社の企画部に届けられた応募原稿の受理リストを作ってからだった。午前中は丸の内の書店で出版説明会があったので、普段のデスクワークの時間が取れなかった。
その日の受付原稿はその日のうちに整理する、それが万里絵の仕事の鉄則だ。そうでなければ全国から五月雨のように送られてくる出版希望の原稿に対処しきれない。
読めなかった分は帰宅してから読むことにした。会議が長引いたからと、部屋に戻ってきた部長の西木英明に、持ち帰りリストに確認の印鑑をもらってから、原稿を入れたマチつき封筒をトートバッグに入れた。
「こんなに出版不況なのに、ベストセラー作家を夢見る出版希望者は後を絶たない。無理するなよ。木賊、明日は土曜日なのを知っているか?」
「そうでしたっけ?」
「おまけに勤労感謝の日だ。会社に来なくていいぞ。家で日々の勤労に感謝していろ」
万里絵は静かに笑いながらうなずいた。
「じゃ、お先に失礼します」
「ああ、おつかれさま」
ローヒールのパンプスで歩きながら、マンション近くのコンビニでビール缶を買った。
風除室の脇にあるメールコーナーをチェックしてから、エントランスホールに入ると、管理事務所の窓口から管理人が呼び止めた。
宅配便が届いていると言う。この時期の届き物には嫌な予感がする。そっけない紅いりんごの絵がプリントされただけの段ボール箱の贈り主は山崎智治、夫だった男の父親からだ。
りんご農家の元義父から届くのは、贈答品のつぶぞろいの上級品ではなく、大きさもまちまちで、色むらがあり、えくぼのようにへこんだ傷もあるものも混じっている。お金になる出荷の規格から外れた物ばかりだ。
りんごに貴賤があるわけではないが、表立っておすそわけに使うのも気がひけるような品質だったし、独りで食べきれる量でもない。管理人に礼を言いながら、いつものように「もし賄の方で使えたら使ってください」と声をかけた。
パソコンの中に入っている何年も同じ文章のお礼のハガキを出さなければならない。
歯並びの悪い口元、そこから吐き出てくるもったいぶった口調を思い浮かべると、その事務的な作業すら気が重い。明らかに万里絵との連絡を途切れさせたくない意図から送りつけているのが見え見えだからだ。
このたび、再婚しましたので、このようなお気遣いは今後無用です、とでも書いて出せたら、どんなに気持ちがいいだろう。
そのハガキを投函した後を想像してみたが、爽快というよりも、陰気な気持ちに拍車がかかった。義父とそっくりな口元の義兄・智一の、万里絵にすがるような情けない顔を思い出して、ため息が漏れた。その残像を消し去るように首を大きく左右に振った。