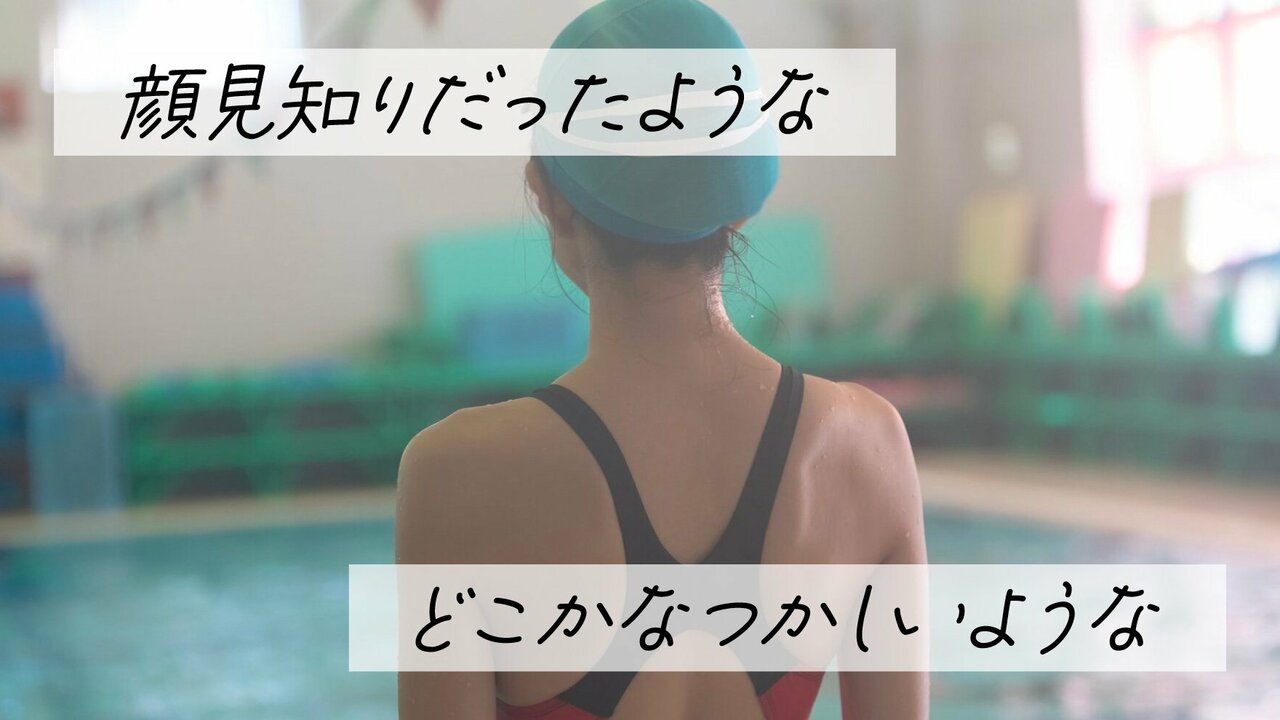「なくされた覚えがありますか?」
山崎三智治の声を聞いた時、砂漠で砂を巻き上げる風のようだと思った。そうでなければ扁桃腺を腫らすとか、喉を痛めているような乾いた声だった。
「キゾクマリエさんですか?」
受付から回されてきた電話で、自分の名前らしいものを呼んだ男の声に万里絵は戸惑っていた。
「財布を落とされませんでしたか?」
山崎は警察官で、勤務している交番の名前を言った。出版社からは二百メートルと離れていない。近くのコンビニで昼食を買う時に持って行った小銭入れが、デスク周りにないことに気がついてはっとした。昼休みには小銭入れだけ持ってふらりと出るのが万里絵の習慣だった。
「あっ」
「なくされた覚えがありますか?」
「はい」
レジの終わった万里絵の隣で、支払いをしていた高齢の女性の手から小銭がこぼれて、足元まで散らばった。それを拾って手助けしているうち、小脇にはさんでいた小銭入れを落としたのに気づかないまま、会社に帰ってしまっていたのだ。
「ピンクと言うのか、なんか織物のような布地の」
「そうです、それ、わたしのものです」
「中にコンビニのカードと名刺が一枚、入っていましてね。カードの裏に記載された名前が名刺と同じでしたので、こちらに問い合わせしてみました」
夕方、万里絵は交番に寄り、電話の主だった山崎を見て絶句した。柔道体型、乾いた声からは想像もつかないほどがっしりした男だった。
「金額はどのくらい入っていましたか?」
ソフトな対応だった。
「お昼を買ったから、後は三百円くらいしか残っていなかったかと思いますが」
「じゃ、抜き取りされたりはしていないですね」
山崎の確認に、こんなことまで心配してくれているのか、と万里絵は感心し、残金の少なさが恥ずかしいように思えた。
「ないです。ないです」
「無事に手元に戻られて良かったです」
ホームスパン製の小銭入れと共に、おおらかな笑顔が向けられた。自分の財布が戻ったとしても、こんなにうれしそうな顔はできない気がした。
「じゃ、キゾクさん。この書類に記名を」
「すみません。わたしトクサです」
「トクサ?」
「はい、木に海賊とかの賊を書いて、これでトクサと読むんです」
「はあー」
砂嵐の相槌のオクターブがさらに上がった。