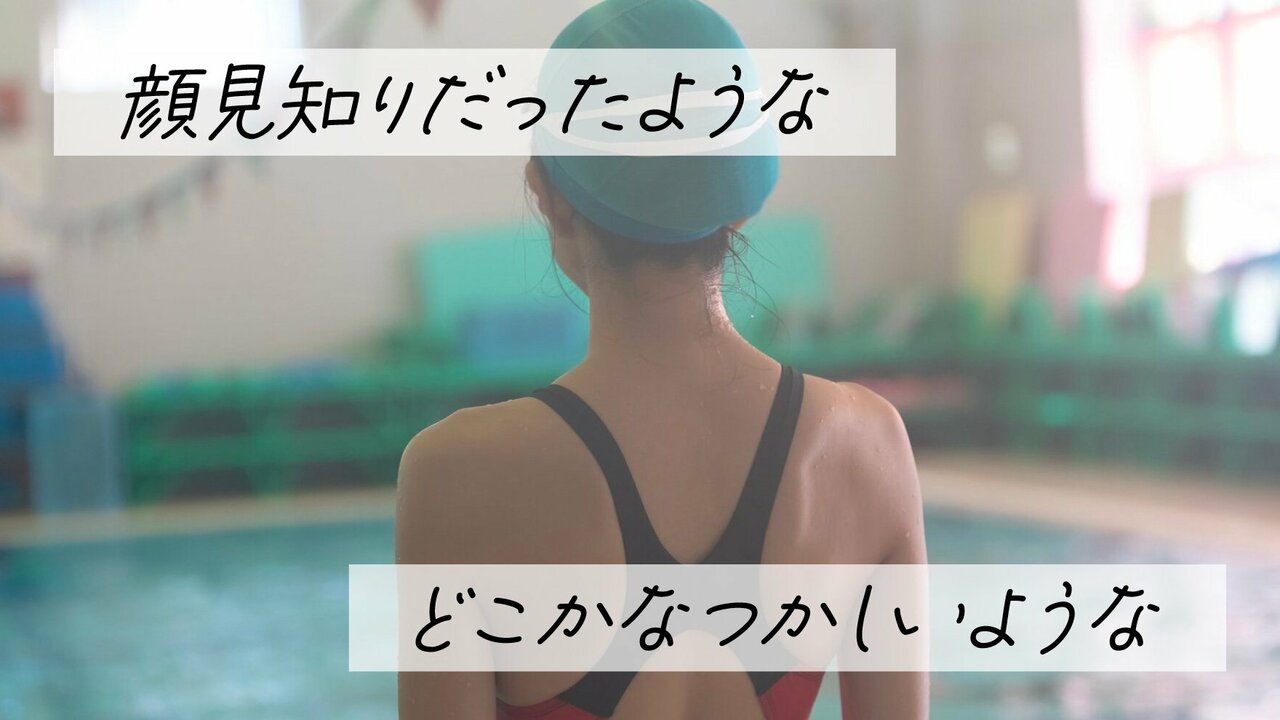二〇一九年十一月
真梨邑は地方在住のBL小説家だ。
十二年前、入社したてで編集部に配属された頃に担当補助をして以来の付き合いだった。企画部になってからも頼みごとがある時には指名で電話が来るのだ。
何を好き好んで乙女たちが男同士の恋愛を好むのかさっぱりわからないが、出版界の一つのジャンルとして確定していることは事実だ。万里絵の出版社でも白桃文庫とか名前をつけてシリーズ化され、それなりの売り上げがある。真梨邑は盛りを過ぎたきらいはあるが、軽視できない正統派の大御所だ。
どの社も申し合わせたように人気漫画家の表紙イラストを採用して、装丁もまるでコミック本のようだ。挿絵を見てもどうにも大変な体位で行為をするのが気に入らない。よほど体が柔らかくないとできないように思える。
万里絵の体験からしても、キスしたくらいで大げさに腰くだけしあえぎ出すような男はいなかった。BL小説は女性作家の手によるものが多く、その凄まじい妄想力に感嘆を禁じえない。
真梨邑は年齢未公表だが、五十代は過ぎているように見えたし、結婚もしているらしい。大人のせいか濡れ場で、男性同士でもきちんとスキンをつけたり、潤滑剤を使ったりする描写があって、リアリティーが評価できた。ただ、BL小説を好む読者からすれば、そのリアリティーは必要ないものかもしれない。
担当した当時は、真梨邑も男女間のソフトな官能小説を書いて、強固な売り上げ数を持っていた。作品が深夜のテレビドラマの原作になったこともある。ショッピングを兼ねて上京したついでに、社に訪れて直接入稿する時もあった。
担当者の佐川は男性目線からすると、官能描写が物足りなかったらしい。
「先生、もっと女性のあえぎ声を入れてくださいよ」
万里絵はぎりぎりまで品のある真梨邑の描写が好きだった。姿を現す時は髪型やファッションも、自分で作家・真梨邑蘭子をプロデュースしているかのようにスキがない。
「なにを言っているの、女はあえがせるものじゃないのよ、歌わせるものよ」
真梨邑は笑いながら、佐川の言葉を切り捨てていた。
低いおちつきのある真梨邑の声が、取った受話器から聞こえてきた。
「来月、ファンの感謝会を兼ねたクリスマスお茶会を開くのよ。あなた、てつだってくれないかしら」
担当の佐川が編集部にいるはずだが、年々腹回りが充実してワイシャツのボタンがはちきれそうな格好をしていた。ファンの手前イケメン編集者がいないのなら、まだ女の木賊を使った方がいいらしい。
「先生の本の即売会も兼ねてよろしいでしょうか?」
「そうしたければそれでもいいわよ。木賊、いつもの黒いスーツでお願いね」
使うホテルは決まっていて、以前も何度か応援に呼ばれたことがある。本を持ってこさせたり、雑用を頼んだりしたいのが本音だが、それを恩に着せようと言い回すのが真梨邑らしい。
「よろしくお願いします」
万里絵は電話口で丁寧に頭を下げながら言った。満足そうな真梨邑の含み笑いが聞こえた。