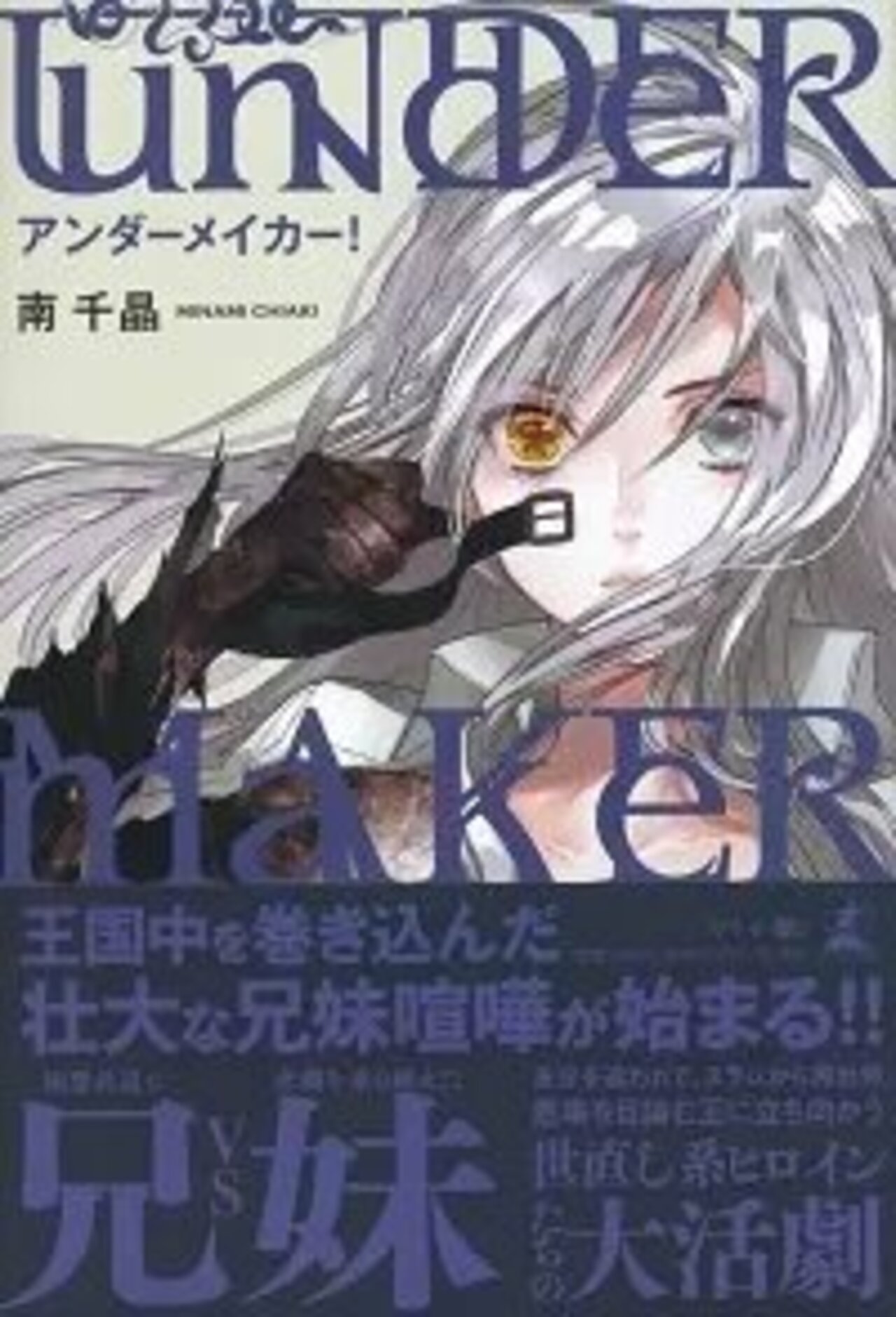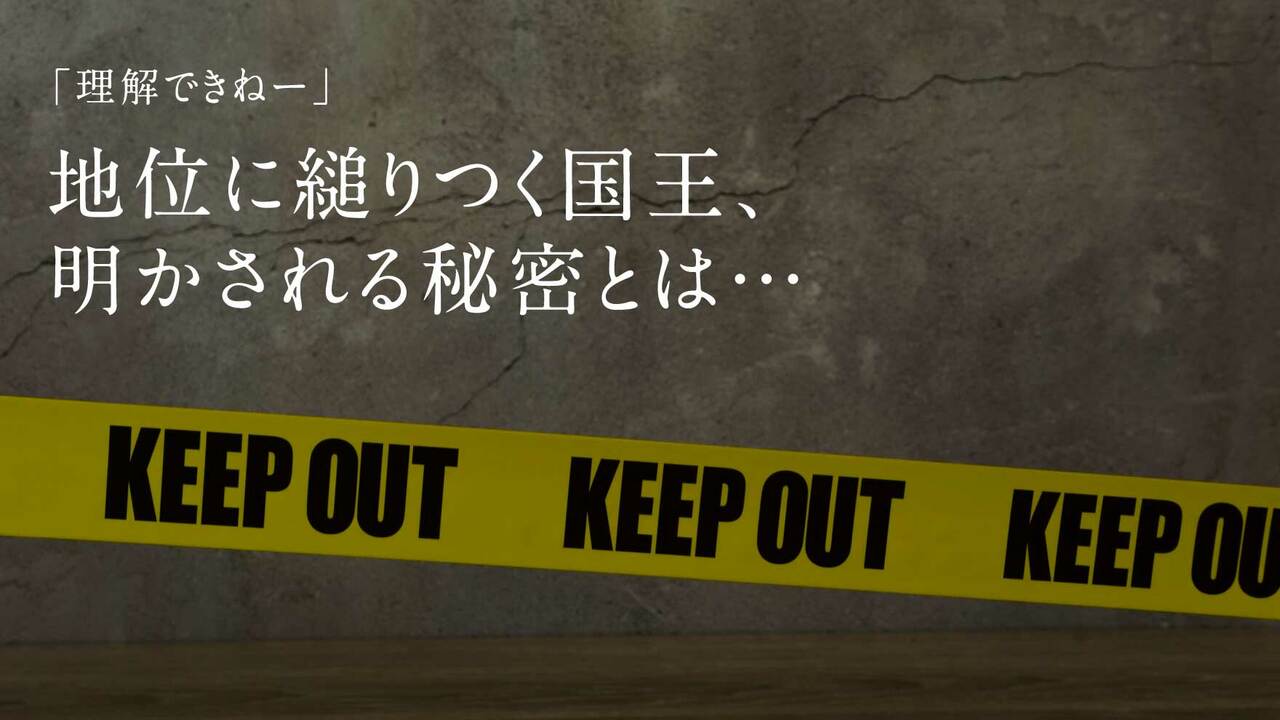【前回の記事を読む】「…二年か、もうあと二年しかあの子を守ってやれんのじゃな」
葬儀屋の居候
「お嬢。パスタはスプーンを使ってフォークで巻き、静かに食べるものだとお教えした筈ですが」
「そんな上品な食べ方してたら味なんて分かんねーだろ。好きなように食わせろ」
「いいえ、そうは参りません。幼少時より教育係を仰せつかった身である以上、お嬢には正しい作法を学んでいただかなくてはなりません」
「まーた説教かよ。飯くらいは普通に食いたいよな、浩輔」
「……あ? あ、ああ、そうだな……」
浩輔は完璧に聞くタイミングを逃したようで、目の前の食事コントを見守るしかできなかった。しかし、自分の身内の話に関係しているのだ、多少強引だろうと自覚しながらも、彼はその名刺をずずいっと彼女に差し出す。
「……なんだよ?」
「今お前、じっちゃんをお客様だって言ったな?」
「おう、聞き間違いじゃなけりゃな」
「じっちゃんは老衰で死んだんだ。でもお前は客だったと言ってる。どういう事だよ?」
ちゅるん、とパスタの最後の一筋を吸い込み、ナプキンで口元を拭いてから栗栖に机上の食事を下げさせた。
「お前、何か勘違いしてねぇか? ここは葬儀屋だぞ? 人の死に係わる仕事してんだよ」
「違う、そうじゃない。なんかニュアンスが違うんだよ。まるで、てめーがじっちゃんを殺したみてーな言い方が」
「おう、俺が殺した」
「……」
「なんだ?真相を教えてほしかったんだろ?」
今度は食後の紅茶で喉を潤している所長だ。だが、それを不意に聞かされた浩輔は返事に混乱しているようだった。何をどこから責めればいいのか―そんな所だろう。
「じっちゃんの体に傷跡はなかった! 安らかな顔をしてた! どうやって殺したんだよ!」
「どうやって、って言われてもなぁ。実演するワケにもいかねーし」
う~ん、と首を捻りながら椅子を回転させ、窓の縁に足をかける。と、当然執事からは注意の声が飛んでくるが、そんな事はお構いなしに窓の外を見やる。
そして駐車場として使用している目の前の広場に何かを見つけたらしく、彼女は紅茶のお代わりを催促した。
「お前がここに来て五日か、このビルで棺とか見た事あるか?」
「ねぇよ。葬式にまつわるものなんてどこにもねぇ」
「だから、俺は殺してるんだ。普通の冠婚葬祭を担当する葬儀屋なら貴族世界にあるだろ、わざわざこんなスラム世界に頼る必要もねぇって事だ」
―足音がする。階段をゆっくり上ってくる音が、徐々に近づいてくる。
「じゃぁどんな奴が来るってんだよ? 俺がお前らに拾われて五日経つけどよ、誰も客なんて来ねーじゃねーか」
「そうだな、例えば……」
ギ、と椅子を回し、正面の入り口を見やった。
「国王直下の国王軍中央司令部総帥・御門桐弥とか、な」
「呼んだかね?」
そこには、赤い両目で緑の軍服を着用した一人の青年が書類片手に立っていた。歳にして二十代半ばだろうか。その後ろには部下と思しき女性もいたが、やけに豊満な胸を強調している。