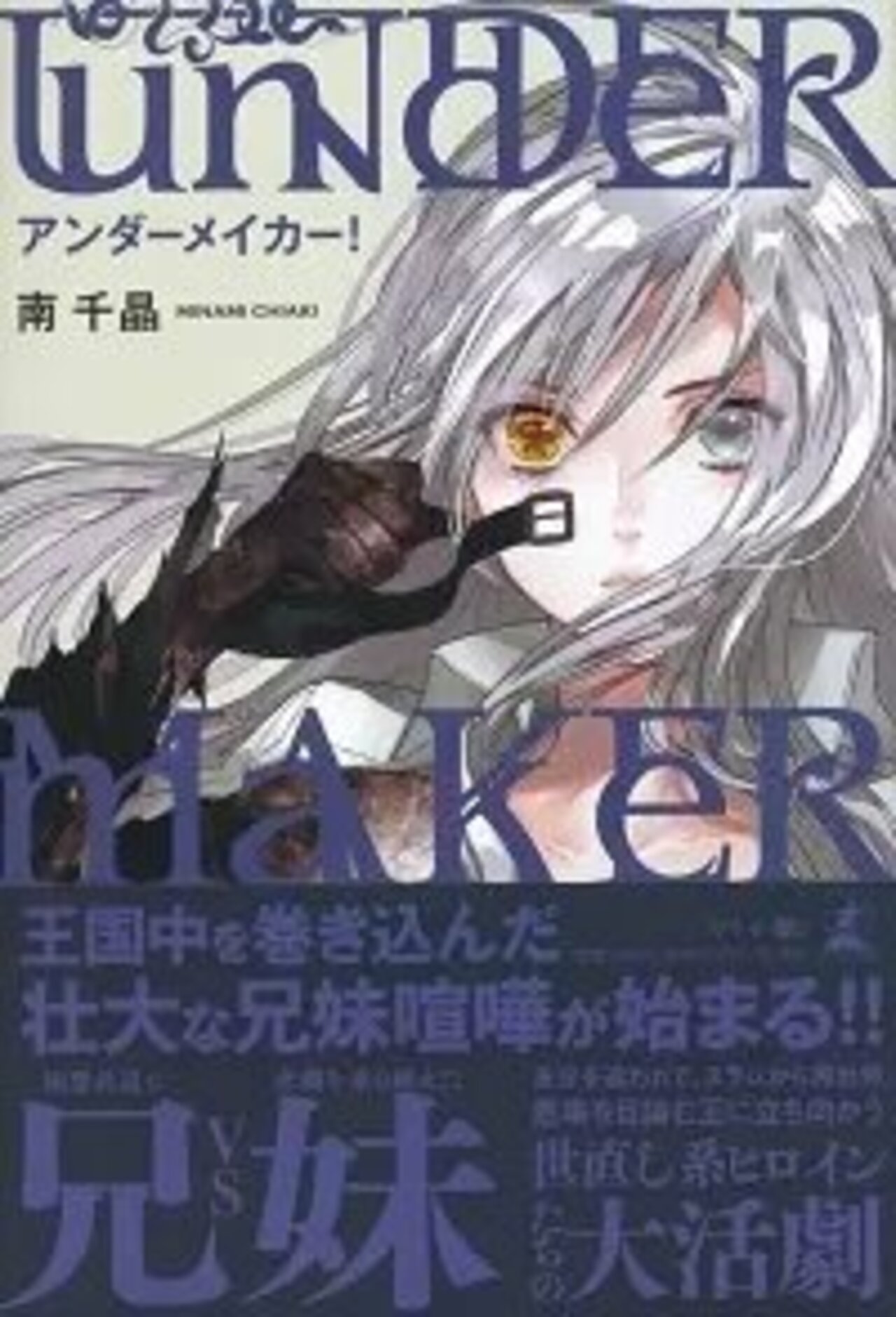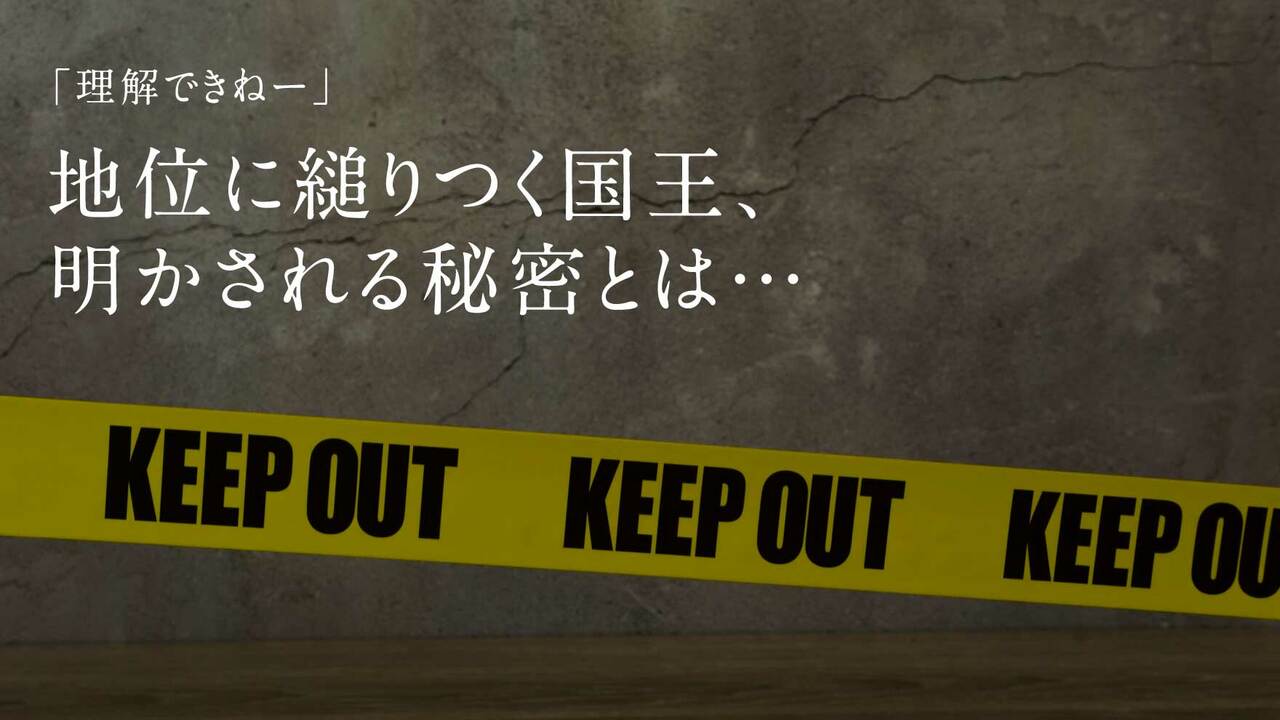【前回の記事を読む】スラム世界に落ちた傲慢な貴族…気に喰わない葬儀屋の女の元へやってきた理由とは
葬儀屋の居候
―あれは二年ほど前の事だっただろうか。
仕事で貴族世界に赴いた時、寂れた河原に一人の老人が座っていた。何も声をかける必要などなかったのだが、その背中が誰かに似ている気がして―というより、そう遠くない未来に〝死〟が近い魂を抱え込んでいるように見えたせいだ。
大した話はしていない。栗栖も同行していたし、日が暮れる前にスラム世界に帰ろうと言っていた最中での出来事だ。だが、話しかけずにはいられなかったのを覚えている。
「……じーさん。こんなとこで一人何してんだ?」
その声で、老人は初めて顔を見せてくれた。温厚そうな表情、丸まった背中、優しい目。
「着物一枚なんて寒いだろ。マント貸してやろうか?」
身に着けていた白いロングコートを脱ぎかけた時、やんわりと断られた。
「もうすぐ死にゆく身じゃ、それはお嬢さんが着てなされ」
どう見てもまだ死が近いようには思えなかった。眼帯を少しズらしてその瞳で解析してみても、まだ二年は生きられる魂を持っていた。
「お嬢」
「少し話をするだけだ。ここで待ってろ」
「御意」
従者を背後に置き、老人の隣に座った。
「ほっほっほ、奇特なお嬢さんじゃな。こんな老いぼれに付きおうてくれるとは」
「別に。一つ言っとくけどな、アンタあと二年は生きられるぜ」
「ほう。そんな事が分かるのかね」
「まぁ、な」
「……スラム世界の葬儀屋の方かの?いや、世間では〝姿を見せない救世主〟と呼ばれる御方かの」
「なんだ、知ってんのかよ。通報するならしてもいいぜ。どの道、まだ捕まるワケにはいかねーから適当に逃げるけどな」
「ほっほっほ、変わったお嬢さんじゃの。通報などせんよ。……ワシには孫が一人おっての。歳にして……そうじゃな、お前さんと同じくらいかのぉ。貴族世界の国立中学校に通っておる」
「学校なんて、俺は行ってねーな。正確には、行く事ができなかった、だけどよ」
「その孫が不憫での」
「不憫?」
季節の植物が優しい風に揺れる。たんぽぽはゆらりとその綿毛を舞わせ、それが水面に落ちて川のせせらぎを聞く。
「……二年か、もうあと二年しかあの子を守ってやれんのじゃな」
「なんかあったのか?」
「ほっほ、これは身内話なのじゃがどうしてじゃろうな、お嬢さんには話したくなるみたいじゃ。これも歳のせいかのぅ」
そして老人は空を見上げ、微笑んだ。